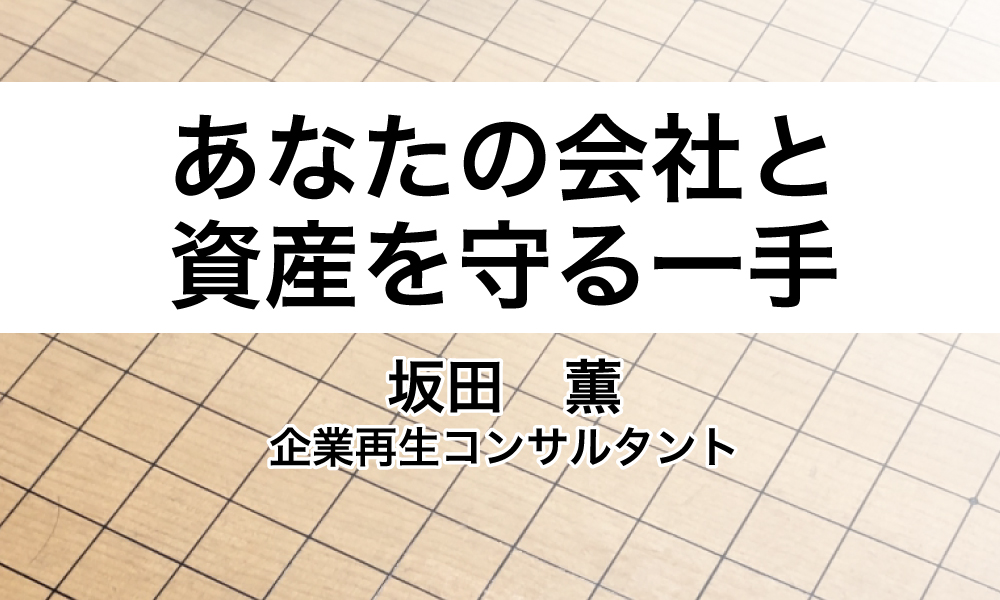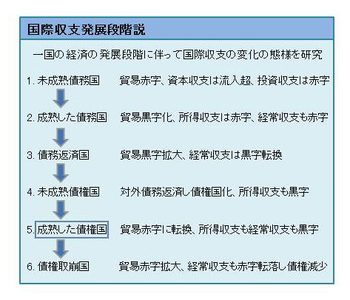諸葛亮南征の真実
三国志に登場する蜀の名宰相・諸葛亮(しょかつ・りょう=孔明)にまつわる「七縦七擒(しちしょうしちきん)」という有名な故事がある。
諸葛亮は、仕える蜀漢の皇帝・劉備(りゅうび)の死後、政情不安な南方、今の雲南省を攻めた。立ち向かったのは地域の豪族の棟梁だった孟獲(もう・かく)という猛将だった。諸葛亮は、彼を六度捕えたが、「大軍の蜀に歯向かうのは無益だ」と諭し釈放した。七度目の対戦でも蜀は勝利し、孟獲は七度目の囚われの身となったが、今回は蜀の陣を去らず、諸葛亮への忠誠を誓ったという諸葛亮の知恵を際立たせるお話だ。
この故事は、正史三国志には登場しないが、約二百年後に裴松之(はい・しょうし)という歴史家が、三国志の註として『漢晋春秋』という史書を引用して紹介し、広く世間に広まった。諸葛亮の懐柔の知恵の引き立て役である孟獲という人名も、この註に登場するだけだ。
正史には、223年春に「諸葛亮が大軍を率いて南征し」、同年秋に「ことごとく平定し、国(蜀)は豊かとなり、(北伐のための)軍を整備した」と伝えるにとどまるが、諸葛亮が、魏との決戦に向けて北伐に出る直前に背後を固める軍事行動をとったことは確認できる。
敵の弱みを握る情報力
中原の天下取りを目指す蜀に立ち向かった孟獲の立場で見ると、この歴史のひとコマからは、強敵に立ち向かう小国の生き残りの知恵が読み取れる。
雲南地方には、紀元前3世紀から少数民族の連合による独立政権が成立していた。中国の歴代政権は、「南蛮」と蔑むが、それは中華史観によるものだ。中国正史の地方異民族蔑視に基づく歴史記述は疑ってかかる必要がある。中華民族の異民族、周辺国蔑視のクセは根深いものがある。今も変わらない。
蜀の劉政権も中原から四川盆地に武力侵入した侵略政権だ。それだけに異境の地での国内の統治に腐心した。国内での徴税は強化するわけにいかず、隣接する雲南からの軍糧調達を強化した。蜀から見ての「政情不安」は、雲南の住民にとっては圧政に対する不満の爆発だった。孟獲は地方の住民をまとめ、その統率力を持つからこそ、蜀の大軍による七度の攻勢に耐えることができた。
七度にわたる講和の交渉にも、孟獲は、蜀(諸葛亮)の弱みを握り存分に活かした。まずは、蜀の優先課題が、北伐にあることだ。雲南との戦いが長引けば、蜀は、北方の魏と南の雲南の挟み撃ちとなってしまう弱みを持っている。
しかも雲南地方は奥深く、多民族が住んでいて、そこを征伐統治するには、大軍の長期駐留が必要となり、北伐の夢は幻となる。
粘り強い交渉で孟獲は。統率力を誇示し、最終的には「今後は刃向かわないから雲南の地は私にまかせろ。軍糧、兵士も出してやろう」と持ちかけただろう。そして孟獲は実行した。諸葛亮は占領地から撤兵し、役人は派遣せず、雲南を地元民の自治に任せた。知恵を言うなら、蜀びいきの視点で後世(元末から明初)に書かれた小説『三国志演義』で膨らまされた「七縦七擒」物語による諸葛亮の知恵より、孟獲の知恵が勝るだろう。
味方の強みを交渉に活かす
雲南の地は、銅や鉄などの鉱物資源が豊富で、米と共に諸葛亮が喉から手が出るほどに得たい軍需品の宝庫でもあった。また、南はベトナム、ラオス、ミャンマーとも国境を接し、またチベットへの街道の起点でもあり、交易の拠点だった。それゆえに、雲南の地はその後も13世紀にフビライ・ハンの元の領土膨張政策によって統合されるまで、中国南西部の辺境にあって南詔国、大理国と名を変えながらも交易国家として繁栄を誇る。
前回まで取り上げた古代中東の小国、ナバテア王国の生き残り戦略と同じである。敵の弱点を知り、おのれの強みを最大限に活かす。小国が軍事力強化だけで国を守れると考えるのは、愚かな幻想なのだ。
(書き手)宇惠一郎 ueichi@nifty.com
※参考資料
「正史三国志 5 蜀書」陳寿著 井波律子訳 ちくま学芸文庫
「読切り三国志」井波律子著 ちくま学芸文庫