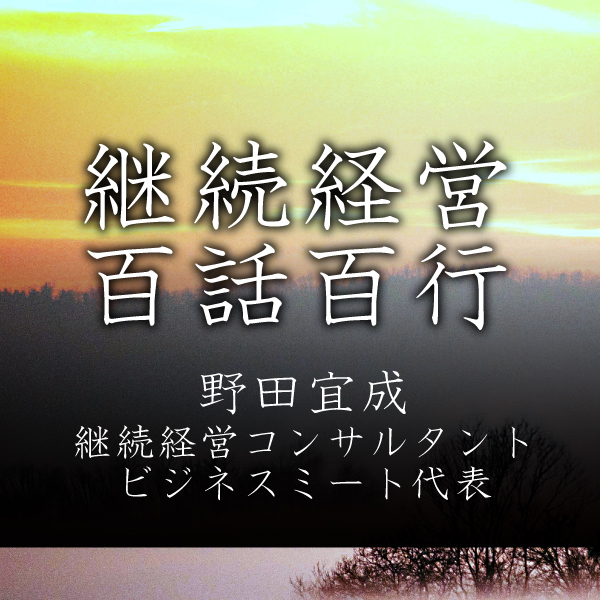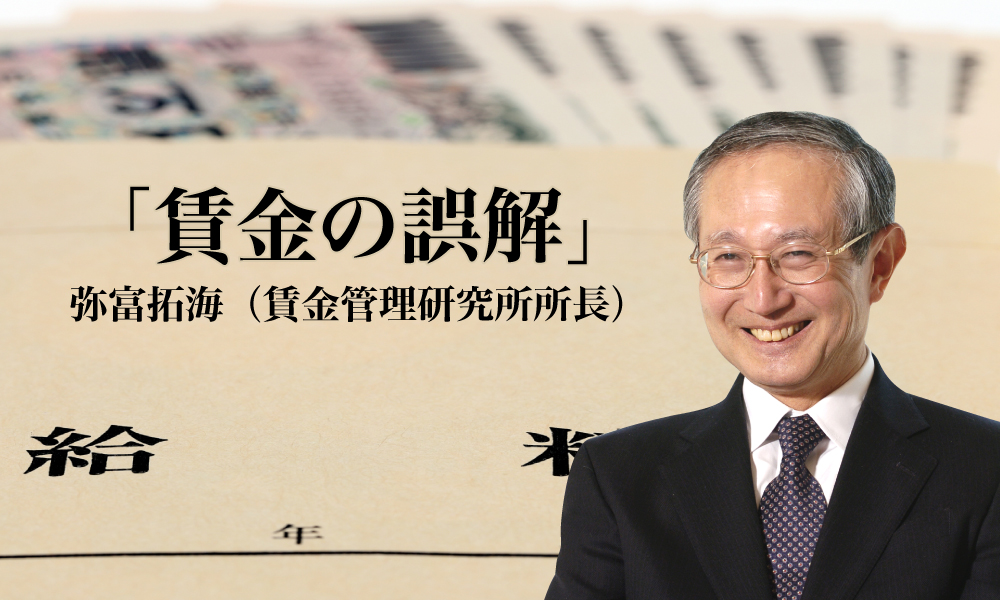来春の賃上げがニュースで大きく取り上げられています。岸田内閣による「成長と分配の好循環」に沿うかたちで税制改正大綱がまとめられました。法人課税においては、企業への3%以上の賃上げ要請に歩調を合わせ、継続雇用者の給与等支給額の増加割合が3%以上のときに、給与支給増加額の15%が税額控除できるほか、増加割合が4%以上であれば税額控除率に10%加算されます。また、教育訓練費の額が20%以上増加していれば、さらに5%が加算されます。(大企業では最大30%)
中小企業では、所得拡大促進税制の適用期限を1年延長。雇用者給与等支給額の増加割合が2.5%以上なら税額控除率に15%を加算、さらに教育訓練費の額が10%以上増加していれば税額控除率が10%加算されますので、税額控除は最大40%に達することになります。
経団連などは、こうした政府対応を好意的に受け止める声明を出してはいるものの、税制で企業を動かそうとする政府の姿勢が際立っていることもあってか、これまでのところ批判的な声も各所から聞こえてきます。4年前(2018年)の安倍政権の時にも政府から3%の賃上げ要請が行われました。この時は、経団連も「経営労働政策特別委員会報告」に3%の賃上げ要請を盛り込み、前向きに取り組む姿勢を見せました。背景には、働き方改革の推進により残業が減り、給与の手取額も減少する中で、デフレ脱却に向けた動きを加速させたいとの意向があったものと思われます。しかし、蓋を開けてみると2018年民間主要企業の賃上げは2.26%、3.0%に届く勢いは全くありませんでした。
おそらく2022年春季労使交渉も、同じ轍を踏むことになるのではないでしょうか。
今回の税制改正では、継続して働く人の給与総額の伸びが小さく、国内設備投資も少ない大企業を投資減税の対象から除くことも決まっています。法人税の優遇という「アメ」のほかに、「ムチ」も用意されているという訳です。しかし、大企業にしても投資減税のメリットを受ける会社はそう多くはありませんし、税制優遇措置についても、黒字申告企業の割合は申告企業全体の35%に過ぎませんから、その効果もおのずと限定的にならざるを得ない気がします。
「賃上げ税制」という名称で報道されてはいますが、2022年度以降の事業年度において継続雇用者の賃金総額(賞与も含む)が前年度より増えることを前提としていますので、春季労使交渉における「賃上げ」とは若干ことばの意味が異なります。春季労使交渉では、定期昇給分とベースアップ分を合わせて賃上げと呼びます。定期昇給分は「賃金カーブ維持分」とも言われますが、昇給ルールに沿って賃金が引き上げられる定昇分は1.8%程度ですので、トータルで3.0%の賃上げを実現するには、残り1.2%分のベースアップをしなければならないことになります。
ベースアップとは、賃金表の水準や賃金カーブ全体を底上げすることですから、企業としての業績向上が見込めなければ、なかなか大幅なベアには踏み切れないものです。企業業績の回復状況に関しては、「K字回復」と呼ばれているように、コロナの影響をもろに受けて非常に厳しい企業もあれば、堅調な回復を見せている企業もあり、同一業種内でも状況が大きく異なりますので、賃上げへの機運が全産業に広がるとは考えにくい状況にあります。
因みに、2021年民間主要企業の春季賃上げ率は1.86%(2020年は2.0%)でした。民間シンクタンク各社が予測しているように、2021年度の実質GDP成長率が3.0%前後を達成したとしても、コロナ前の水準には未だ及びませんから2.0%を超えるのは困難でしょう。中小企業に目を向けると、2021年の賃上げ率(経団連調査)は1.68%(2020年は1.70%)と全産業平均では落ち込み幅は僅かでしたが、製造業では「機械金属」、「電気機器」が、非製造業では「商業」が大きく落ち込みました。資源価格が高騰を続け、価格転嫁が進んでいない昨今の状況下で大幅な業績改善は見通しにくいとすれば、「賃上げ税制」をもってしても、賃上げ率の大幅な上昇は望めないものと思われます。