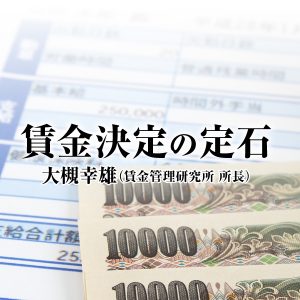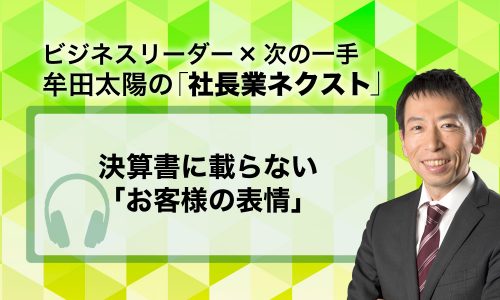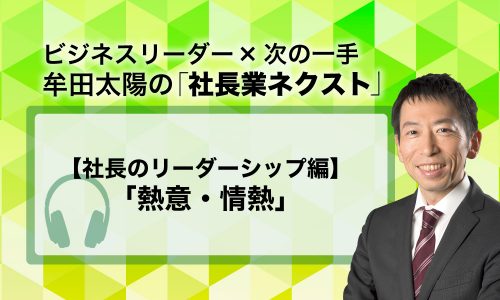5月の中旬から下旬にかけての時期は、多くの会社で社員の勤務成績に対する評価が行われています。
賃金管理研究所で推奨している成績評価制度を導入し運用している中小企業の多くは、5月及び11月の賃金計算期間を区切りとし、6カ月ごとの評価対象期間を設定する会社が大半を占めます。賃金計算期間で区切ることは出勤率の算定の面で便宜であることに加え、賞与支給日に近いタイミングで評価を実施できることで、評価結果とそれを反映した賞与支給額が一体的に捉えられ、社員のモチベーションアップに繋がりやすいというメリットがあるのです。
これに対し、事業年度に合わせて目標管理制度(MBO)等を用いた方針管理をしている会社が多い大手企業や上場企業では、事業年度(上期・下期)に合わせて評価します。3月決算の会社の場合、評価実施時期とその結果が反映される賞与支給までの時期はやや間が空いてしまいますが、社員個人への動機付けとしては、期首に事業計画から個人目標に至る目標の連鎖を確認し、業務行動のブラッシュアップに繋げやすいというメリットは大きいといえるでしょう。
さて、この働き方改革の一環として注目され、新型コロナの感染拡大によって急速に拡大したものにテレワークがあります。
2020年の緊急事態宣言以降、非対面・非接触、ソーシャルディスタンスが叫ばれる中にあって、テレワークを推進することは事務系の職種では不可避であったといえるかも知れません。実際、IT系の企業だけでなく、管理部門の職種においてテレワークを導入した会社は多く、テレワークの環境整備に対する行政による補助金・給付金等による助成も、テレワーク導入を後押ししました。
しかしながら、いざ人事評価を実施しようとすると、評価者から「テレワークは評価が難しい」との声が数多く上がってくるようになりました。
テレワーク業務では、部下の働いている姿を視認できないために、
1)評価要素・評価基準に沿った判断が下しにくい
2)勤務時間が確認できないため、生産性や効率が判断しにくい
3) 数値実績は把握できても、挑戦・工夫・改善努力などのプロセスが見えない
等の難しさがあるということなのでしょう。
ただ、これはテレワークに特有の問題なのでしょうか?
わが国では、評価者たる課長クラスの多くが、プレイングマネージャーだといわれています。例えば、営業課長は、ライン課長とはいっても営業課のマネジメントに専念するのではなく、自らの取引先と業績目標をもって収益に貢献することが求められます。このような状況下では、上司として常に部下の仕事ぶりを直接自分の目で確認したり、その進捗状況をタイムリーに把握したり、問題点を適時適切に指摘し注意や指導をしたりすることは、日頃からよほど意識して取り組まない限り、そう簡単にできることではありません。
それでも部下の育成責任を負う上司および評価者として、部下の仕事ぶりを正しく把握するように努め、良いところ悪いところを見極めて、部下の育成計画を立案し実行しなければならないのは管理職の普遍の責務です。これは、テレワーク下でも同じことです。
では、どうすれば良いのでしょうか?
基本的には、それぞれの会社や職場ごとに知恵を絞って有効な方法を確立することにはなりますが、例えば「Webツールを使用した個別面談や1on1の定期開催」、「隙間時間を部下との対面のための時間に優先的に確保する」などの対応も考えられますし、書面やメールによる業務報告(日報・週報など)から双方向コミュニケーションを意識したWebミーティングにシフトするなどの対策もできるでしょう。
評価制度との関係では、評価者である管理職が、評価要素や評価項目(着眼点)に沿った業務確認を日頃から行なっていただくのも有効な方法です。
セミナー等でもご紹介している賃金管理研究所作成「成績評価基準書」では、5つの評価要素ごとにそれぞれ4つの着眼点を設定し、全20項目で評価を実施しますが、管理職者が個々の着眼点について「自分は評価者として正しい評価を下せるだろうか」と自らに問いかけ、不安な項目や着眼点に対しては、積極的に情報収集をしていただくことをお勧めします。
例えば、就業状況に関する「仕事のやり方について改善工夫に向けた努力をしたか」という着眼点に対して、部下に対する判断材料が十分でないと思われるようであれば、面談などを通じて部下の業務改善に向けた行動計画や取組みについて確認し、効率アップに関する考えや見通しを聞くなどすると良いでしょう。その際、部下への具体的な支援やアドバイスも併せて行なっていただくことをお勧めします。そうすることで、その後の部下の業務行動がより印象に残りやすくなりますし、評価結果に対する部下の納得感が増すことにも繋がります。