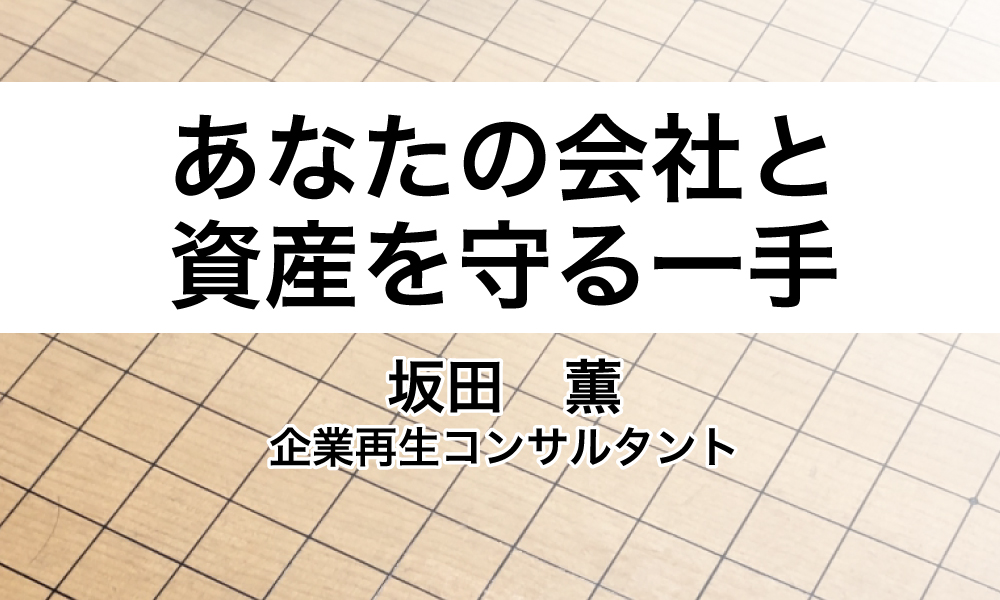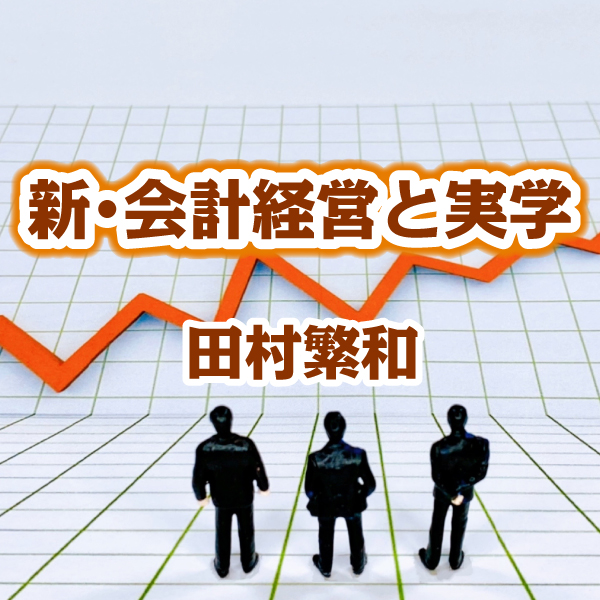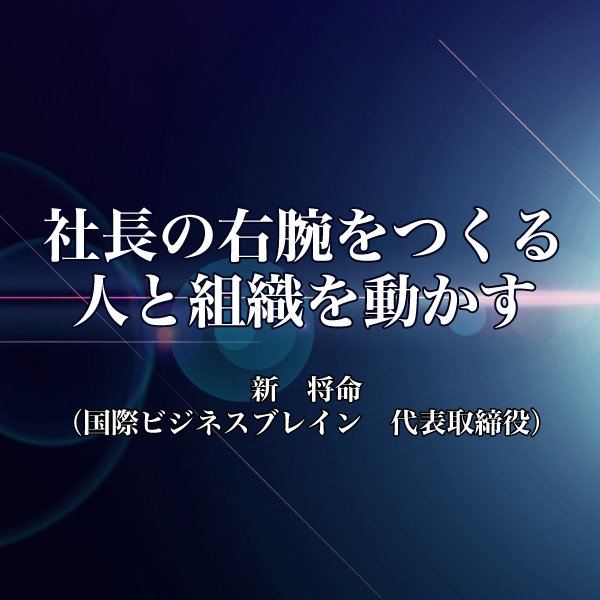順風満帆に進んでいる現在の仕事を手放し、全く知識のない分野に一人で飛び出すのは、想像を絶する勇気が必要なことだ。
昭和43(1968)年、民間では初の肢体不自由児のための社会福祉施設「ねむの木学園」を静岡県で開設した宮城まり子(1927~2020)。
裕福な家庭に生まれたものの、父の事業の失敗や母の死などで弟と共に親戚の家に預けられ、小学校卒業と同時に歌手を志して吉本興行の人となった。
戦争末期の昭和19(1945)年、17歳で初舞台を踏み、自らが座長となり、一座を率いての地方巡業中に終戦を迎えた。その後、歌手デビュー、『ガード下の靴みがき』、『毒消しゃいらんかね』、『夕刊小僧』などの歌を昭和20年代後半から30年代にかけて連続ヒットさせ、NHK紅白歌合戦にも合計8回出場している人気と実力の持ち主だ。
その多才さは歌だけにとどまらず、舞台では主に「コメディエンヌ」として、喜劇に巧みな才能を発揮したほか、自らの激しい半生を舞台化した『まり子自叙伝』は昭和33年に日比谷の芸術座(現:シアタークリエ)で上演され、3か月のロングランを記録した。35年に自らが脳性麻痺の子供の役を舞台で演じたことをきっかけに、障がいを持つ子供の教育や生活の場が整っていない現実を知り、独学で猛勉強を始めた。
その間もスター女優として帝国劇場や東京宝塚劇場で活躍をしていたが、昭和43年、「社会福祉法人」としての認可を取得、54年には学校法人「ねむの木学園」としての認可を得た。そして、全国から障がいのある子供たちを預かり、我が子のように慈しみ育てる「ねむの木学園」の園長となった。
*
徐々に「ねむの木学園」としての仕事に勢力を注ぐようになる一方で、女優業は引退同然となった。世間では、「女優の道楽で、いつまで続くものだか」などの心無い声も聞こえたが、宮城は屈することなく、必要があれば所管の大臣に直談判に赴くなど、精力的な活動を続けた。
それに加え、女優の感覚を活かしたアイディアで世間への認知度を高めた。「ねむの木のこどもたち」の豊かな感性を知らせるコンサートや絵画展、日々の生活のドキュメンタリー映画『ねむの木の詩』などの監督として自らメガフォンを取るなど、活動の幅は広がった。
昭和59(1984)年に、フランスのコメディ・ミュージカル『イルマ・ラ・ドゥース』を演じたのが、女優としての事実上の完全な引退となった。この舞台の明るい輝きと、裏に漂う哀しみは、今も鮮やかに脳裏に焼き付いている。
*
私は、彼女の稀代の女優の才能を奪ってまで打ち込まなくてはならない仕事は、本来は国や自治体が主導するべきものだと感じた。こうした施設の運営は他にできる人はいても、「女優・宮城まり子」は一人しかいないのに、と思いながら彼女が演じるイルマを観ていたような感覚がある。もちろん、この時点で引退を明言していたわけではないが、舞台も間が空けば勘も鈍る。また、すでに60歳に近かったことを考えれば、結果として最後の舞台になった作品を観られただけでも幸福なのだと思っている。
*
その後、イベントなどで何度かお目にかかったが、忘れられない言葉がある。「優しいことは強いこと」。宮城は笑顔が可愛く、愛らしい喋り方は晩年まで変わることがなく、多くの人に優しい慈母のような愛情を注いだ。もちろん、自らが面倒を見ている学園の子供たちも同様だ。しかし、優しい一方ではなく、厳しく子供たちを叱りつける場面を目撃したこともある。女優として厳しい芸能界を生き抜いてきた矜持と、優しくなれるように子供たちを強くしたいとの想いから出たのだろう。
自分の子であろうがなかろうが、子育ては自分の都合で辞めることはできない。まして、ハンデを背負っている子供たちが生きにくい世の中である。いつか自身がこの世から去っても、自分たちの足で立っていられるように、それが子供たちへの真の優しさだったと私は思う。
同時に、こうした難事業を、人気女優がその座を捨てて、髪を振り乱さねばならないほどに日本の政府や自治体が鈍感だったことに哀しみをも覚える。世の中は殺伐とした空気を深め、誰もが息苦しい時代になった。この時代を予見していたかのように、宮城まり子は「優しく」なるために「強く」ならねばならないことを、実践しながら教えたのだ。予見ではなく、彼女の経験から来るものだったのだろう。
*
平成24(2012)年11月、銀座・ヤマハホールで『シャンソンの黄金時代』という一夜限りの贅沢なコンサートが催され、多くのゲストが登場した。85歳の宮城は、白い衣装に身を包んで車椅子で登場し、「28年ぶりの歌手なの」と客席を笑わせながら、フェデリコ・フェリーニ(1920~1993)監督の映画『ジェルソミーナ』の主題歌『道』を歌った。歌は音程もはずれ、お世辞にも巧いとは言えなかったが、車椅子とは言え元気な姿を見せ、ユーモアを交えたお喋りで一曲を披露した宮城に、客席は大喝采だった。
驚いたのは、カーテンコールで両腕を支えられ、登場した宮城が、音楽に合わせて踊っている途中で、いつの間にか自らの足だけで立って踊っていたことだった。その微笑みは、さながら童女のようにあどけないもので、多くの艱難辛苦を超えた果ての、すべてを包み込むような明るい笑顔を忘れることはできない。コンサート終了後のロビーには、観客を見送る宮城のそばの人だかりはいつまでも消えずにいた。疲れているだろうとは思ったが、去り際に挨拶をすると、「今日は本当にありがとね。優しくね、優しくね」と舞台と変わらぬ明るさで交わした言葉が今生の別れになった。
もう、「宮城まり子」と聞いても、かろうじて「ねむの木学園」の園長としての認識はあっても、女優時代を知る人は少なくなった。今はただ、懐かしくあの顔と「優しいことは強いこと」の言葉を思い出す。