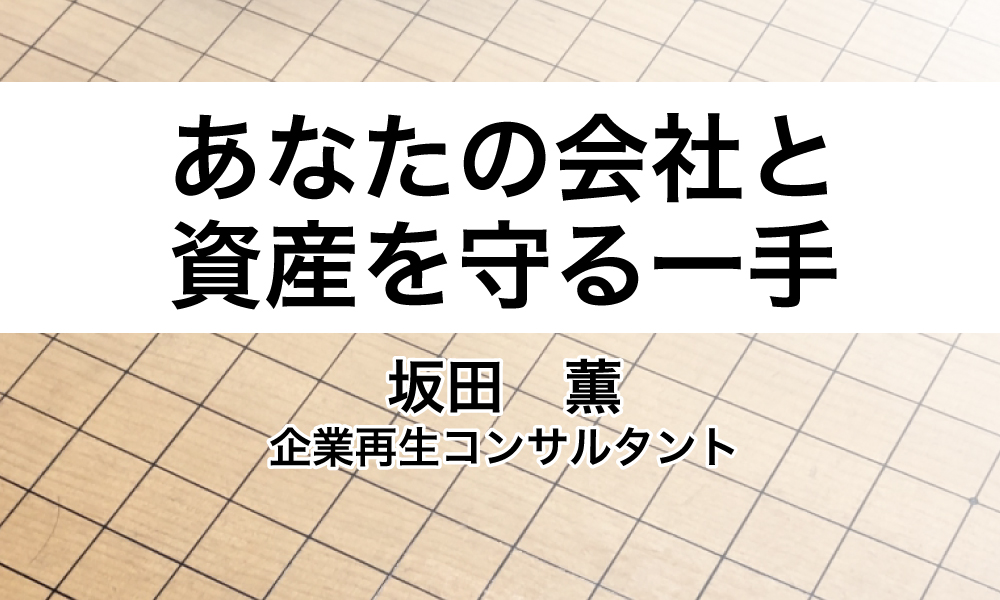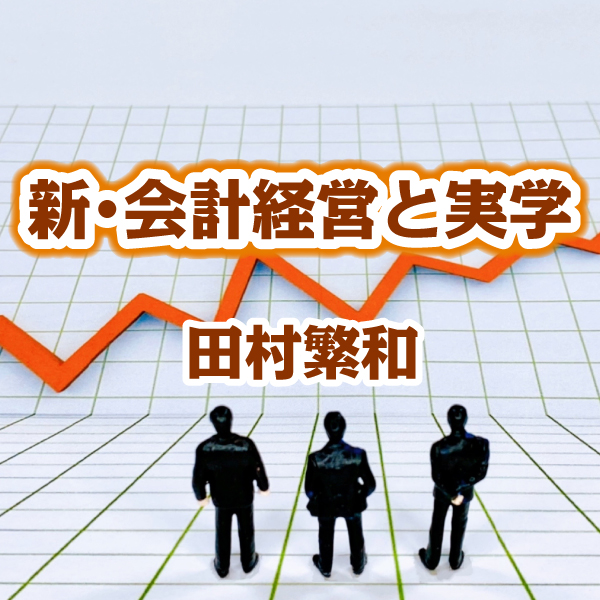十二月のことを一般的に「師走」と呼ぶ。年末の慌ただしさに師も走る、ことからそう言われるのは広く知られているが、他にも「極月」との呼び方もある。「ごくげつ」ないしは「ごくつき」と読む。
時代が変わっても年が改まるとの感覚にそう変わりはない。しかし、過ごし方はだいぶ違うようだ。カレンダーの関係で長期の休みが取れれば、日本を離れて海外で年を越す人も多い。
江戸の昔は、「年を越す」のは大きな仕事の一つだった。時刻が進めば自然に年は変わるものだが、それまでに片付けなくてはならない用事がたくさんある。
まずは、ツケで買ったものの支払いだ。江戸庶民は、馴染みの店からは現金でなくツケで買い物をすることができた。現在のように多額のボーナスが出るわけではないが、日々の支払いをまとめておき、盆暮れの二回に分けてまとめて支払うシステムだ。昨今、現金を使わずにカードはもちろん、スマートフォンを使って現金を持たずとも即時決済で買い物ができる時代だ。しかし、江戸期は現金を持っているわけではなく、夏のお盆から半年分の支払いを暮れのうちに済ませておかなくてはならなかったのだ。
米に始まり酒、薪炭、八百屋、魚屋、はては家賃に至るまで、必ずしもその場で支払うことはなかった。今で言う「売り掛け」のシステムだ。違っているのは、支配期限のサイトが決まっていないことで、年末に支払えないと翌年に持ち越す。決して良いことではないが、そうしないと暮らしが立たず、借金をされたまま夜逃げでもされるよりは増し、と考えたのだろう。自由のような長屋暮らしも、長屋を管理する「大家」(持ち主ではない)や町内の「五人組」と呼ばれる人々の管理の目は、さり気なく行き届いていた。
とは言え、売った代金を支払ってもらわなければ店は潰れてしまう。ある意味では、大晦日は売り掛けを取りに来る方も、払えないで延ばしてもらう方も、命がけとは言わないまでも、年末一番の大勝負である。
今でも時折高座に掛かる『掛取万歳』という噺がある。先に述べたように、いろいろな店が掛けを取りに来る。来られても払えない方は、相手の好きな物であしらって、その都度追い返すという噺だ。ただ、「好きな物」が義太夫、歌舞伎、狂言、三河萬歳、変わったところでは喧嘩など、江戸期に流行した芸能・娯楽で、これを口演する噺家にはそうした芸能の素養がないと演じることはできない。いずれも、そこまでして借金の言い訳を工夫した知恵に感心して、支払いの延期を承諾して帰るのだが、これはあくまでも落語の上の話だ。
実際には、少しでもツケの足しになれば、と九尺二間の棟割り長屋の乏しい家財道具で、いくらかでも金に換えられそうな物を持ってゆくところもあり、ひもじく、寒い思いをしながら新しい年を迎えた人も少なくはなかっただろう。
ただ、こうした落語や、真冬に裸足で川から採ったシジミを売って歩く少年を主人公にした「蜆売り」などの噺が残っていることを見ると、相互扶助が必要な時代であり、その分、情もあった時代だったのは間違いない。
***
仕事上、取れるものは取りたいが、一夜明ければ新年である。お互いに、嫌な気持ちで迎えたくはない。その上、毎日顔を合わせる近所のこと、暮らしぶりはわかっている。現代では、高価な外車に乗りながら生活保護を受給したり、誤魔化すために不正を尽くして、公的な補助金や助成金を受給しようとするケースが取り上げられたりする。それに比べれば、どっちがどうとは言えないだろう。
今も昔もお金はないよりもあった方が良いに決まっている。しかし、江戸の人々は貧乏が当たり前、という基準を持っていた。
「貧乏の棒がだんだん長くなり 振り回される年の暮れかな」
「貧乏をしても下谷の長者町 上野の鐘(金)の唸るのをきく」
などの狂歌が詠まれ、多くの人の口の端にのぼる。しかし、そこには江戸っ子の見得で押し隠しているのか、惨めらしさはない。貧乏に生まれ付いたのも天命と、日々を楽しく暮らせればよいのだ。
そうした生活に嫌気が差し、一所懸命に働き、少しずつでも借りを返してがんじがらめに縛られていた身も軽くなり、裏長屋から表通りに店を出す人もいた。それは、町内の同じ暮らしの人々からすれば大成功である。今まで「八っつぁん」だの「五兵衛さん」と呼んでいた八百屋のおじさんや魚屋のおじさんも、「旦那」や「親方」と呼ばれるようになる。「身を粉にして働く」という言葉があるが、まさにその結果である。
一年の中での最も大きな節目、歳末には多くの人々の悲喜こもごもが見られるのは、多少の違いはあれ、昔も今も同じことだ。しかし、同じ夜が一晩明けるだけで、年が変わり、気分が改まる。何日までもつかはともかくも、そこで「今年こそは!」と新たな誓いを立てる。歳末から新年への人々の心持ちは、時代が変わってもそう大きくは変わらないものなのだ。
さて、来年をどんな年にしようか。年末の慌ただしさの中、少しでも考えたいものだ。