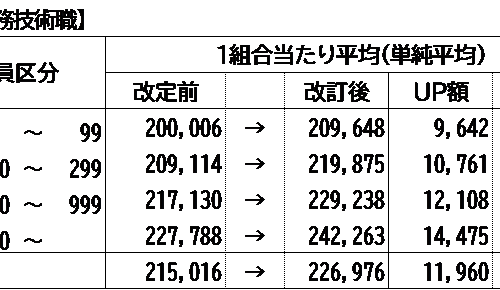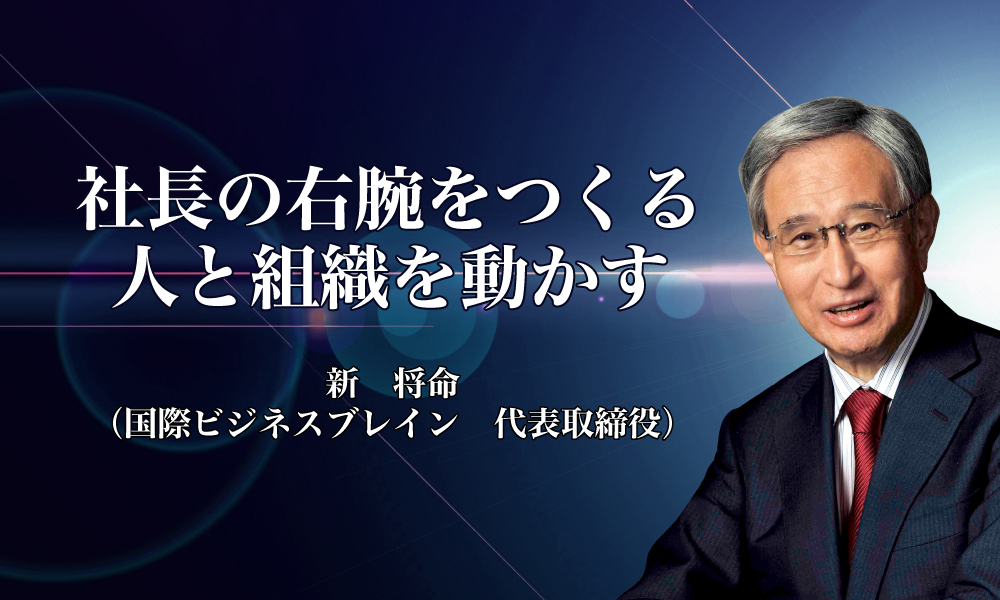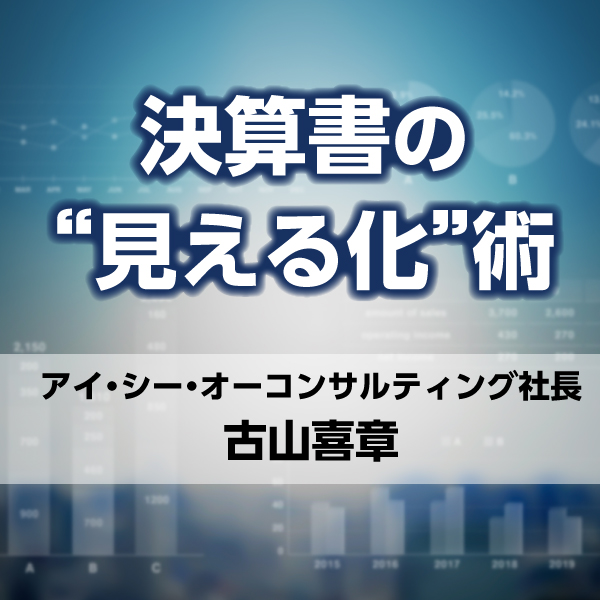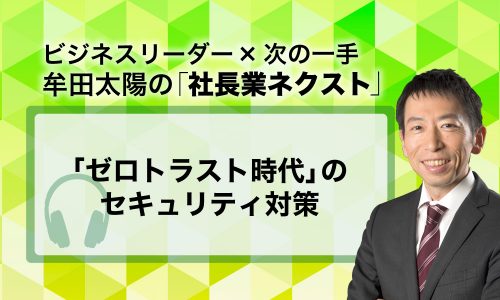今年の最低賃金引上げは、全国平均で63円増の1,118円となり、過去最大の上げ幅となりました。政府が掲げる「2020年代中に1,500円」の目標に対しては、現実的な修正が加えられた印象もありますが、それでも最低賃金の上昇は今後も続くと見られます。
このような状況下で注目すべきは、「最低賃金付近で働く人材の層」が拡大しているという事実です。最低賃金未満の従業員は法的に引き上げざるを得ないため、最低賃金の上昇はその水準で働く人の比率を高めることになります。
では、最低賃金付近で働いているのはどのような人たちでしょうか。学生アルバイトのような未経験者だけでなく、実は職務経験が豊富な人材も多く含まれています。
たとえば、年収の壁を意識して働くベテラン主婦パート。厚生年金の扶養範囲(130万円の壁など)を超えないよう、時給や労働時間を調整している人たちです。業務に精通し、勤続年数も長いにもかかわらず、制度的な制約により昇給が難しく、企業側も昇給を控えざるを得ない状況があります。
また、定年後に再雇用されたシニア社員も該当します。中小企業の製造業や建設業などでは、定年時の給与水準から大幅に引き下げられたことで、時給換算ベースで最低賃金に近づくケースが増えています。かつて自社で活躍した経験豊富な人材が、高卒初任給以下の待遇となれば、モチベーション低下の要因にもなりかねません。
東北や九州・沖縄など、最低賃金額が低めに設定されている地方では、もともと最低賃金が実質的な地域の世間相場となっているという事実があります。非正規の熟練労働者が最低賃金水準で働いている事例は、小売業や飲食業、宿泊業などに多く見られます。長年働いているにもかかわらず、正社員登用の機会が乏しいこともあり、賃金水準が地域の最低賃金に固定されているのです。
さらに、賃金体系が職務内容や時間単価に固定されている事業構造も影響しています。飲食チェーンや物流センター、介護職場など、非正規雇用者が中心となる職場では、学歴や職歴に関係なく最賃水準が適用される傾向が強く、昇給の余地も限られています。
こうした背景には、雇用の非正規化、定型作業の常態化、コスト抑制重視、年収の壁による雇用調整など、制度的・慣習的な要因が複雑に絡み合っています。結果として、能力や経験に見合わない待遇を受けている人材も少なくありません。
今日のように変化が大きい局面ほど、現実的な目先の対応だけでなく、中長期を見据えた人事戦略が必要です。これは、経営戦略や事業計画と一体でなければなりません。人材育成による生産性向上を目指すなら、制度設計だけでなく企業風土や慣習の見直しも必要です。つまり、最低賃金の引上げは、単なるコスト対策ではなく、人材活用のあり方自体を見直す契機と捉えていただきたいのです。
最低賃金付近の従業員が多い職場では、個々の従業員に対する生産性向上や収益への貢献度といった価値判断が、人事評価に反映されていないという問題もあります。人事評価を今後の戦略に繋げることができなければ、企業の持続的成長も望めません。そして、最低賃金近くで働く人は、必ずしも「経験の浅い低スキルの人」ではありません。組織の活性化の観点からも、雇用形態に関係なく仕事力のある人が正しく評価され、責任を伴う仕事を任せられる体制を目指したいものです。
最低賃金への対応は、正社員に限らず、シニア社員やパート社員など、あらゆる従業員の働き方と処遇の関係に配慮して行っていただきたいと思います。そうした取り組みが生産性向上、ひいては貴社の競争力を高めることに繋がるはずです。