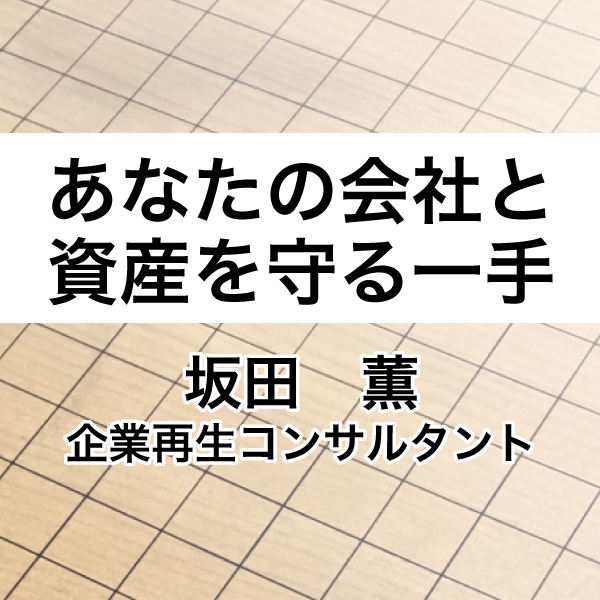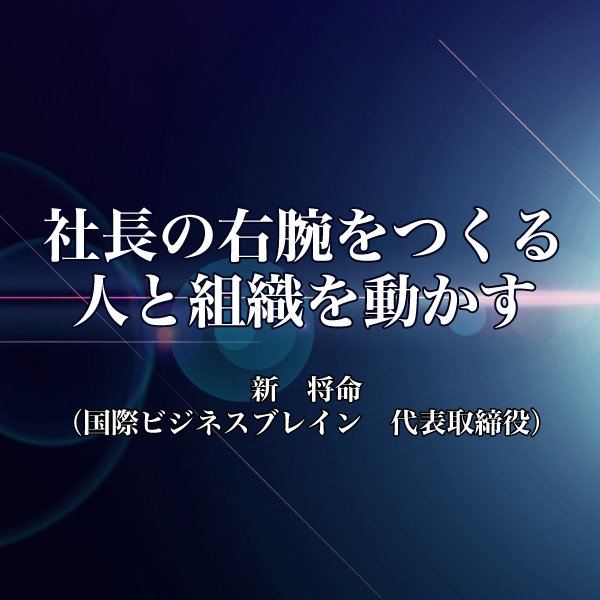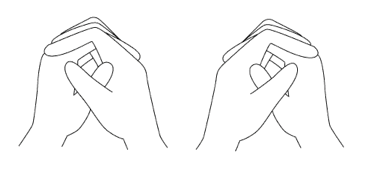敗戦と少数者の暴政
紀元前404年、ギリシャ世界を二分するペロポネソス戦争でスパルタに敗れたアテネには過酷な運命が待っていた。海外領土をすべて失い大量の戦死者を出して、国土は荒廃した。混乱の中、スパルタの軍政下で、民主政に批判的だった富裕層で構成される寡頭(かとう)派が権力を握る。権力はわずか30人の政治家に集中し、民主政で培った諸制度をことごとく廃止した。彼らは、民主政派を次々と拘束し即決裁判で処刑して、その財産を奪う。数か月で1,500人が犠牲となった。
あまりの暴政だが、戦争末期に、民主政下で戦争指揮が「衆愚」とも言える混乱を見せていたこともあって、哲学者のプラトンでさえ、30人政権による改革に一時は期待を寄せた。だが、暴政は長く続かなかった。秘密警察組織によって弾圧されて恐怖におびえる市民たちが立ち上がり、アテネを二分する内戦に発展する。暴政の首謀者たちが戦死すると、30人政権はあっけなく崩壊した。
憎しみを超えて再建を優先させる英断
混乱を見かねたスパルタ王のパウサニアスが両者の和解斡旋に乗り出し、半年後に民主政を回復させ事態を収拾する。政権を掌握したトラシュブロスら民主政派は英断を下す。市内には寡頭勢力への憎悪が渦巻いていたが、トラシュブロスは彼らに寛大な処置で臨んだ。暴政の首謀者を除いた残党たちに大赦を与え、公民権と財産権を保証した上で市街から退去させた。
民主政派は、荒廃した市の再建のためには、戦前の民主政最盛期に偉大な指導者ペリクレスが基礎を築いた、貧富の差、出身を問ない市民の大団結が不可欠だと判断したのだ。
憎しみによる報復は新たな憎しみを生み、また報復を呼ぶ。憎しみの連鎖は、破壊と混乱と分断を生むだけでしかない。最近のイスラエルとパレスチナの争いを見てもわかる通りだ。古代アテネ人は、この憎しみの連鎖を断ち切る知恵と決断力を持っていた。
また、戦勝国としてアテネに乗り込んだスパルタ“G H Q“も、「アテネの国のかたち」を最終的には尊重し、「スパルタの国のかたち」を強制することはしなかった。寡頭政派と民主政派の争いが自らの国制に波及するのを恐れたためと言えばそれまでだが、戦勝国の姿勢として学ぶべき点は大いにある。
民主制度の改革と法治の道
次にアテネが取り組んだのが、民主政の改革だ。アテネ民主制の基本は、全市を構成する自由人全員の参加による民会の制度にある。そこでは市民全員が、政策遂行について自由に発言し一人一票で投票する権利を持つ。多数の賛成で市政が動く。この点は優れた制度だ。しかし、ペリクレスの死後、たびたび民会が暴走し、混乱を招いてきた。
「市民の多数が決めれば何でも通る」が、政策をあらぬ方向に導く可能性がある。いわゆる「衆愚政治」だ。そこでアテネが打ち出したのが法治主義だ。民会の決議は、あくまでも法の範囲内でのみ有効であると定めた。このため従来の慣習法を含めて、市の運営、個人の民法的権利に関して、さまざまな法を成文法として定め整備した。これによって民会は法に反する決議ができなくなる。この原則は、現在も世界の民主国家に受け継がれている。
敗戦国のアテネは、法を民会の上位に置くことで安定した政治を手に入れることになった。政策方向づけを、ペリクレスという個人の判断に頼っていた民会の機能が、より普遍的となった。人治から法治への大転換だ。
アテネは、敗戦によってギリシャ世界に君臨する「帝国」ではなくなったが、この後、一ポリス国家として哲学、芸術、文芸において黄金期を迎えることになる。この民主政は、マケドニアのアレキサンダー大王が世界制覇に動くまで、百年にわたり安定して運営された。
(書き手)宇惠一郎 ueichi@nifty.com
(参考資料)
『民主主義の源流』橋場弦著 講談社学術文庫