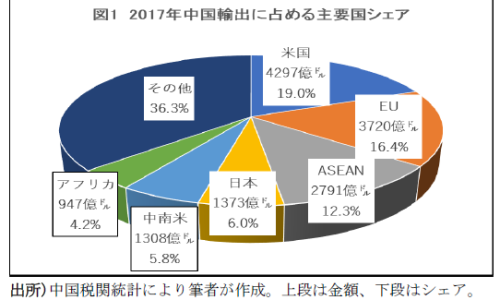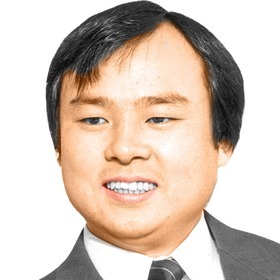しばらく前からの現象だが、最近の20代、30代には、録画したテレビ番組やインターネットの映像を「倍速」で観る習慣が根付いているようだ。「途中経過はいいから結果が知りたい」「観たい物がたくさんあり、普通の速度で観ていると消化できない」など、理由は様々だ。「効率重視」もここまで来たか、と嘆くばかりでは能がないが、感情論だけではなく実際にのちのちに影響を与える危険な側面もあるのではないだろうか。
「文化」というものは、そもそもが「隙間」や「余裕」などの無駄から生まれるものだ。あるいは、「マニア」が生み出すと言ってもよい。司馬遼太郎が看破したように、「文明はマジョリティのもの、文化はマイノリティのもの」との言葉は正鵠を射ている。何でもかんでも無駄を省き、スピードや効率に傾斜すればするほど、文化的な能力は落ちる。
「日本オリジナル」とまでは言わないが、「余韻」も立派な日本の文化だ。遠くの寺で撞いた鐘の音が、徐々に音が小さくなり、やがて聞こえなくなる。夕日が沈んだ後、闇が訪れる前の僅かな時間の薄明と言うべき明るさも「余韻」である。こうしたものを大切にできる感性こそ、日本人の繊細な感覚であり、美を生み出す源泉の一つだと私は思う。「余白」も同じことで、紙一杯に何かがぎっしりと書かれていれば、情報量は多いが読み難く、息苦しい。
今はまさに「息苦しい」時代だ。余韻や余白などを求め、そこに味わいがあるのだ、などとのんきな事は言っていられない。真実である一方で、哀しいことでもある。
作詞家の阿久悠は、かつて新聞のコラムでこう述べた。「いつの間にか必要以上の酸素を幸福と思うようになり、息苦しくなっているのが現代である」と。もう10年以上前の文章だが、阿久は今のありようを予見していたのだろうか。それとも、もう既にその予兆があったのか。
息苦しさは、もはや大人だけのものではなく、学校教育現場の荒廃ぶりを見れば被害は子供たちにも及んでいることは明白だ。仮に百歩譲って、「知るを足る」美徳を捨て、あくまでも「求め続ける」ことに価値を見出すのが全く無意味ではない、としよう。しかし、30年少し前の「バブル経済」崩壊後に経験した痛みや苦しみを想えば、それが有益なことではないことも言わずもがなだろう。
地位や年収に関係なく、誰もが「1日24時間」というのは、人間に与えられた数少ない平等だ。しかし、この「時間」(「時刻」ではない)の感覚が日本に根付いたのは、明治維新後のことで、僅か150年余に過ぎない。世界に合わせることは必要だが、そのために古来からの良き伝統を捨て去ることが良いかどうかは別の話であろう。
世の中の流れに逆らうつもりはないが、かつては「喫煙」の時間がまさに「一服」の無駄であり、余白であった。これは煙草に限ったことではなく、お茶を喫するのも一服なら、仕事帰りにどこかで少し気分転換をして、スィッチを切り替えるのも一服だ。それさえも無駄だとなれば、「24時間」という平等な時間の使い方に問題があるのだ、と言わざるを得ない。
今は昔話になってしまったが、かつては広い庭を持つ一戸建てに、それなりの庭があり、季節ごとに移ろいを見せる庭木が植えられた家がそこここにあった。そういう邸宅には何十年と庭の手入れに通っている職人がいたものだ。そんな時代、植木職人が一番仕事をしているのは、縁側で煙草を一服しながら庭を眺めている時だ、と聞いた。休憩しているようでも、職人の頭の中には、半年後、あるいは一年後の理想の庭木の枝ぶりが浮かんでおり、そこへ近付けるためには、今、どの木をどう手入れすれば良いかを考えている時間だ。「それでは休みではないではないか」との意見もあろうが、心身がリラックスした状態でのこの光景は、仕事と楽しみの間にあるようなものだ。このわずかな「間」が重要なのだ。現代は、その「間」を取り、空けることさえ許されない「息苦しい時代」になってしまった。いたずらに過去ののんきな時代を懐かしんでいるのではない。
私が言いたいのは、過去の遺物や単なる無駄ととられかねない行為にも、きちんとした意味や理由があるのだ、ということだ。
世の中がこれほどスピーディになった今、なお時間が足りずに僅かな娯楽の時間を削る前に、この文字をご覧いただきたい。「齷齪」。「あくせく」と読む。文字に責任はないが、画数も多く、字面も悪い。こんな生活を続けていれば、人間の魅力の一つである「余白」や「のりしろ」がどんどん狭まるのはやむを得ないことだ。実はこの「余白」こそ、その人の「伸びしろ」でもあるのだ。これを削ることに意味があるとは思えないどころか、その人にしか持ち得ぬ魅力、いわば「個性」でもある。
今、改めて、自分の一日、一週間、一か月、一年に、どんな「余白」があり、それをどう過ごしているのかを考えることは悪いことではないはずだ。