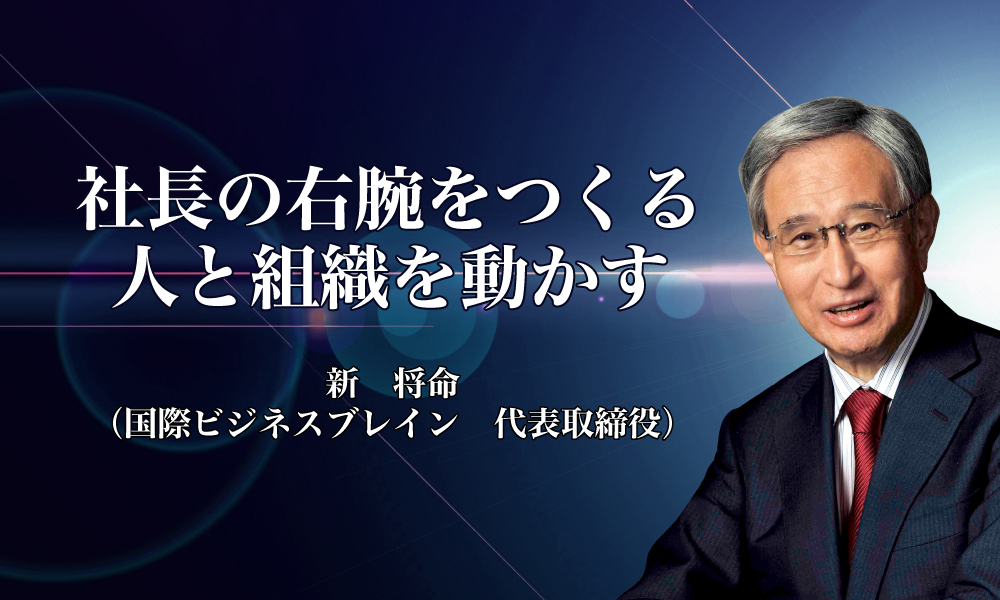昨年の記録破りの夏だけを取り上げるまでもなく、我々の生活から「季節感」が失われたことは、事々しく言うまでもない。地球の気候変動の影響で、四季の彩り豊かな日本の最もよい季節である「春」と「秋」が、年々短くなっているのは、誰しもが肌で感じていることだろう。
近代的な意味での「天気予報」が日本で始まったのは1884(明治17)年のことで、今から140年ほど前のことになる。それ以前の人々は、過去の経験に加えて朝晩の空気の温度や湿り気、周りの樹木の葉の散り具合や色合いなどで季節の僅かな移ろいを感じ、夕暮れの空を見上げ、明日の天気を予想していただろう。日照りや長雨は農作物に大きな影響を与え、一晩の嵐や時化は命に関わる。そうしたことども以外に、生活の中の季節感が薄れて久しい。
***
言うまでもなく、我々は五感を駆使して日々の生活を送っている。それらの感覚が捉える僅かな日々の差が季節感の現われになるのだが、言ってみればこれは生活における「オプション」であり、絶対に必要なのか、と問われれば答えに困るのも事実だ。真冬にTシャツと短パンで歩いているからと言って、キチンとしたドレスコードのある場所でもない限りは、人に迷惑が掛かるわけではなく、全くもって「大きなお世話」である。まして、ハラスメントにうるさい昨今、「人のファッションセンスに文句を言うのか」と逆ねじを喰らわされかねない。
せめてもの慰みに、と小さなベランダに風鈴を吊るせば、風の強い日にはうるさい、と苦情を言われ、庭木を楽しもうとすれば、隣家から枝が邪魔だとお叱りがくる時代でもある。もちろん、季節感や風情を楽しむにも、それ相応のマナーは必要で、何でもかんでも好きにやれるものではない。
外気の温度がどうであろうが、エアコンのおかげで室内を常に快適な温度に設定することもできる。何もかも、便利な世の中になったことに棹を差しても仕方がない。問題なのは、こうした生活の中で、我々が遥か昔から持っている鋭敏な感覚がどんどん鈍くなり、失われていることにある。誰しも、スイッチ一つで何でもできる快適な生活を好むだろう。しかし、何か便利な物を一つ手に入れれば何かを失うのも明らかなことだ。こればかりは、自分で感覚を研ぎ澄ます努力を続けていないと、世の中の動きのままに感覚は鈍くなるばかりだ。
***
珍しい苗字と言っていいだろうが「四月一日」という姓がある。「わたぬき」と読む。春になれば、それまで着ていた冬用の綿入れから綿を抜き、冬物から春物へと衣装が変わるから、この読み方になった。普段着に「着物」を着る風潮が激減している昨今、「袷」と「単衣」の違いもわからない人々が増えている。
流通や保存技術、養殖などの技術の発達で、夏野菜のトマトも茄子も年中スーパーの店先に並んでいる。さすがに秋刀魚や寒ブリなどの天然の魚類は、かろうじてその季節を感じさせてくれるものの、食べ物にも「旬」がなくなっているのも今に始まったことではない。食べ物の食べ頃を旬と言うが、本来の旬は十日から二週間である。ひと月を「上旬」「中旬」「下旬」、ないしは「上旬」「下旬」と分ければ、その期間の根拠は成程、と思える。便利な一方で、食べ物に旬がなくなった、とも言われているが、これは無い物ねだりだろう。
***
これらのことどもをただ批判したところで、時代遅れの小言にしかなるまい。問題は、まだかろうじて四季の美しさや季節の好さを保っている日本の季節感をどう味わうか、の工夫だ。一年の気候の変わり目をほぼ二週間おきに示した「二十四節季」は、すでに実際の気候と大きなズレを持つようになって久しい。「暦の上では立秋」と言いながらも、日中の最高気温が35℃という状況は珍しくも何ともなく、驚く話ではない。
先人が創り上げてきた感覚や習慣は、実状を考えて一度頭の隅に置くとして、今の我々がどこに季節感を求め、覚えるか、が心のありようを豊かにしてくれるのではないだろうか。暑い時期が長くなったので、仕事でも軽装の「クールビズ」の推進や、寒くなったのでダウンを羽織るなどの実利的なことばかりではちと寂しい気がする。その上での精神性の問題だ。
いろいろな分野の発達の恩恵を利用して、季節の花を家のどこかに飾り愛でるのか、旬の食材で食卓を彩るのか、あるいは日帰りで出かけられる範囲で足を延ばし、季節の移ろいを感じるのか、方法は人それぞれだが、ないわけではない。
***
私は風呂が好きだが、30を過ぎて所帯を持つまでは銭湯暮らしだった。風呂付きのある家に住みたくて所帯を持ったようなものだ。しかし、やはり数分歩いてでも、大きな湯船で短い手足を伸ばした方が温まる感覚は否定できない。大学生の頃、雨が降ろうと雪が降ろうと、アルバイトから帰って日付をまたぐギリギリの仕舞い湯に飛び込んで、一日の区切りを付けることは大事だった。
雪の降る晩に、サンダル履きの足を真っ赤にしながら銭湯へ行くと、不思議なことにいくら寒くても湯冷めはしない。その一方で、開店は午後3時だったので、朝や昼に風呂に入ることはできない。今は、好きな時間にいとも簡単に湯船に浸かることができる上に、お湯の温度調整もボタン一つだ。どちらが良かったのか、今となっては判断のしようがなく、それぞれに良いところを持っている。それでも、真夏に出先で銭湯を見付けると、ザブッと浸かり汗を流すと、さっぱりするだけではなく、日が高いうちに風呂へ入るという何とも言えない贅沢な気持ちになる。こうした暮らしの中に、季節感があったと言うべきなのか、単なる懐古なのか、この複雑な世の中ではもはや判断は不能である。
昭和初期の東京の歌舞伎界を牽引した名優・初代中村吉右衛門(先年歿した『鬼平犯科帳』で人気を博した吉右衛門の祖父に当たる)の句に、「雪の日に雪の科白を口ずさむ」というのがある。俳句を詠むまでもないが、確実に季節を感じ、時代に左右されないのは、日の出・日の入りの長さだろうか。冬の夜は、相変わらず長く、寂しい。