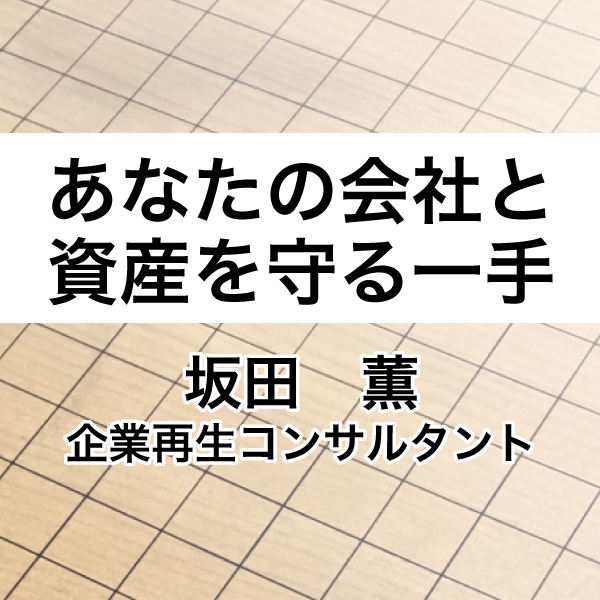いつ、誰が言い出したのか、「ピンチはチャンス!」なのだとか。字面をそのまま受け取る人もいないだろうが、如何なる窮地にも活路を見出せ(るはずだ)、との言葉の意味が、イメージだけ一人歩きしているような気がしてならない。
「ピンチ」の時は、本当にピンチなのだ。「月末の手形が落ちないかもしれない」という危機的状況を、「今がチャンスだ」と喜ぶ経営者はいるまい。もしもこれさえも「チャンス」と言うのなら、本当のピンチなど存在しないことになる。「ピンチ」をトップが危機感を社員に肌で感じさせ、一丸となって乗り越えよう、との士気が高まってこそ、初めて「チャンス」に変じる可能性が生まれる。ここでもまだ「可能性」であり、本当に「チャンス」とすることができるかどうかは、その先に待つ厳しさを、社員それぞれがどう実感し、対処するかだ。何とか「ピンチ」を乗り越えて、それを振り返った時に、「あそこで頑張れたことがピンチを切り抜ける唯一のチャンスだった」と考えることはできる。しかし、深く考えずに、言葉の前向きなイメージに踊らされるのは怖いものだ。
歴史に名を遺した人の金言の中にも、参考にすべき言葉は多々ある。その稚気を愛されながらも、平易な言葉で人間の真理に迫り、多くの人に愛されている江戸中期の僧侶で、俳人・書家でもあった良寛和尚(1758~1831)。
晩年になっても「あるがまま」を貫き、恋をしという、その人間くささが愛されている理由でもあろうか。子供たちと遊ぶ光景が多くの絵本などで見られるのは、「純真な子供の心こそ、一番み仏に近いものだ」という僧侶ならではの感覚だ。多くの至言・名言を遺しているが、友人の俳人に宛てた見舞状の中にある「災難に逢う時節には災難に逢うがよく候。死ぬる時節には死ぬがよく候。是はこれ災難をのがるる妙法にて候」との言葉が興味深い。
どう読み解くかは人それぞれで、その解釈の多様さが古典の魅力でもある。私は「どんな時でもありのままの状態を受け入れなさい」と考えたい。「災難に遭いたい」人はいないが、不幸にもそうなったら、悪あがきをせずに、その状態に身を任せなさい、ということ。「無駄な抵抗はよせ!と書けば物騒だが、今の我々の過信と我欲を戒めているようにも聞こえる。
良寛の時代からたかだか数百年を閲したからと言って、我々を取り巻く環境は飛躍的な発展・進歩を遂げたが、我々人間の持つ能力が同様の発達をしたわけではなく、大きな動きの中で生かされている状態に変わりはない。その一方で、目覚ましい医学の発達を前に、難病にかかった家族を前に、その道の専門家である医師が難しい顔をした時、「何とかなりませんか」と無理無体の要求をする自分がいる。そんな時の私は「我欲」の塊でしかなく、専門家として経験を積んできた医師に対する尊敬の念など見失っている。
自らが病を得た時に、チャンスだとは思う人はいない。しかし、そんな時こそ「一日も早く治して会社に顔を出さねば」ではなく、自らの身体が発する声なき声に耳を傾けることが大事だ。長年酷使してきた自分の肉体を労り、今までの無謀な生活を反省し、休息することこそ、実は回復への近道なのかもしれない。風邪を引くのは一瞬でも、治るまでには一週間や十日はグズグズするものだ。ここで、「どうしてもはずせない会議」があるからと、薬を何種類も服んで出社することが正しいとは言えるのかどうか。誰でも、突発の危機が訪れる。そんな時に、安心して事を託せる人を持てるかどうかも、人間の判断の一つになるのではないだろうか。
閑話休題。日本が誇る古典芸能の代表格「歌舞伎」。日本人の素養として、一度や二度や観ておかなくてはと思うものの、馴染まないうちは何を言っているのかもわからず、誰が誰やらもわからない。その上、何だか「交渉」なイメージがつきまとい、なかなか敷居が高い。しかし、「歌舞伎」は何度もの危機を乗り越えながら、400年を超える命脈を保ち今に至っている「庶民の芸能」であり、「高尚」なのはイメージの産物である。
歌舞伎の歴史の中で、幕府の弾圧により潰されかかったこともあれば、人気のほどはともかくも、身分としては庶民同様に扱ってもらえないほどの差別を受けてきた歴史もある。それでも、江戸時代には「反体制」としての側面を持ちながら、庶民と共にしたたかに生き抜いて来た。
そんな芸能でさえ、昭和に入ってからも、「歌舞伎は滅亡するのではないか」と話題になったことは一度や二度のことではない。しかし、その都度、歌舞伎はあの手この手で危機をやり過ごし、あるいは挑戦的に乗り越えて来た。
昭和の歌舞伎の名優がこんな言葉を遺している。
「歌舞伎が危ない、と皆さんに言われているうちはまだ大丈夫なんです。誰も何も言わなくなった時が一番危ないんです」。どの分野にも共通する、けだし名言である。