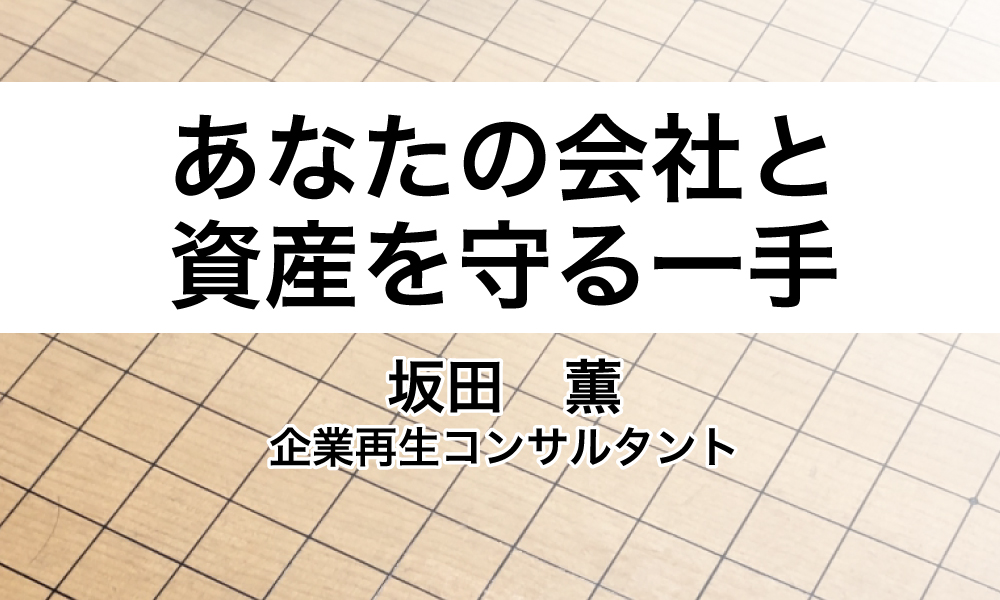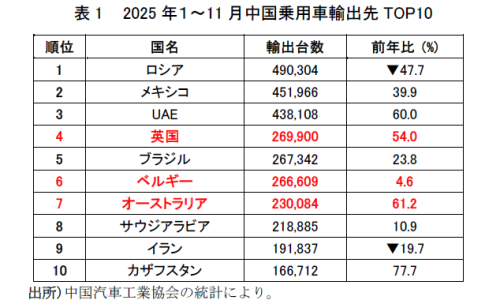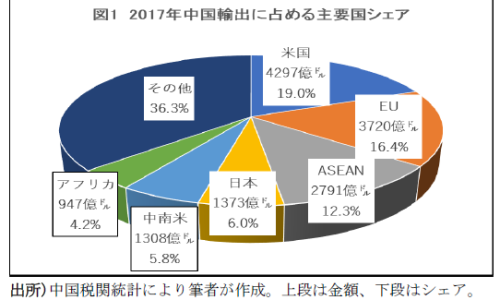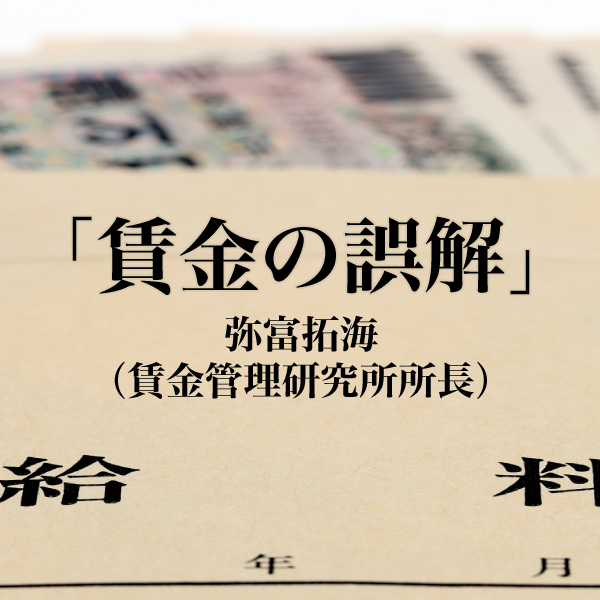多くの中小企業経営者にとって、決算を迎えるたびに頭を悩ませるテーマがあります。それは「銀行から評価される内容の良い決算書を作りたい」という思いと、「税金負担をできるだけ減らしたい」という思いとの二律背反の問題です。どちらも経営上の重要課題ですが、しばしば相反する方向に動くため、調整の妙が問われます。
銀行員の本音を先に述べれば、「税金を払っている企業であれば安心して融資できる」というのが実感です。なぜなら、税引後利益を計上し、法人税をきちんと納めているということは、帳簿上の利益が実際に残っている証拠だからです。いくら決算書上黒字であっても、税務上の調整で課税所得が小さければ、銀行は「実質的な利益は本当にあるのか」と疑います。
一方で、経営者にとって税負担の重さは切実です。売上が伸びても、利益がそのまま税金に消えてしまえば、手元資金が苦しくなります。だからこそ、節税を重視し、交際費を多めに計上する、あるいは役員報酬を引き上げるなどして利益を圧縮する傾向が強いのです。ただ、これらは税務上は正しい処理であっても、銀行から見れば「利益を削って自己資本を厚くする努力をしていない」と映る場合があります。
ここで重要なのは、「節税」と「脱税」「粉飾」の境界線を理解することです。税務上認められる費用計上は問題ないのですが、実態以上に経費を作り出したり、架空や回収不能な資産を資産として残すのは粉飾に近づきます。さらにいえば、銀行は節税よりも粉飾を強く嫌います。したがって経営者は「節税策を講じつつも、実態を歪めない」ことを大原則としなければならないのです。
そこで、実務上の調整のポイントを挙げてみようと思います。
① 役員報酬の設定
利益圧縮の常套手段ですが、銀行は役員報酬を「返済原資から出ていく資金」として見ています。極端に高額な報酬は内部留保を減らし、借入返済の余力を低下させるのです。銀行からの評価を意識するなら、報酬は妥当な範囲にとどめ、余剰を内部留保として残す方が有利です。
② 減価償却費の扱い
税務上は損金算入できるため節税効果があります。一方、銀行は減価償却費をキャッシュアウトしない費用と捉え、営業キャッシュフローの源泉としてプラス評価します。つまり、償却を正しく計上することは、節税と銀行評価の両立が可能な珍しい項目なのです。法人にとっては減価償却は任意(注1)なので、赤字の時は減価償却をせず、黒字になれば減価償却をするのが一般的な中小企業ですが、これらは決算書の別表16とその明細書で銀行側もすでに理解しています。したがって赤字・黒字で理論通りに減価償却しても、しなくても、その実質的効果は変わりません。
③ 交際費・会議費・福利厚生費
過大に計上すれば節税にはなりますが、過大な数字は利益水準を下げるため銀行評価は悪化します。では、適正とは何なのか? というと、決算年度ごとにそれらの科目の元帳を見比べたときに異常な数字が散見されるか? ということになります。銀行員が元帳の精査をすることは少ないですが、税務署は違います。これらの科目は、そういった視点から支出を考えるべき科目なのです。
④ 内部留保と納税
銀行が重視するのは「税引後利益が残っているか」です。節税のために利益をすべて費用化してしまうと、税金は減っても内部留保が積み上がらないことになります。結果として自己資本比率は改善せず、借入依存度が高まるわけです。貸借対照表の左上の金額の比率と、同時に右下の金額の比率が高ければ融資しやすい企業になるのです。銀行の評価を考えるなら、ある程度の税金は「信用を買うためのコスト」と割り切るしかないと思います。
⑤ 別表調整の説明
税務申告で加算・減算調整を行う場合、その内容を銀行に説明できる準備をしておくことが重要です。例えば交際費の損金不算入など、税務上はだめでも実態に即した数字を示せば、銀行は安心します。「税務上の利益」と「実態の利益」がどこで異なるのかを明確にすることが大切なわけです。
結局のところ、融資に強い決算と節税は、二者択一ではないものです。節税を意識しすぎて実態を悪く見せれば融資に不利となり、融資を意識しすぎて過大な納税をすれば手元資金が不足する。そのバランスをとるカギは、「利益をゼロにしない」「実態を歪めない」「説明できるようにする」という三原則にあると思います。
銀行員としての経験から言えば、銀行融資をうけようとするなら最も安心できるのは「適正な利益を計上し、その上で税金もきちんと払い、さらに残った利益を内部留保に回している企業」です。税務上の工夫は必要ですが、過度な節税は結局、銀行との信頼を損ねます。
(注1)
(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)
法人税法第三十一条
内国法人の各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費として第二十二条第三項(各事業年度の所得の金額の計算の通則)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額(以下この条において「損金経理額」という。)のうち、その取得をした日及びその種類の区分に応じ、償却費が毎年同一となる償却の方法、償却費が毎年一定の割合で逓減する償却の方法その他の政令で定める償却の方法の中からその内国法人が当該資産について選定した償却の方法(償却の方法を選定しなかつた場合には、償却の方法のうち政令で定める方法)に基づき政令で定めるところにより計算した金額(次項において「償却限度額」という。)に達するまでの金額とする。
この条文は
「損金の額に算入する金額は、・・・までとする」
という、損金算入の範囲を定める形式で書かれています。
では、なぜ「任意償却」と言われるのか?
その根拠は、「損金経理額」 という言葉にあります。
つまり、
損金経理(=帳簿に費用として処理)した金額だけが損金になる
もし「損金経理」をしなければ、その年度の償却はゼロ扱い
という構造になっています。
言い換えるなら、
法律上「できる」と明言しているわけではなくても、
法人が償却仕訳をすれば税務上認められる
償却仕訳をしなければ認められないが、それも自由
結果的に「やってもよい・やらなくてもよい」=任意償却
と解釈されています。