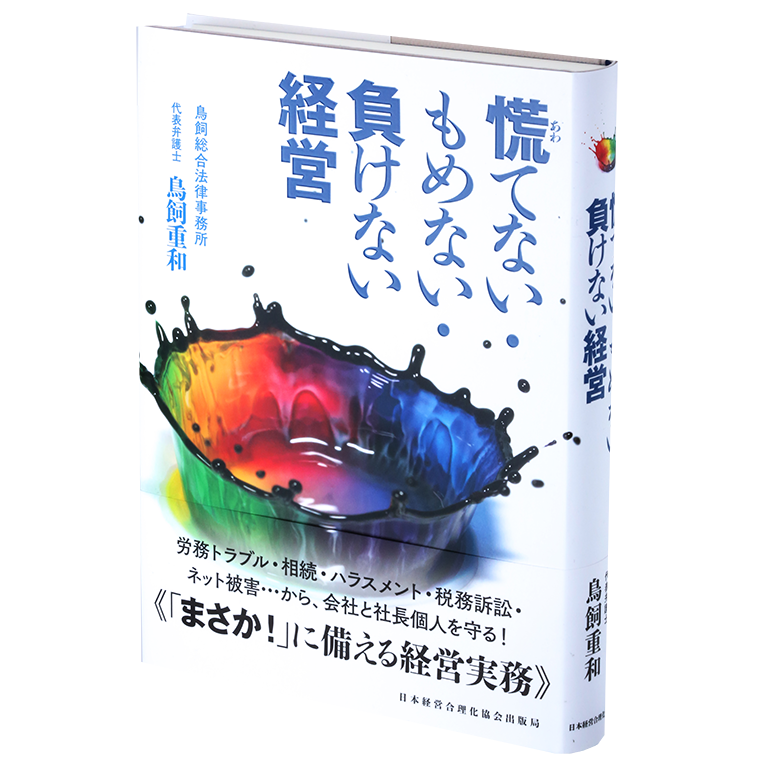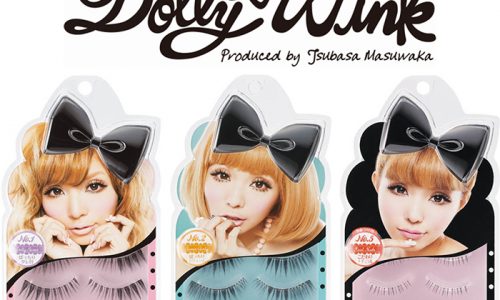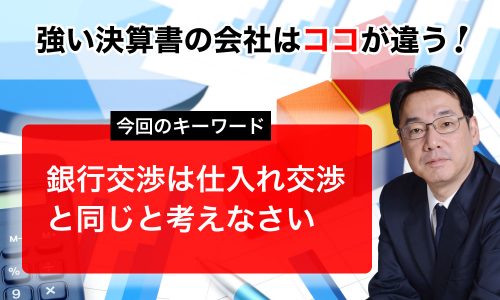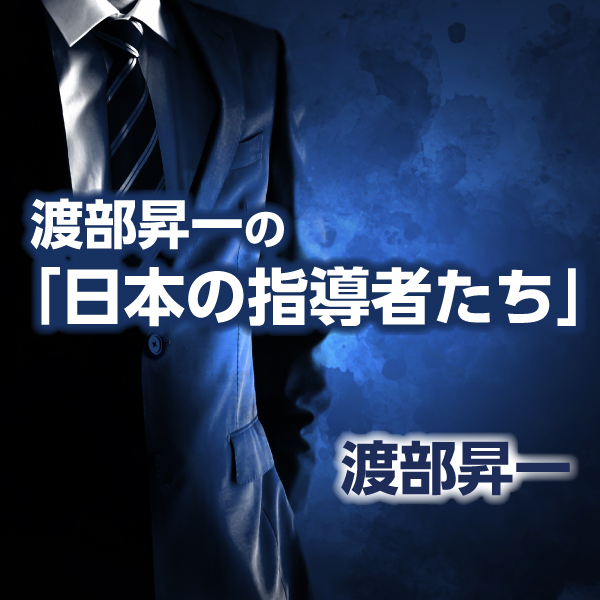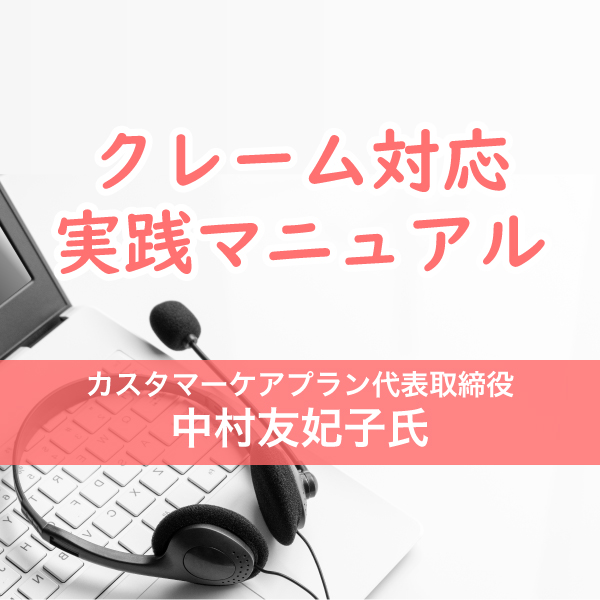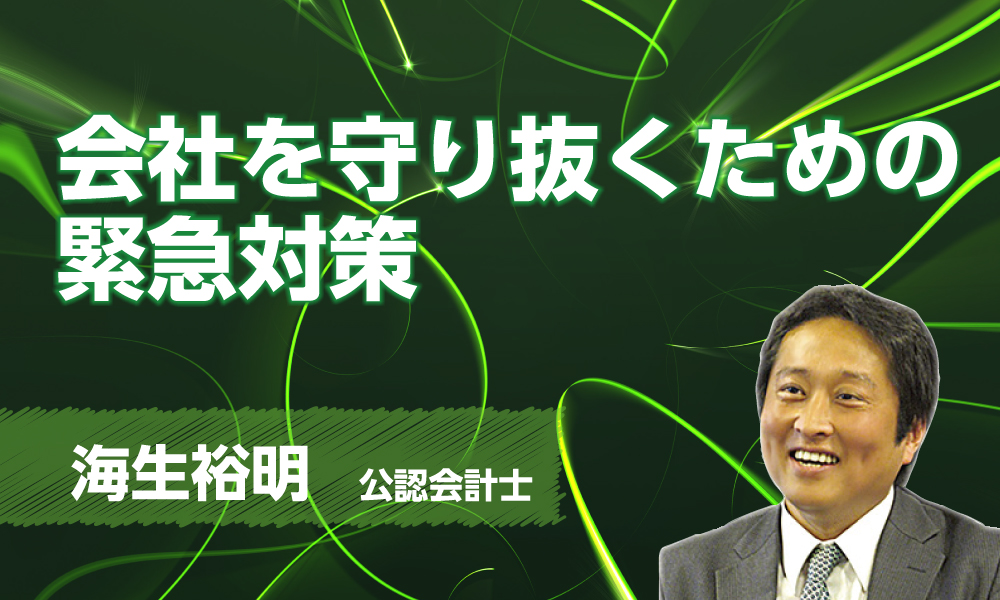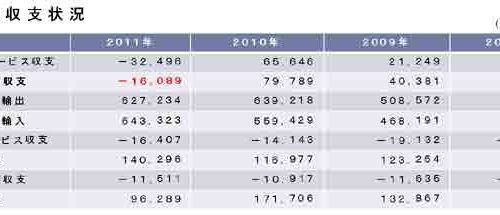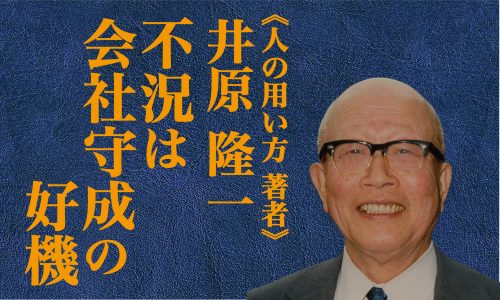中田社長: 先生! 今日は、うちの課長のパワハラについて相談させてください。この課長は、非常に責任感が強くて、仕事もできるのです。ところが、大声で部下を叱っていることが頻繁にあると耳に入りましたので、その課長を呼んで、「部下への言動には気をつけろ。相手のレベルに合わせて指導しろ」と厳しく注意しました。ところが、最近、この課長の部下が急に仕事を休み始めましたので、直接その部下に理由を聞いたところ、課長のパワハラのために仕事に行かれないと言うので、びっくりしました。私から注意したにもかかわらずそれを守ることができないのですから、課長から外してしまおうかと思いますが、いかがでしょうか。
賛多弁護士: 課長は、どうして部下を大声で叱ったのでしょうか。その理由を課長に確かめましたか。
中田社長: いや、大声を出したときの理由を詳しく聞いたわけではありません。でも、部下に対して大声を出すのはまずいでしょう。
賛多弁護士: それはそうですね。確かに、どんな状況でも、どんな相手であっても、穏やかに理道を正して話しをすることができれば、その方がよいことは確かですね。
それでは、ちょっと想像してみてください。例えば、社長自身が、ある仕事を部長に任せていたにもかかわらず、取引先からクレームが来て、部長が何も手をつけていなかったことが分かったとき、社長は部長に対してどういう対応をされますか。
中田社長: いや、それは、取引先に迷惑をかけてしまって、うちとの取引を切られるかもしれませんし、そんな無責任なことをする部長には、非常に腹が立ちます。厳しく叱責すると思います。
賛多弁護士: では、その部長には他にやらなければいけない仕事が山積していて、わかっていても手をつけられなかった、さらに、その仕事は、部長にとっても経験がないもので、社内でもわかる人がいないため、部長自身で取り組むしかないものだったことを説明されたら、いかがでしょうか。
中田社長: そうしたら、やむを得ないところもあるかな、と少し冷静になれるかもしれません。あ、いや、それでも、「言い訳は聞きたくない」と、余計に怒れてくるかもしれませんね。
賛多弁護士: そうでしょうね。事情や経緯が分かることで、違った光景が見えてくることがありますし、またそれに応じて、感情もさまざまに揺れ動きますね。
中田社長: わかりました。課長に部下を大声で叱った理由をよく聞いてみます。
【後日...】
中田社長: 先生! 課長としっかり話をしました。そうしましたら、まずは課長自身が、さばき切れないほどの仕事をかかえていて、余裕がなかったことがよく分かりました。私や部長から常々、「君には期待しているよ」と声掛けをしてきたこともあって、苦しい状況を上に相談しても解決しないと思い込んでいたそうです。
賛多弁護士: そうですか、話をされてよかったですね。
中田社長: ところで、課長が大声で叱った部下なんですが、課長がその仕事について何度も説明しているのに、理解していないようであり、違うことばかりすることが繰り返され、そのたびに課長がフォローしていたので、遂に、課長は、「何度言ったらわかるんだ。どうしてできないんだ」と叱ることが増え、段々、その声も大きくなってきてしまったのだそうです。これでもパワハラになるのでしょうか。
賛多弁護士: パワハラか否かは、業務としての必要性と相当性で判断すべきです。「相当性」というのは、法の世界では“比例原則”というもので、目的と手段が均衡していること、バランスがとれていることを要求するものです。とは言っても、厳密に必要最小限を求めようとしても、その状況への認識や対処の仕方にはそれぞれに幅があってしかるべきですから、ある程度、ゆるやかな許容範囲はあるでしょう。
本件は、今うかがったところでは、確かに、仕事上、厳しく注意・指導しなければならない状況であり、その目的のために著しく過剰であるとか、目的を達成しようとすることから大きく逸脱しているとまでは評価できず、パワハラと判断するべきではないと思います。
もっとも、その部下は、なぜ、何度も説明されて理解ができないのか、また、理解したとしてもそのとおりにできないのか、それは注意して観察する必要があるでしょう。人には、自分の認知のかたちやパターンに合わない他人の話は、何回繰り返し言われても、理解が難しいことがあるようです。「わかりました」と答えているかもしれませんが、理解を押し付けられていると感じると、苦しくなります。それでは、とてもできるような気がしないので、結局、自分流に解釈したことをやってしまうことにもなります。大きな声で言われるだけで、頭の中が真っ白になってしまい、余計に話の中身が分からなくなることもあります。部下がこのような困難を抱えていると、たとえ上司が業務として必要かつ相当な注意や指導をしているとしても、パワハラを受けていると感じているでしょうし、パワハラだと主張して何とかその状況から逃れるしかないことも起きうるのです。
中田社長: わたしたちが若いときは、上司から、自分には理解できない理不尽なことを言われても、仕事だからと我慢するしかありませんでしたが、しんどかったことは確かです。今はそれをパワハラだと言えるようになったわけですね。
賛多弁護士: そうですね、声をあげられるようになったこと自体は、悪いことではないと思います。
ただ、パワハラだと感じさせたのが悪いと上司を非難するだけでは、上司は非常に残念な気持ちになるでしょうし、部下の注意や指導を躊躇するようになってしまうでしょう。他方で、仕事ができない部下について、上司が自分の認知のかたちやパターンで認識したまま、やる気や責任感が欠けていると問い詰めることもまた、問題の解決にはならないでしょう。
中田社長: 両方のことをよく見て、それぞれから丁寧に話を聞いてみれば、わかってくることがあるのですね。改めて、課長と部下のそれぞれから話を聞いてみることにします。
* * *
このようなすれ違いは、どこの会社でも起きていることです。毎日のように相談をお受けしますし、最近は、経営者や管理職に対する研修として、このような話をさせていただくことも求められます。
「認知」とは、わたしたちが、ものごとを経験し、感覚を統合し、学習し、思考し、記憶し、想像し、判断する、情報処理のプロセスのことです。そのかたちやパターンは、人それぞれに違いがあることを知ることが、良好な人間関係を作っていくことの第一歩になるでしょう。
【参考】
執筆:鳥飼総合法律事務所 弁護士 小島健一