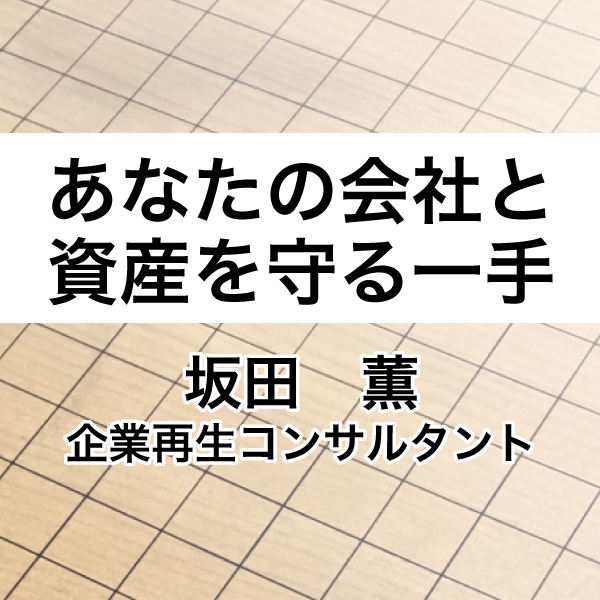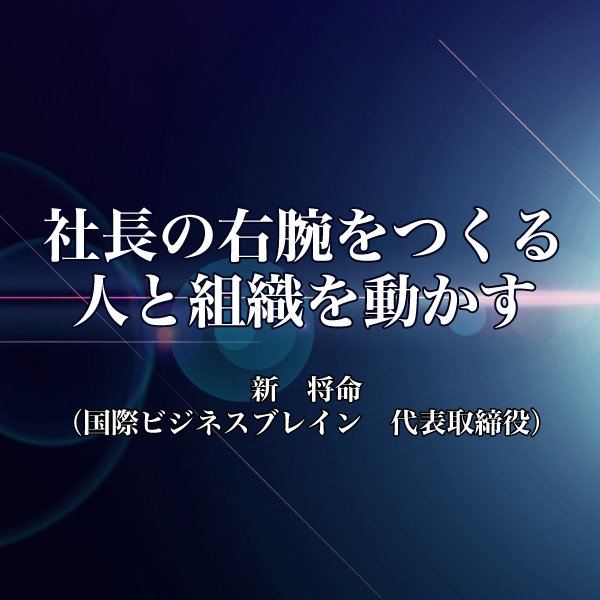ひと様に物を差し上げる折に「つまらない物ですが」「くだらない物で」などという。海外の人には、これが日本人の謙遜や美徳と映る一方、せっかく人にプレゼントを贈るのに「これはあなたに似合いそうだから」「確かこれが好きだったから」とプラス志向で渡さないのかも疑問だろう。
しかし、この言葉の根っ子にある事実を知れば、「なるほど」と思うと同時に、多くの事象の根源を知ることの重要性にも気付けるかもしれない。
今から150年以上前の江戸時代、都は京都であり、それ以前から経済・商業・文化の中心地は大坂(あえて江戸期の表記とする)だった。今でこそ電車はすべて東京駅や上野駅を目指して「上って」来るが、それまでは逆だったのである。上方へ上り、江戸へ下る。江戸へ行くことを「東(あづま)下り」と表現することからも、江戸期の江戸と大坂の格差の違いの大きさは歴然である。
現在では、どこの港で獲れようが、一番いい魚は東京の市場へ集まり、そこから各地へ配分されるケースが多い。これは流通の進歩の結果が大きく寄与しているが、かつても同様で、一流の品はまず大坂に集められ、そこから各地に「下って」行った。今でいう「お取り寄せ」で、江戸でも上方からの品を客に見せる場合は「これは上方からの下り物で…」と言えば、他の品とは違うのだ、との証明にもなったのだ。
江戸時代も中期になると、各地での農業の技術改革が進み、効率化と共に余暇の時間が増えた。それを活用して、各地の名産品を作り、少しでも収入を増やそうという動きが各地で起きた。「村おこし」や「町おこし」の発想とも言える。
この痕跡は、各地で江戸時代の国名や藩名が付いた特産物がずいぶん残っているのを見れば一目瞭然だ。石川県の「加賀友禅」、京都府の「丹後縮緬」、茨城県の「結城紬」、新潟県の「越後上布」などの着物をはじめ、島根県の「石州和紙」、広島県の「温州みかん」、島根県の「出雲そば」、香川県の「讃岐うどん」などなど…。
東京近辺に眼を移せば、千葉県は「醤油」の産地として有名だ。野田、銚子などには、大手の醤油メーカーがある。この「醤油」こそ、日本の料理を劇的に進歩させた調味料に他ならない。
閑話休題。こうして、いくつかの事例を挙げてきたように、わざわざ京・大坂から高い品物を取り寄せずとも、自分の村の近郷近在で、一流品ではなくともいろいろな品が手に入るようになった。これが「下らない物」であり、今の「地場産業」だ。何も相手に恥じる理由はない。それが二百年ほどの歳月の中で意味が変わると共に本来の意味が失われたのだ。
ここまでは、流れを理解していただければ「あぁ、そうだったのか」で終わる話だ。しかし、「下らない」「つまらない」がイコールで結ばれてしまうと、そこに誤解が生まれる。言葉の意味が似ているだけに、どちらでもいいのではないかと思われても困る。ここで、わずかな「言葉とがめ」をしようとしているのではない。
長い年月の間には、多くの言葉の意味や使われ方が変わることは言うまでもない。私は、「ことばとは変容する運命を持つ」との持論がある。今更例にするまでもないが、40代から50代以上の世代は「ヤバイ」という言葉を「まずい」「危ない」などの意味でスラングとして使っていた。しかし、今は「すごい」の意味で全く逆とは言わないまでも少なくも否定の意味ではなく使われている。こうした例は枚挙に暇がない。
あえてこうした例を引いたのは、組織のトップやリーダーが発する言葉にはそれ相応の重みがあるのみならず、場合によっては「見識」をも問われるケースがある、ということだ。さすがに社員や多くの人が集まる場で「ヤバイ」という方はいないだろうが、同じ意味を持つ言葉の言い回しでも、その語源や類義語を知っているだけで同じ内容の話が豊かな膨らみを持つ場合がある。言語学者になる必要もなければ、使い慣れない言葉を無理に使う必要もない。ただ、自分の語彙を増やすことは、それ相応の年代になればリーダーとしては必須とも言える作業なのだ。まさに「社長の教養」である。
手紙の頭語で、特に改まった内容ではなく、親しい相手なら「前略」で始め、「草々」と結ぶのが一般的だ。「匆々」や「早々」などの書き方もある。また、同様の意味で「冠省」「不一」という頭語・結語もある。最初は何だか馴染みがなく、不似合いな気がすることもあるが、何十回か使ってしまえば「前略」も「冠省」も同じ感覚の言葉になる。
こうした感覚を持つことも、リーダーの「見識」の一つではないか、と思うのだ。ことばに敏感なリーダーは、部下と対峙する時にも多くの方法を持っていることになる。叱り方、褒め方一つでも、どう言うかで相手に与える印象が大きく変わるのは周知の通りだ。
どうでもいいような事に思えるが、こうした小さな積み重ねなくして、大きな人物が生まれないと思うが、いかがだろうか。