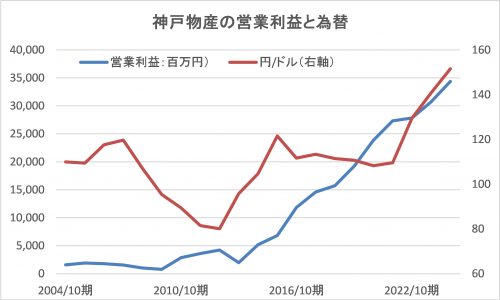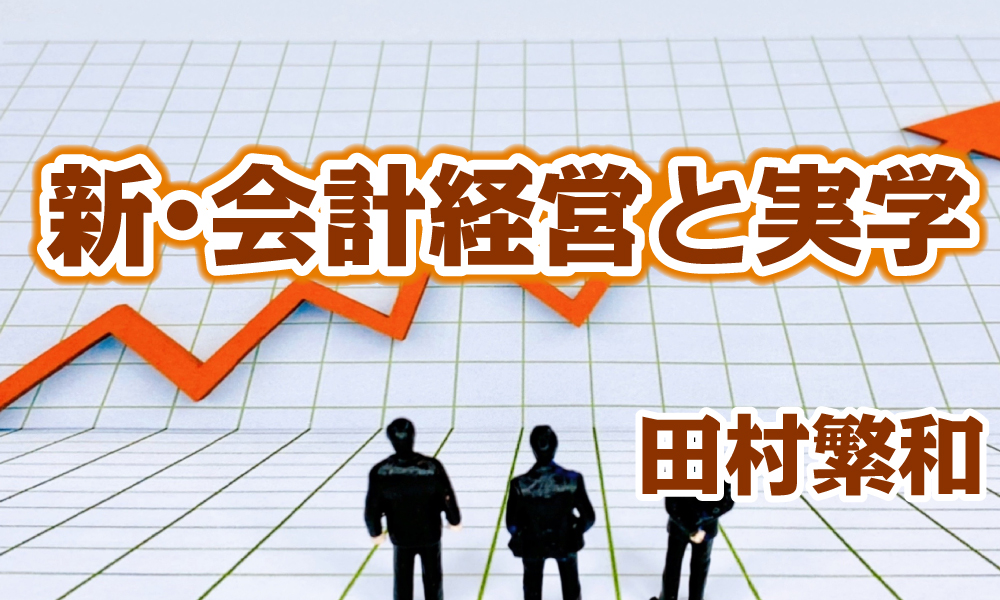- ホーム
- 指導者たる者かくあるべし
- 故事成語に学ぶ(32) 日暮れて道遠し
執念の男、伍子胥(ごししょ)
『史記』が描く傑物の列伝の中で、伍子胥(ごししょ)の物語はあまりに激烈で、物悲しい。思わず感情移入してしまう名篇である。
はじめは楚の平王に仕えた伍子胥は、あまりに優秀であったが故に父、兄とともに周囲の讒言に遭い、陰謀によって父兄は殺された。彼自身、国を捨て亡命、流浪の旅に出る。彼の人生は裏切った祖国・楚への復讐への執念で貫かれる。彼の生き様は、『春秋左伝』『韓非子』にも登場するが、『史記』に見える、優秀さと裏腹の激情が招く悲惨な最期は、まるで抗いがたい運命を描くギリシャ悲劇なのだ。
死者に鞭打つ激情
亡命先の宋、鄭(てい)でも国を追われた伍子胥は、楚と対抗する呉王・闔閭(こうりょ)にようやく拾われる。『孫子』を書いた孫武を武将として推薦し、二人は楚攻略の策を練る。楚王の代替わりの混乱に乗じて伍子胥は楚の都を落とす。伍子胥は恨み骨髄の平王の墓をあばき、遺体に三百回も鞭を打ち、積年の恨みを晴らした。
隣国に逃げおおせたかつての楚の友は、「お前もかつては平王のそばに仕えた身ではないか。一時の勢いに任せて勝ったつもりでも、天道が定まれば、いずれお前は仕返しを受けることになるぞ」と、人づてに残虐行為を諌めた。興奮を収めて伍子胥は言う。
「日暮れて道遠し。故に倒行(とうこう)してこれを逆施(げきし)するのみ」(私は年取って残された時間がないが、やるべきことはまだ多い。仕返しのために手段を選んでいる場合ではない)
復讐の激情を行動規範にしていては、いずれしっぺ返しを食らう。さらに年老いての焦りは、時として理性的判断を狂わせる。友の予言めいた忠告は、やがて伍子胥の身を襲うことになる。
身に降りかかる悲劇
時は過ぎ、呉は夫差(ふさ)が王となった。夫差は越との戦いで勝利したがとどめをささず、中原に攻めのぼるために北方の斉を討とうとした。伍子胥は、南方の越を徹底的に撃滅すべきだと強く意見した。結果的に夫差の北伐は成功し、伍子胥は死を賜る。
自ら首をはねる前に、鬼の形相で言い遺した。「墓の上には、やがて必要となる夫差王の棺桶用に梓の木を植えよ。城の門には、わが眼をくり抜いて掲げよ。やがて越軍がやって来て呉の国を滅ぼすのを見届けるために」。死ぬまで激情の人なのである。「あくまで俺は正しいのだ」と。夫差は怒り狂って、伍子胥の遺骸を馬の革にくるんで揚子江に投げ込ませた。
やがて越王は、国力を立て直して呉に攻め込み、呉は滅んだ。伍子胥の判断は正しかったのだ。優秀で正しい判断も、その言動が相手に恨まれる。慎むべきは慎むべきなのだ。
司馬遷は、この列伝の結語で言う。「怨恨が人に及ぼす害毒はなんと甚だしいものか」と。そして続ける。
「しかし、彼は(楚王から受けた一族の)大恥辱をそそいだ。烈々たる丈夫でなくて、これは成し遂げられなかっただろう」と、伍子胥の激情に同情的である。おそらく、自らが李陵事件で身に受けた宮刑の屈辱と、『史記』著述に後半生をかけた自らの復讐とも言える烈々たる思いとを、伍子胥の人生に重ね合わせていたのだろう。
(書き手)宇惠一郎 ueichi@nifty.com
※参考文献
『世界文学大系5B 史記★★』小竹文夫、小竹武夫治訳 筑摩書房
『史記を語る』宮崎市定著 岩波文庫