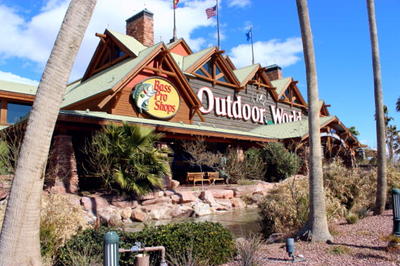自分が蹴散らかすように歩いて来た半生をふと振り返ると、いかに多くの先輩や師と呼べる人々の教えを受けて来たか、そしてそれをいまだに活かせていないかをしみじみと感じる。反省と自戒の念を込めて、「わが師」のことを何回かに分けて紹介をしたい。分野は違うが、一人の人間の生き方として、一流の人の歩んだ道が、他の道を懸命に歩む方々の助けになれば幸いである。
歌舞伎俳優・十三世片岡仁左衛門(1903~1994)。現在の十五代目片岡仁左衛門の父に当たり、2歳で初舞台を踏み、90歳で亡くなる3ヶ月前まで現役で舞台を踏んでおり、芸歴は88年に及ぶ。江戸期から続く名門・片岡家の御曹司として生まれながら、関西に拠点を移したため、昭和30年代に他の娯楽に観客を奪われ、衰微する「関西歌舞伎」で多くの辛酸を味わった。しかし、そこでめげることも折れることもなく、ただひたすらに「芸の精進」のみに心を砕き、晩年になって大輪の花を咲かせた名優である。
私が出会ったのは高校生の折、仁左衛門は75歳、その後、亡くなるまで教えを乞う日々が続いたが、77歳の昭和56年11月、生涯に何度かできれば幸福、という大役が回って来た。菅原道真の半生を描いた作品で、仁左衛門が主役の菅原道真を演じることになったのだ。しかし、その半年前、仁左衛門は緑内障でたった一夜で視力を失っていた。高度な技芸を要し、一幕で二時間かかる歌舞伎の大作を、盲目に近い状態で一ヶ月演じることは常識では考えられない。しかし、仁左衛門は「死んでもいいからこの舞台を演じる」と周囲の制止を振り払って舞台に立った。
初日の舞台。幕が開くと、眼が見えないなど一瞬で忘れさせるほどの演技で、「技芸神に入る」「神品の演技」と新聞や批評で絶賛を浴び、仁左衛門はこの芝居で「名優」となり、以後、80歳を過ぎても年間6カ月以上の舞台を勤めることが少なくなかった。
信仰に篤く、常に感謝の気持ちを忘れない仁左衛門が、不慮の失明という災難に遭い、不自由になったが、私はそれを悔やみ、嘆く言葉を聞いたことはなかった。それどころか「悪くなったのが眼でありがたかった。もしも耳が聞こえなくなっていたら、役者としてはどうにもならなかった」とさえ口にした。この強靭な精神力と、物事を良い方に考える力が、仁左衛門の内面を充実させ、舞台での演技に光彩を増した。
古今東西の知識に精通し、著書も多かった仁左衛門は、83歳の折に口述筆記で出した芸談で、こんなことを述べている。(以下、『芝居譚(しばいばなし)』河出書房新社より引用)
「二十歳代にはとにかく、よく見られたい一心、三十代には褒められたい一心、四十代になると、何とか自分の尊敬する大先輩のようになりたい、五十代には、いい役者と言われたい、と思ったものだ。それが六十になると、何とかいい芝居をお客様にお見せしなければ…、お客様に満足していただける芝居をしなければと考え、七十になるととにかく、役になりきらねば…、と苦心をするようになった。八十も半ばになったこのごろは、もう何も考えなくなった」。
視力を失って、余計な物が見えなくなり、ただ「演じる」ことだけに神経が集中できるようになったのだ、と語っている。「歌舞伎」「俳優」という一つの分野に特化した生き方の中での考え方だが、年代による考え方の進化・熟成が非常によくわかる。80代の仁左衛門は、まさに「無我の境地」とも言える精神状態の中で演じていた。だからこそ、年を重ねるごとに評価が高くなったのだ。
篤実な人柄で、芝居の稽古以外で声を荒げた場面を知らないが、たった一度、たしなめられたことがある。文化・芸術に関わる人々に与えられる栄誉の中での「芸術院会員」に選ばれた折、私は自分の事のように嬉しく、お祝いの言葉に「次は『文化功労者』ですね」と付け加えた。仁左衛門は、
「中村君、そういうことを言うもんやない。今、私は、眼は不自由でも、他にどこも悪いところはなく、三度の食事より好きな芝居を元気で勤められます。それを、お客様が褒めてくださることがある。こんな幸せな日々の中で、感謝こそあれ賞がほしいなどと言ったら罰が当たる」と。
俗な常識にまみれていた私は返す言葉もなく、ただ恥じ入るばかりだった。結果を先に望むのではなく、日々懸命に自分の道を精進しながら歩けと言われた気がしたのだ。もう40年も前のことになるが、仁左衛門の言葉を真似れば「何とか、読者の皆さんに満足していただける原稿を書かねば」という年齢に達して、その重要さを知り、満足できずに歯噛みをしている。
1993年12月、京都・南座での舞台で体調を崩し、千秋楽まで数日を残して休演、療養に入った。しかし、年齢もあり、病が篤くなり、もう面会は叶わぬと知りながらも、玄関先にスープだけでも置ければと、翌94年3月26日の朝、私は新幹線で京都へ向かった。静岡を過ぎた辺りで、車内の電光掲示のニュースが、仁左衛門の訃報を告げた。亡くなって数時間で京都の自宅へ泣きながら飛び込んだ私を見て、「お父ちゃん、呼ばはったんやね」と家族が言った。号泣し、物を言わぬ仁左衛門に縋り付きながら、私は「良い原稿を書く」と誓った。亡くなって30年近くなる今、まだ約束は果たせていない。