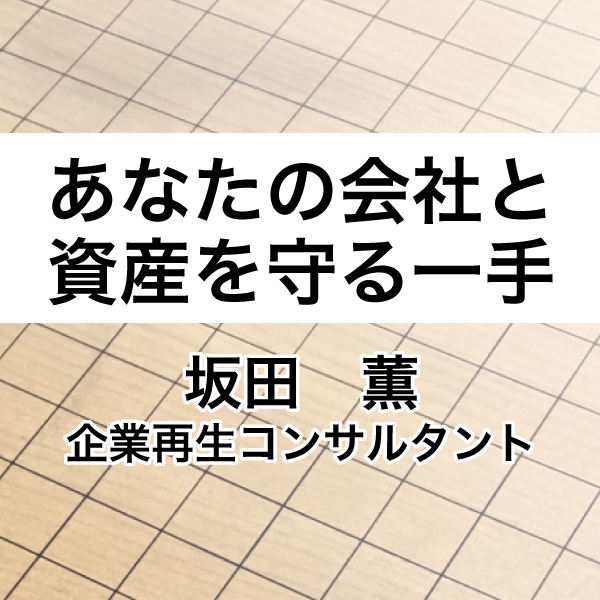政府による米の全量統制と配給
子どものころ、米を買いにお使いに出されるときには、母親が茶箪笥から米穀通帳を出してきて渡された。米屋の主人は通帳に記載された世帯名と販売数量を台帳に書き写して米を売ってくれた。昭和30年代のことだ。
当時、町の貸本屋で漫画本を借りるときには、米穀通帳が身分証明書がわりになった。この通帳が、戦時中に公布された「食糧管理法」(食管法)による配給制度の名ごりであることを知ったのは大人になってからだったが、通帳の記憶は鮮明にある。
前回書いた大正の米騒動を受けて、原敬内閣が出した「米穀法」では、米価の安定が主眼であった。豊作で米が余った年には政府が余った米を農家から買い入れて備蓄し、凶作や災害で米が不足した年には政府の持つ米を放出する緩やかな調整策だった。
満州事変や日中戦争の勃発で情勢が緊迫するにつれて、政府の米流通への介入は、調整から統制へと戦時色を強めていく。1933年(昭和8年)には、「米穀統制法」で、米取引の公定価格が定められ。1939年(昭和14年)には前年の国家総動員法に合わせて「米穀配給統制法」で、米穀商を許可制とし、米の先物取引を禁止する。太平洋戦争開戦の2か月後、食管法によって国の米流通統制は完成する。
戦後に引き継がれた食管法
終戦後、わが国は、米の海外生産拠点でもあった台湾、朝鮮という植民地を失い、慢性的な米不足に陥った。その意味では主食の統制と配給制度は、戦後も必要とされた。現在とは違い、インドやタイからの輸入米は国産米よりも高く、政府は輸入に助成金を出してまで米の確保に迫られた時代が続いた。
米の増産が進むにつれて、配給制度は1960年代には形式的にも終わりを迎えたが、政府が主食の供給量の調整に間接的に関与するという発想は、食管法が1995年(平成7年)11月に廃止された後も根強い。
米の価格は、市場の自律性に任せるだけで安定するのか、という疑問は、江戸時代から続く古くて新しい問題だ。政府はどう関与すればいいのか。
背景には、米という農作物の特殊性にあるという指摘もある。
米という商品の特殊性
農産物はそもそも、工業製品と違い、自然の天候が相手だから、豊作と不作を繰り返し、価格が変動しやすい。一般の野菜では、旬が限られて長期保存ができないから、不作なら値が上がり、取れすぎると下落する。この夏の猛暑で夏野菜が採れず、高値が続いている。そうかと思うと、キャベツや白菜が取れすぎて値崩れし畑で腐っているというニュースはよく目にする。
米とて、収穫期は夏から秋に限られており、収穫量は気象に左右されやすい。だが、他の商品作物とは違い、玄米での保存が利く。冷蔵保存技術が進歩した現代ではなおさらだ。さらに日々口にする主食だから、消費者としては、値が高いからといって買わないわけにはいかない。安いからといって大量に買って大量に食べるわけにはいかない。食べる量には限りがある。そういう消費特性からいって、米は、流通量が減れば値が極端に上がりやすい。投機筋が介入すると値動きの幅はさらに増幅される。それが、今回の事態だ。
国民総飢餓状態からスタートした日本の戦後の米農政は、「米の全量国内自給」を悲願とし、増産路線をひた走る。その結果、1967年(昭和42年)に全量自給達成を実現した。
皮肉なことに、そのころから米の消費量は落ち込み始める。米が余り始めた。それが、戦後の米農政の分岐点となった。
(書き手)宇惠一郎 ueichi@nifty.com
※参考資料
『日本のコメ問題』小川真如著 中公新書