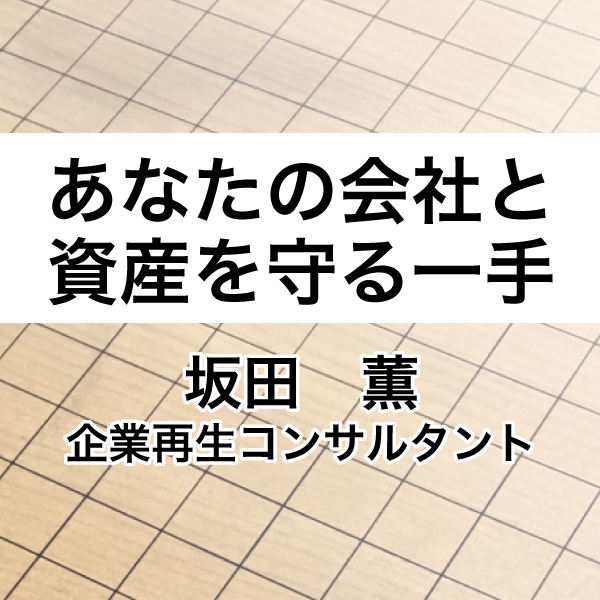政府による米流通への介入
米価格高騰による「米騒動」(1919年)によって瓦解した寺内正毅(てらうち・まさたけ)政権の後を受けた原敬(はら・たかし)内閣にとって、米価の安定は急務だった。
明治維新後も、江戸時代と同じく米価格は、自由流通による需要と供給の原則に任されていた。明治政府は、1886年(明治19年)、東京深川に東京米穀商品取引所を開設し、膨張する首都の現物米流通の円滑化を図ったが、政府が直接に主食流通に介入することはなかった。
しかし、工業化の進展で、都市生活者が急増し、非農業人口を食わせるだけの需要と供給のバランスは不安定になる。さらに第一次大戦の特需による好景気が去ると、1920年には戦後恐慌(きょうこう)と呼ばれる不景気に陥り、工場、企業の合理化による帰農者が増えて、米の相場は下落の一途をたどる。ここに原内閣は、景気動向に左右されない米価の安定を目指して、米流通への政府の介入を打ち出した。
1921年(大正10年)に公布、施行された「米穀法」だ。形を変えて戦後まで続いた食糧管理制度のひな形だった。
米穀法の制定と農業政策
新しく制定された米穀法では、収穫された米の買い入れと売り渡し、交換、加工、貯蔵は政府が行うことになった。また、米の輸出入も政府の管理下に置かれた。原内閣は、前年には、開墾助成法も制定して米の増産にも動き出している。
しかし、主食米の価格は単純に需要と供給のバランスだけで決まるものではない。米の価格の上昇を望むものと、下落を期待する二つのベクトルの調整が必要となる。これまで見てきたように江戸時代であれば、米価格で俸禄が保証される武士階層は高値安定を望み、都市に暮らす庶民は、安い米を期待する。その狭間で、バランスが折り合う“適正な”価格で商人が米を売りさばく。
昨年秋以来、高止まりしている異様な米の値動きを見るがいい。一昨年比で2倍の値をつけるほど、米の流通量が落ち込んでいるわけではない。スーパーを見渡しても流通量は確保されている。米がなくて飢え死にする状態ではない。どこかに大量の米が隠匿されているわけでもない。にもかかわらず、米の値段は下がらない。
「これまでの価格では、農業資材代も出ない」と考えている生産者の値上げ圧力が、「米を安く出せ」という消費者の声を圧倒している。どのあたりが適正な価格かという米価設定目標を生産者と消費者の間で調整できていない政府の無策が事態を長引かせている。この問題で政府が処方箋を示せないままでは、米蔵を開いて多少の備蓄米を値下げの呼び水として出すという小手先の対処法では、解決の見通しはない。
大正の米騒動後も同じだ。米穀法の制定だけでは、米価は安定しなかった。
米価は社会矛盾の反映
大正時代の農政の困難は、農村の疲弊に起因していた。明治維新で領主への年貢から解放された農民は、現金での納税を義務付けられた。凶作年があると売る米がなくなり、肥料、農具代を豪農から借りた。借金が返せなくなると豪農は土地を取り上げる。土地を手放した農民は小作料を豪農に支払い農事を請負う小作農家に転落する。年々自作農家は減少し、1917年(大正6年)には、小作農家率は、51,7%と半数を超えている。農民は、景気が良くなると工場労働者として都会へ出て、不景気になると農村に戻る不安定な立場となる。
小作には納税義務がないが、小作料を要求される。事実上の納税者と同じだが、当時の選挙法では、有権者は、一定以上の納税者に限られたから、広範な土地を所有する自作農家だけが参政権を持つ。政党政治が軌道に乗りつつあったが、代議士支援者の豪農の意思だけが農政に反映されて、農村は疲弊していく。農政、米価は社会矛盾を反映する。
現在、社会の形は変わったが、疲弊した農村のままでは、米価の安定は望めない。
農村、農業の立て直しこそ急務なのだ。
(書き手)宇惠一郎 ueichi@nifty.com
※参考資料
『日本の歴史 23 大正デモクラシー』今井清著 中公文庫