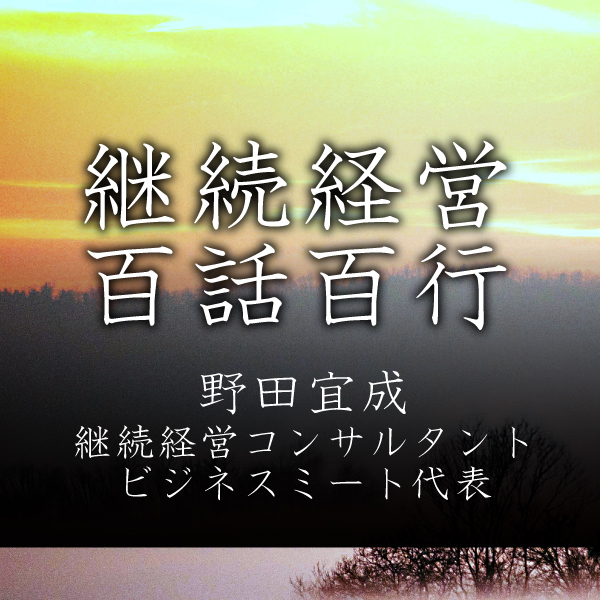生産者と消費者の綱引き
物の価格は、生産量(供給)と消費者の必要量(需要)とのバランスで決まることは言わずもがなである。しかし、米の価格はそう単純に決められないことはこれまで見てきた通りだ。生産者にしてみれば、生産経費も考えて、できるだけ高く売りたい。都市で暮らす非生産者としての消費者は、1円でも安く安定して手に入れたい。公定価格の設定をめぐる両者の綱引きだ。
農民にしてみれば、戦前から続いてきた配給を前提にした食糧管理法(食管法)のもとで、米は不当に安く提供させられてきたという不満がある。戦後、食糧不足の中で政府が考えたのが、生産された米の全量を適正な公定価格で買い上げ、適正な公定価格で卸売に売り渡す制度の導入だった。では「適正な公定価格」をどう決めればいいのだろうか。
政府は1949年(昭和24年)に、政府の諮問機関としての米価審議会を立ち上げる。毎年、収穫期を前に生産者と消費者の代表に中間委員(学識経験者、国会議員)を交えて合理的な米価を審議させ答申を得て、決定することにした。
しかし審議会は、当初から意見が対立して、難航を重ねた。
農協の台頭と与党とのもたれ合い
のちに中間委員から国会議員は排除されたが、答申が出ても、それはあくまで基本方針であって、政府買い上げ価格と、消費者に影響のある政府売渡価格は、政治の介入で決定されていく。票田である農村票に依存する政治(政府与党)は、農民寄りで米価の引き上げに同情的だった。農林族が暗躍する。
戦後復興下の食糧不足の解消のため政府は、農家に増産の努力を期待し、農家はそれに応えて反収(たんしゅう)増加に協力する。復興から高度経済成長に至る過程で、消費者側は、労働組合を圧力団体として生活向上のため賃上げ獲得に奔走する。賃上げが進めば、諸物価は上昇する。生産にかかる経費(農薬、肥料、資材代)も上がり、農民は、それに見合うだけの米価引き上げを要求する。労働組合を持たない農民たちの圧力の拠点となったのが、経済団体として発足した農業協同組合だった。
敗戦直後は、収入面で都市居住者に対して劣っていた農村部の年収との調整は、政府の政策課題の一つであったから、米価は労働者の賃金を上回る勢いで上がっていく。例えば、昭和39年の生産者米価は、前年に比べて11.3%、翌年は9.15%引き上げられている。
農民は、与党自民党の農林族議員を頼り、農村部に基盤を持つ与党議員たちはその要求に応える代わりに、来たるべき選挙での投票を期待する。持ちつ持たれつ、もたれ合いの米価決定が日常化する。
米価闘争の裏で進む米離れ
1970年代から80年代、筆者が米どころの青森、新潟で記者として取材活動をしていたころ、毎年夏の米価決定シーズンを迎えると、全国の農民たちの代表は大挙して上京した。ムシロ旗を押し立てて、自民党本部、国会周辺を取りまき、「米価を上げろ」のシュプレヒコールとともに、大デモを繰り広げ圧力をかけるのが、恒例行事となった。
上京を前に、農民たちは各地で米価要求大会を開き、地元選出の国会議員たちに圧力をかける。
1980年代のある年の夏。新潟県下越地方のある体育館に農民たちが集結して開かれた米価要求大会。「決死」の鉢巻と、「大幅米価引き上げ」のタスキをかけた農民代表が、壇上の地元選出与野党議員たちに米価引き上げ要求書を読み上げて手渡した。
法務大臣まで務めた古参の大物国会議員は、「諸君の要求はよくわかった」と応え、会場は大きな拍手に包まれる。そして、気骨のあるこの議員は聴衆を制して続けた。
「言いたいことはよくわかった。しかし、わしにも言いたいことがある。よく聴け。米価に生活がかかっているというなら、お前たちの毎日の食卓はどうなんだ。朝はパンを食べて、晩酌にはビールとウイスキーだ。米価を上げて欲しかったら、率先して米を食え。もっと日本酒を飲まんか!」
固唾を飲んで聴き入っていた農民たちからは、一瞬沈黙の後、大爆笑が起きた。
しかし、笑い事ではなかった。このころ米の消費量は急激に落ち込み、「減反」という生産調整が農林族の間でも真剣に話題に上っていた。米の全量買い上げ、公定価格制度も破綻に瀕しつつあった。
(書き手)宇惠一郎 ueichi@nifty.com
※参考資料
『日本のコメ問題』小川真如著 中公新書
『日本の歴史26 よみがえる日本』蠟山政道著 中公文庫