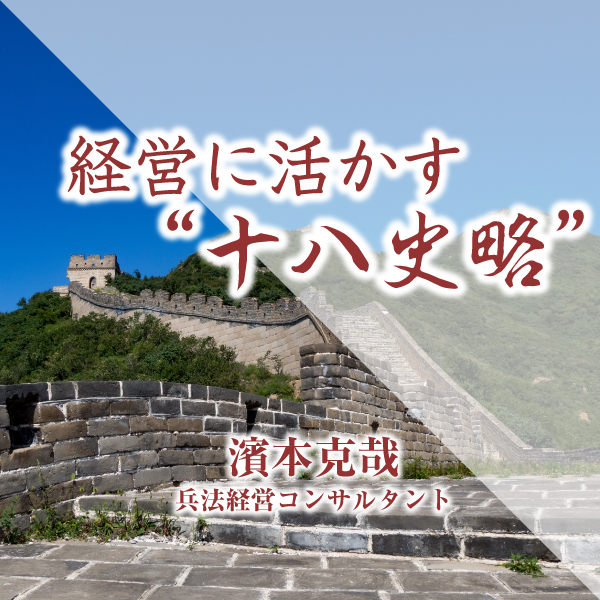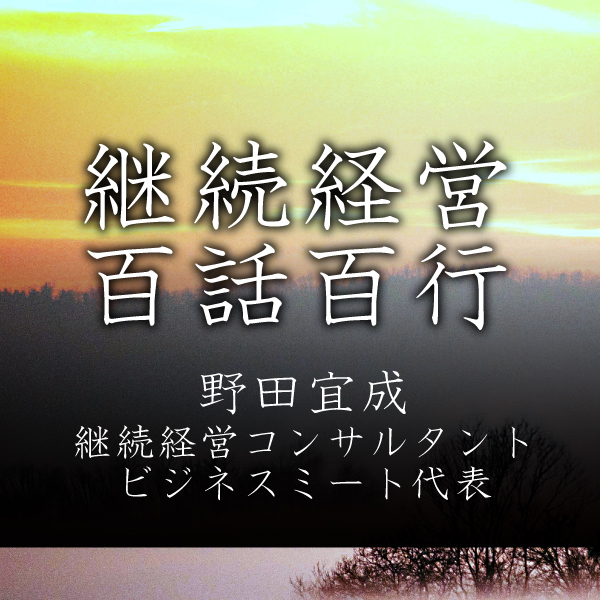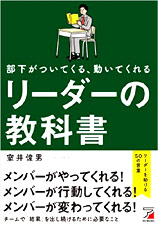国連主義による国際貢献の道
第二次世界大戦の敗戦処理を終えて、1955年に永世中立を掲げて国際社会に復帰したオーストリアが国の進路の指標としたのが国連連合(国連)中心主義による平和外交だった。
独立と同時に国連加盟を認められたオーストリアは、2年後には原子力の平和利用を推進し、核物質の監視を行う国際原子力機関(IAEA)の本部を首都ウィーンに誘致した。また、冷戦が深刻化する1971年から2期10年にわたり、のちに大統領となるクルト・ワルトハイムが国連事務総長を務めた。
政府は、ドナウ川左岸の土地を緑地公園化して国連に実質無償で貸与し、各種国連機関の誘致に乗り出した。現在ウイーンのUNシティには国連教育科学文化機関(ユネスコ)、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)など数多くの国際機関が集中立地している。ウイーンは、国連本部のあるニューヨーク、スイス・ジュネーブと並ぶ国連都市なのだ。変わったところでは、石油輸出国機構(OPEC)の本拠も1965年以来、この地にある。中東の戦乱でレバノンから退避した国連パレスチナ難民救済事業機関の仮事務所もウイーンにある。
国際社会との繋がりこそが、地政学的に欧州の東西の接点にある人口900万人の小国の生き残る道だというオーストリアの強い決意の表れでもある。同じく国際平和国家を自認し、国際機関への最大資金拠出国の一つである日本とは、国際社会における比重に大きな開きがあることは知っておいたほうがよい。
冷戦終結への対応
大戦後の世界を規定した冷戦構図の中で、東西両陣営の最前線に位置する永世中立国家としてのオーストリアは、冷戦構図終結時にその存在感を発揮する。
1989年に起きた「ベルリンの壁崩壊」という大事件では、オーストリアは陰ながら大きな役割を果たす。東ドイツの政治・経済的混乱から東ドイツ市民の間に国外脱出の動きが高まる。同じ東側ながら、改革派が政権を握ったハンガリー経由で西ドイツを目指す亡命希望者は、行き場を失いハンガリー国内に大量に足止めされる。オーストリアは、ハンガリーと西ドイツに国境を接している。ハンガリー政府は、オーストリアとの間の「鉄のカーテン」開放を選択する。当初、両国国境の自由往来を認められたのはハンガリー国民に限られていたが、国境で企画された東西諸国民の交流事業に一枚噛んだオーストリア政府は、同事業を口実に東ドイツ市民の越境を容認し、オーストリア経由で西ドイツの難民収容所への移動を認める。このうねりがベルリンの壁を壊すことに繋がり、冷戦は終結に向かう。
1990年になると、ハンガリーの南で東陣営の最前線にあった多民族国家のユーゴスラビアも鉄の結束が崩れて民族間の紛争が激化する。この時にオーストリアが取った立場は、「もはや、ユーゴスラビアを統一国家として維持することは困難」というものだった。ハプスブルグ家によるバルカン半島統治の歴史から得た判断だった。ユーゴ統治勢力のセルビアからの独立を目指す、クロアチア、スロベニア、ヘルツェゴビナを次々と国家承認し、民族紛争を収拾の方向へ持っていった。かつて統治した土地での負の歴史から逃げず、積極的に関与する姿勢が今も評価されている。このあたりも日本の戦後の真反対にある。
ウクライナ事態と国の進路
戦後一貫して非軍事同盟を貫くオーストリアはもちろんロシアを仮想敵とする北大西洋条約機構(NATO)には加盟していない。しかし、独立と同時に連邦軍を組織し、成人男子に6か月の徴兵制を敷いている。兵力は陸軍、空軍合わせて6万人だ。武装中立の立場は隣国スイスと同じだ。防衛軍事力として最低限のレベルだが、世界各地の紛争地には、積極的に平和維持軍を送り込んできた歴史がある。
そのオーストリアで、軍事力強化の世論が高まりつつある。ロシアによるウクライナ侵攻の影響だ。政府は、2027年度までに防衛費を大幅に増額し、国内総生産(GDP)比1.5%に引き上げる計画だ。冷戦終結で、ロシア勢力との最前線は国境からはるか東側へ移動した。しかし、国際外交頼みで、ウクライナのような事態が起きた場合、今の装備と兵力で国を守れるのかという問いだ。NATOが打ち出している軍事費は、対GDP比で2%だ。政府は保守勢力からの突き上げにあっている。非同盟を貫いてきたスウェーデン、フィンランドのNATO加盟で、欧州内での孤立感も深まっている。
「国際情勢は大きく動いている。永世中立の憲法規定も時代に合わないのではないか」との声まで、保守派野党や識者から上がり始めている。
(書き手)宇惠一郎 ueichi@nifty.com
※参考資料
『オーストリア 永世中立国際国家』大西健夫・酒井晨史編 早稲田大学出版局