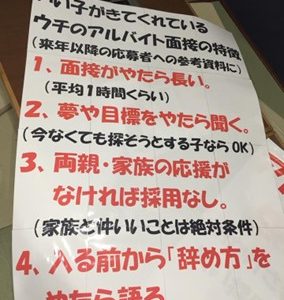後継者の決断
軍旅の途中で武田信玄を失った息子で後継者の勝頼と家臣団の動揺は大きかった。後継者とはいっても、勝頼の立場はあまりに微妙だ。信玄は遺言で、家督は孫の信勝(のぶかつ:勝頼の子)に継がせると明言している。勝頼は、わずか7歳の信勝が成人するまでの“つなぎ”としての後見の役割しか与えられていない。信玄の遺言は、重臣たちに「孫を担いでクーデターを起こし、勝頼を排除せよ」と命じているのに等しい。
勝頼が取るべき道は一つしかない。偉大な父・信玄の体制から、自分中心の新たな体制に革新するほかはない。信玄も若き日に、その父・信虎(のぶとら)を今川家に追放し、クーデターで支配権を獲得した過去があった。ここまで無碍にされては、それに倣うほか武田家が生き残る道はないと考えて当然だった。
勝頼には、父が築いた(源氏の血を引く名門武田家と領地内の豪族との連合政権)は、時代に合わないという考えがあった。織田信長ばりに、中央集権的な強固なピラミッド構造の統治が必要だ。それでこそ安定的な軍事動員も可能になると思い描いていた。「新しき酒は新しき皮袋に盛る」。新しい武田家をつくる。勝頼は早速、改革に取りかかる。
攻めこそ最大の防御
遺言の一件によって、勝頼と信玄以来の家臣との間には、微妙な空気が流れていた。後見の立場でしかない勝頼に忠誠を尽くせるか、という疑問である。勝頼は機先を制して家臣たちとの間に、従来の役割を保証するとともに忠誠を誓わせる起請文(契約書)を取り交わし勝頼体制に組み込んでいく。
また、信玄が勝頼に言い遺した、「当分、他国に攻め入らず専守防衛に徹すること」という戒めも破り、周辺国へと軍を率いて攻め込んだ。新たな大将を中心とした結束を高めるには攻撃に勝るものはない。軍事の大原則である。
美濃の前線では信長同盟軍を蹴散らし、遠江(とおとうみ)では、信玄も落とせなかった高天神城を落城させている。さらに勝頼は、上野(こうずけ)、越後へも攻め入って、信玄の死から七年後の1580年(天正8年)には、武田領は信玄時代を超える最大版図を実現するに至る。
この間、勝頼は宿敵上杉謙信との間で和睦を成立させ、武田領攻略を虎視眈々と狙う信長を牽制する外交的したたかさも見せている。
一方で、勝頼は1575年(天正3年)5月、奥三河の長篠城奪還をめぐる長篠の戦いで、物量作戦に打って出た織田・徳川連合軍の前に手ひどい惨敗を喫している。山県昌景(やまがた・まさかげ)ら信玄以来の名将の多くを失い、ほうほうの体で逃げ戻った勝頼は、これを世代交代の好機と見て、諸将の代替わりを急ぎ、「勝頼の軍隊」に変身させている。長篠の敗戦の3か月後には、勝頼は13,000余の兵を率いて遠江に姿を現し、家康を驚かせている。
家康の謀略と家臣の叛逆
しかし、うち続く戦さで疲弊した重臣たちと勝頼との確執は次第に表面化する。その引き金となったのが、勝頼による韮山新府の築城だった。元はといえば、「人は城、人は石垣、人は堀」と豪語して、拠点城を持たなかった信玄の防衛戦略の欠陥があったのだが、これを改革の柱と位置付ける勝頼による城普請は、人夫を大量動員する諸将の間に不満が鬱積していた。
「先代はこんなことはなさらなかったのに」。この不和に目を付けた家康は、武田の重臣たちに密かに調略工作を仕掛けていた。
そして徳川軍は、天竜口から諏訪を経て甲府に向け雪崩れ込む。武田の重臣たちは次々と寝返る。一旦は、諏訪から甲府盆地への喉元である韮崎で侵攻を食い止めようとした勝頼だったが、新城はまだ未完成だった。韮崎を放棄して東へ落ちのびる勝頼の軍勢から次々と家臣たちは離れ、天目山で勝頼が果てたとき、周りにはほぼ女たちしか残っていなかったという。
今に伝わる「信玄は賢将、勝頼は武田家を滅ぼした愚将」という常識は、武田領を乗っ取り、武田家臣団の多くを取り込んだ家康の「信玄公は偉かった。勝頼は馬鹿だから滅ぼした」という信玄家臣たちを褒めて使う筋書きなのだ。
武田滅亡の張本人は、後継問題を処理できず旅立った信玄の無策と言えるのではないか。カリスマ創業者だけでは家は続かない。
(書き手)宇惠一郎 ueichi@nifty.com
※参考文献
『武田三代』平山優著 PHP新書
『戦国武将に学ぶ「危機対応学」』童門冬二著 角川SSC新書
『名将言行録』岡谷繁実著 北小路健、中澤惠子訳 講談社学術文庫