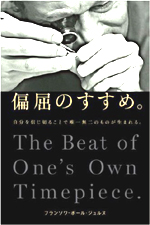野中郁次郎は、なぜ理論に「主観」を持ち込んだのか
社会科学の建前からすれば、理論の評価基準は一般的な説明能力の頑健性にある。理論は客観的で価値中立的であるべきで、理論をつくる側が主観的に感じる明るさ・暗さは理論の価値とは関係ない。だから、普通の研究者はある理論を批判するときに「暗い」というような表現は使わない。
ところが、野中郁次郎先生は違った。先生にとっては、理論は自らの存在や経験や信念や感情を丸ごとぶち込んで煮詰めるように創りあげるものだった。生身の人間としての自分が感情的に入れ込める理論でなくては意味がない。これが野中先生の信念だった。そもそも知識という野中理論の基本概念からして、その定義は「正当化された真なる信念」だ。信念である以上、主観がたっぷりと含まれている。
先生と最後にご一緒した仕事は昨年の対談だった(「理論は創るもの」『Executive Foresight Online』2024年5月)。その中で先生はおっしゃっている。「理論とはあくまでも個人の体験をベースに創るもの」「経験の質量がキーポイントになる。近年のビジネスの潮流を見ていると、経験よりも分析が重視されているように感じる」「事実を分析的に羅列したって何も面白くない。その人の生き方が投影されて、初めて面白いコンセプトを創ることができる」——ここに野中理論の真骨頂がある。
「考え続ける研究者」野中郁次郎の原点となった一枚の写真
一連の知識経営の理論は、野中先生ご自身の人生や経験、そこから醸成された人間観や価値観を観察対象に叩きつける中で構想されたものだった。対象を客観的・中立的にとらえて抽象的な思考を重ねるだけでは、SECIモデルのような壮大な枠組みは絶対に思いつかない。先生自らの暗黙知――経験に基づく直観と五感を駆使して獲得した身体知――を総動員したからこそ、あのような独自のアイデアが生まれた。頭だけでこねくり回したものではなく、腹の底から出てきている。だからこそ、あれほど抽象度の高い理論でありながらも、多くの人にとって腹落ちするものとなった。
僕は2000年に新設されたビジネススクールに移ったのだが、そこでも野中先生と一緒だった。研究室が同じフロアにあったので、しょっちゅう先生をお見かけした。いつも本を読んで、考えていた。思考に対する集中力が尋常ではない。最後まで先生の知的探究心は衰えることがなかった。
野中先生が暗黙知の重要性を確信したきっかけの一つが、ホンダ創業者の本田宗一郎さんの一枚の写真だった。サーキット場で地面に顔をつけ搭載エンジンの響く音から車の性能を見極めようとしている本田さんの姿を見て、野中先生は直観的に「これだ!」と思ったという。人間には優れた暗黙知がある――その後数十年にわたって続く知識経営の研究の出発点だった。
野中郁次郎と本田宗一郎に共通する「人間観」
つくづく思うのだが、野中先生は本田さんに似ていた。僕はもちろん直接本田さんにお目にかかったことはない。それでも本田さんの自著や評伝を読み、生前の本田さんと交流があった方々のお話を伺うにつけて、野中先生と酷似していると思うようになった。野中先生を通じて本田宗一郎さんはこういう人だったのではないか、と想像するくらいだ。自分の信じた道を迷わず進む。全身で対象をつかむ。自らの手を動かして創造する。当人の人間性を創造物に丸ごと投射する。人間が好きで、人に愛される。何よりも、底抜けに明るい――お二人とも天才的な人間である以前に、人間についての天才だった。
僕との対談の中で、野中先生が本田宗一郎さんに似ているという話をすると、先生はこう言った。
どうだろう、似ているのかな。アメリカ留学から帰国してしばらく経った頃、ホンダからの依頼で講演したことがあります。講演中、ずっと僕の話にうなずいてくださる男性社員がいました。それも、全身を動かして、いちいち共感を示してくれる。個性的な方だなあと思っていたんです。講演が終わったあと、その方がつかつかと僕のところに歩み寄ってこられて「どうもありがとう」と。それが本田宗一郎さんでした。
「私の手は、私がやってきたことのすべてを知っており、また語ってもくれる。私が話すことは、私の手が語ることなのだ」――本田さんの著書『私の手が語る』にある言葉だ。野中先生が全身をぶつけて創り上げた理論もまた先生の手が語ることだった。
お別れの会で参列者に配られた野中先生の写真の裏に、先生が遺した15の言葉が記されている。その最初にあるのが「経営とは、生き方(a way of life)である」――本田宗一郎さんにとって、経営とは彼自身の生き方だった。野中先生にとっても、理論とは生き方そのものだった。見事な生き方。唯一無二にして空前絶後。今後ともこのような全身経営学者が出てくるとは思えない。