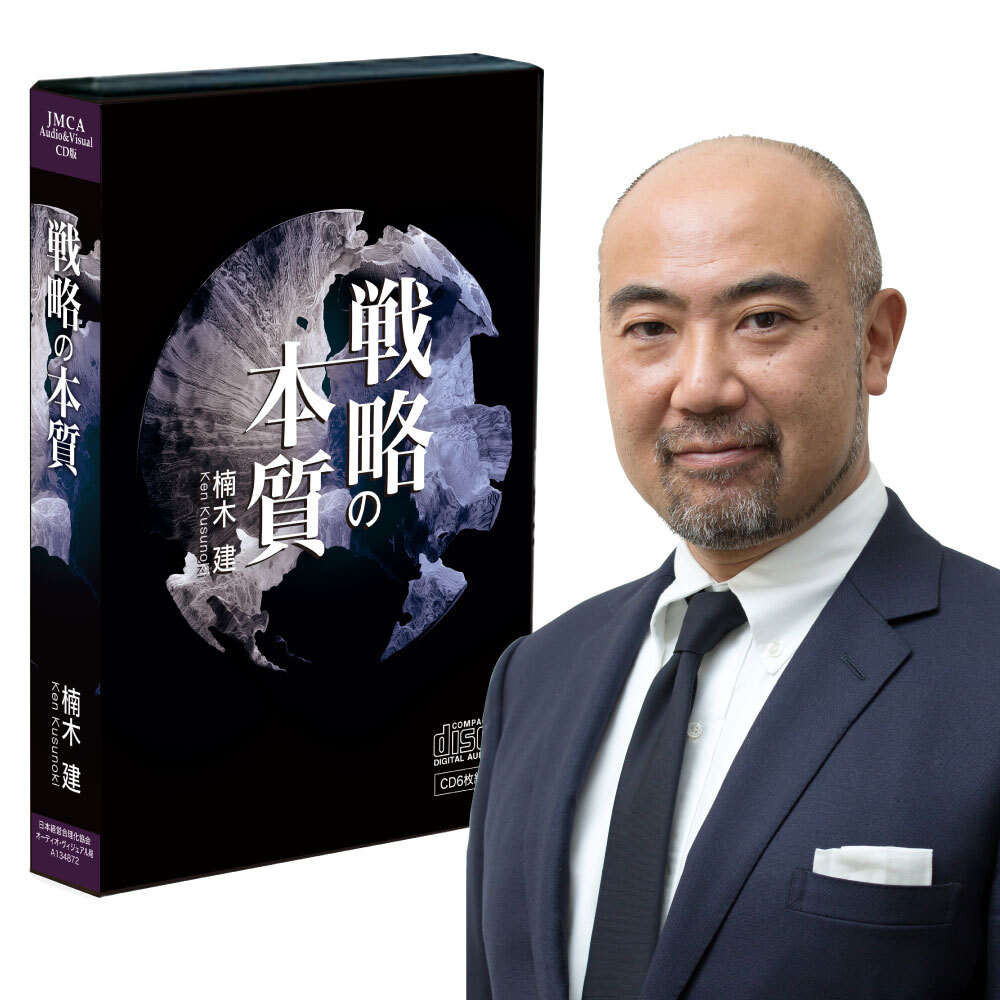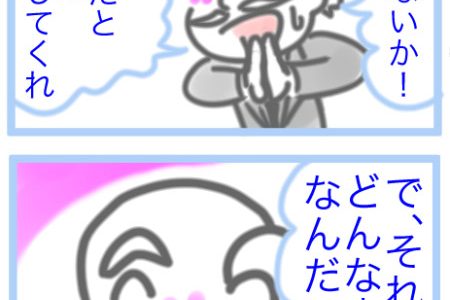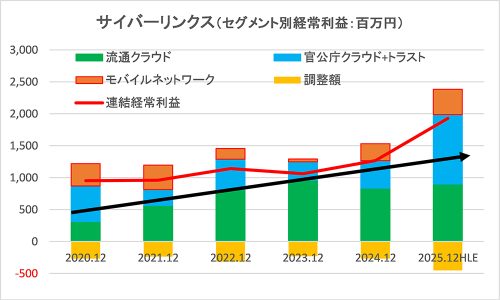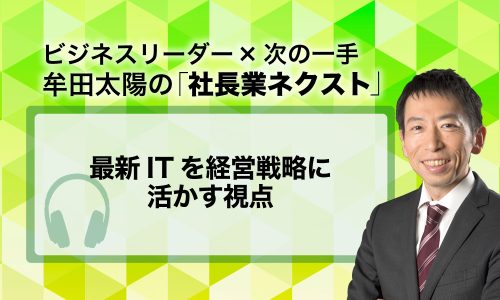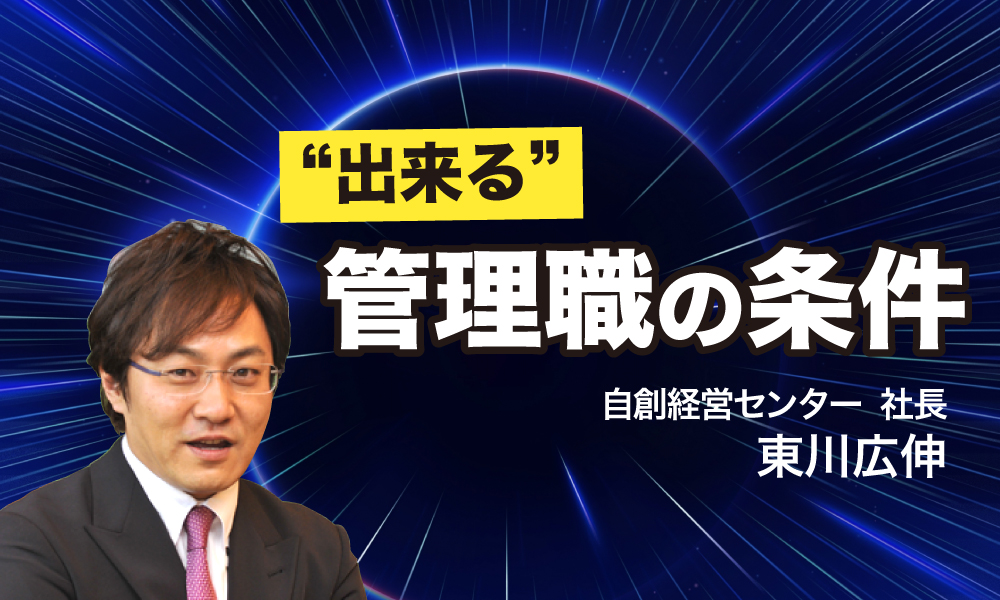感情、感覚、直感を重視するリーダーシップの新しいパラダイム
少し前にニコラス・ヤンニ『最強のリーダーは人を癒すヒーラーである』という本を監訳した。
現在の企業文化は行動(doing)モードに支配され、存在(being)モードが希薄になっている。理性的で分析的な思考を重視するあまり、感情、感覚、直感といった本来人間に備わっている重要な能力が軽視されている。
問題解決に向けた行動ばかりを繰り返し、存在の重要性を見過ごしている。従来のリーダーシップのパラダイムの下では、感情は弱さの表れであり、非合理で予測不可能なものとして排斥される傾向にある。
こうした前提を再考するところからリーダーシップを語るべきではないか――この本の目的はリーダーシップの新しいパラダイムを提示することにある。
「執行者」としてのリーダー
著者はリーダーシップのモデルを二つに分けるところから議論を始める。すなわち「執行者としてのリーダー」と「癒し手としてのリーダー」だ。
これまでのリーダーシップ論は多かれ少なかれ執行者としてのリーダーに偏っていた。リーダーの役割は、純粋に合理的な意思決定を下し、成長と効率性を目指して集団を統制することにあるとする見方が一般的だった。その一方で、他者に共感し、自分の弱さをさらけ出し、人との繋がりを築くといった特性を弱点とみなしてきた。
執行者としてのリーダーの思考や行動は狭帯域(ナローバンド)に押し込められている。理性的で戦略的な思考を優先する結果、感情や身体性をもった自己から切り離されてしまう。他者の話に耳を傾け、他者を受け入れることができなくなる。
「癒し手」としてのリーダー
一方の癒し手としてのリーダーとは何か。
著者の言う「癒し」とは、われわれが一般的にイメージする身体の癒しというよりも「統合の回復」を意味している。
従来のリーダーシップやマネジメントのパラダイムの下で分断されてきた個人の感覚を一つの調和した統一体にまとめ上げる。
頭で考える自己と感情をもった自己のバランスを取り戻す。
感情や感覚を持った存在としての自己を伝える。
人と人とのつながりが持つ力を認識し、人々に認知と感情と身体を一体化させた自己の発揮を促す――そこに癒し手としてのリーダーの本領がある。
思考力と想像力を高める「存在モード」
この意味での「癒し」は組織のパフォーマンスを犠牲にするものではない。
行動モードで仕事をこなすことばかり考えていると、人から言われたことを無条件に受け止め、その背後にある感情や感覚をほとんど意識しなくなる。著者が言う「不在の文化」だ。
不在の文化は効率を追求しているように見えて、実際のところ組織の効率を阻害する。
自分を開いて相手の言うことに耳を傾け、相手の考え方や心の中にある感情を受け入れれば、はるかに迅速に多くの情報を得た上で行動を起こすことができるようになる。
相手の話を傾聴すると、相手に寄り添った的確な対応を取れるようになる。時間の無駄がなくなるだけでなく、相手との絆が深まり、協力して行動することによって、思考力や想像力が高まる。
つまり存在モードを重視する癒し手としてのリーダーは、効率と効果の両面で組織のパフォーマンスを高めることができる。
リーダーシップを進化させる「デジタル化」という補助線
興味深いのは、著者が提示する癒し手としてのリーダーというモデルがなぜ今になって大切になってきたのかという理由だ。
著者によれば、その最大の理由は組織や個人が直面している現在の環境変化にある。
VUCA(変わりやすく、不確実で、複雑で、曖昧)な環境やBANI(脆弱で、不安で、非直線的で、理解するのが難しい)な状況にあって、これまでのリーダーシップでは対処できなくなっていると言う。
それはそうなのだが、ここに「デジタル化」という補助線を引いてみると、いよいよ問題の所在ははっきりする。
不確実性や複雑性に対応する手段としてAIなどの情報技術が有用なのは言うまでもない。今やデジタル化はメガトレンドであり、今後とも仕事の現場でさまざまなデジタル技術が浸透しているのは間違いない。
しかしその一方で、デジタル化には著者が問題としている不在の文化や行動モードの偏重をさらに促進するという面がある。
VUCAな環境に対処するためにデジタル化を推し進めるほど、個々人の感覚や感情が分断され、その結果として不確実性や複雑性に対処できなくなるという皮肉な成り行きに陥っている。
私見では、本書が言う意味での癒し――個人の感覚を一つの調和した統一体にまとめ上げる――が求められるようになった一義的な理由はここにある。