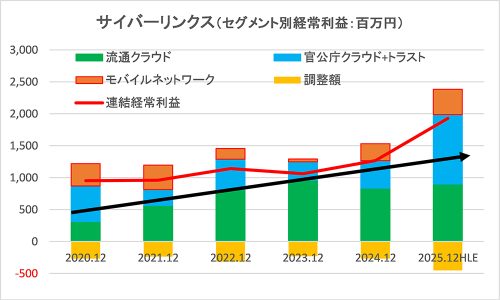経営者として最上級の英断を果たした丹羽宇一郎氏に学ぶ
バブルの後遺症を引きずる伊藤忠の社長だった99年、4000億円の不良資産を一括処理し、翌年には史上最高益を叩き出した丹羽宇一郎氏。これは経営者として最上級の英断と言える。
丹羽さんには多くの著作があり、どれをとっても勉強になる。例えば美しさと結果は比例するという話。ビジネスマンでできる人は仕事の仕方が美しい。無駄な力が入っていない。余計な動きがない。理にかなった仕事の仕方は傍から見ていて美しいものだと言う。
悪い心を持たない人はいない。無理に打ち消す必要はない。無理やりなくそうとすると、自分を偽ることになる。「自分はまだこの程度の人間なんだな」と自己認識を新たにする。そうやって自己理解を深めるほうが多少なりとも人間の器を大きくすることになる――悪い心をふんだんに持ち合わせている僕にとっても指針として有用だ。
丹羽さんはとにかく裏表がないストレートな人で、役員時代のエピソードが面白い。社長を含め、役員たちで料亭で会食をしていたとき。自分の上に入る専務が社長のおべんちゃらばかり言っている。「社長のお話は本当に素晴らしい」と何度目かのお世辞を言ったとき、ついに我慢がならなくなった丹羽さんは「貴様、いい加減にしろ! 社長がいまいったことは全然いいことなんかじゃない!」――実にイイ話だ。
社長の給料を「ゼロ」に?
伊藤忠のリストラの真っ最中、2000年の『文藝春秋』6月号に丹羽さんが寄稿している。当時、丹羽さんは社長(自分)の給料をゼロにするという意思決定で注目されていた。その真意を語る記事だ。
日本経済がバブル崩壊の後遺症からなかなか回復できないでいた当時、多くの企業が不良資産の処理に苦しんでいた。伊藤忠も二期連続で無配を続け、役員報酬はもちろん、一般社員の給与削減を実施していた。
この時点で社長に就任して三年目を迎えた丹羽さんは、それまで自らに課していた報酬五十%カットからさらに踏み込んで、社長だけは完全に無給とすることを発表。本人は飄々としている。
「だいたい七対三の割合で歓迎してくれる社員のほうが多いようです。ただし、社員でも海外の反応は逆で、かえって会社のイメージを悪くするからやめてくれ、という反応が多かった。驚いたことに、発表した数日後には外国の友だちからも連絡があって、彼は「グッド・ディシジョン」だという。
ひとのことだと思って何を言ってるんだという気もしますが、そもそも私が無報酬になったところで、ほとんどの人には何の関係もないことです。当たり前ですが、大変でしょうと声はかけてくれても、これを差し上げますとお金を持ってきてくれる人は一人もいません(笑)」
「責任」と「ケジメ」
注目すべきは、無給の背後にあった経営者としての意思だ。二十世紀のことは二十世紀中に片づける。ため込んだ負の遺産は全部片づけて、二十一世紀からは大攻勢に転じるというのが丹羽の経営方針だった。
「実は、無報酬は私の独断で決めたことです。役員会で話し合って決めたわけでなく、先月十日の取締役会で私から発表しました。その場で一部の役員から「社長だけが責任を取るのはおかしい。私も無報酬でいい」という発言も出た。(中略)「責任はみんなで、ケジメは一人で取ろう。みんなの分をまとめて私がやったと思ってくれ」と言って、気持ちだけ受け取る形にさせてもらいました。それでも一部の役員は返上したいというので、「じゃあその分、僕がもらおうか」と言ってやりました(笑)」
「責任」と「ケジメ」、この2つの言葉は同じ意味で使われがだが、丹羽さんははっきりと区別している。そもそもケジメとは、連続する物事に区切りをつける、前と後の境目をはっきりとさせるという意味だ。
変革者は破壊者であり、切断者でなければならない
伊藤忠は収益構造を大きく変えようとしていた。「ラーメンからミサイルまで」と言われたように、従来の総合商社は事業の間口を横に広げて、取引の手数料を収益源としていた。バブル崩壊を受けて、伊藤忠は自らリスクを取って投資をし、事業主体となる方向に舵を切った。
取引手数料から事業投資へという収益構造の転換は決して独自の構想ではなかった。Aという現状からBという将来の姿へのシフトが変革だとすれば、Bについてはどの総合商社も一定の構想を持っていた。もちろん誰も正確に未来を予見することはできない。
Bが成功する保証はどこにもなかったが、少なくとも将来の姿は描けていた。変革の難しさは、Bを描くことにあるのではない。Aを破壊し、それまでの流れを断ち切る方が何倍も難しい。Bを掲げながらいつまでも変革を実行できない企業が多い理由もまたそこにある。
「二、三年にわけて償却するソフトランディングの方法もあったとは思います。しかし、スピードが要求される時代に不良資産に足を取られている余裕はない。今期、経営資源を重点分野に配分すれば、二〇〇〇年度は単体で二百億円の純利益を計上できる自信があります。巨額損失の処理はこれが最後。この十五年間に溜まった膿はすべてきれいに片づけたつもりです。
私は、伊藤忠を性格的に明るい会社にしたいと考えています。ここで過去を断ち切って、二十一世紀は大きく飛躍したい。おたがいに指さしあって責任を押しつけあったり、業績悪化したのはあの先輩のせいだと陰口をたたくようなことはもうやめる。これで、豹が獲物に飛びかかる前のように、ぎゅっと屈みこんでジャンプする寸前と態勢はできました。これからは守勢から一転して攻撃と実行の時代が来ます」
ケジメをつける。これまでを破壊し、流れを断ち切る。だから、明るく元気に未来に踏み出せる。変革のリーダーは何よりも破壊者であり、切断者でなければならない。言葉の正確な意味で、丹羽さんは変革の経営者だった。彼は伊藤忠の中興の祖ではあるが、その正体は「中断の祖」だった。