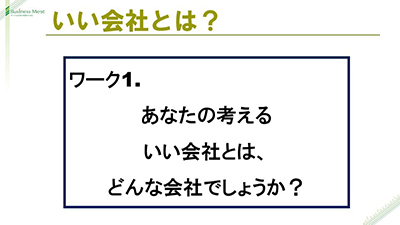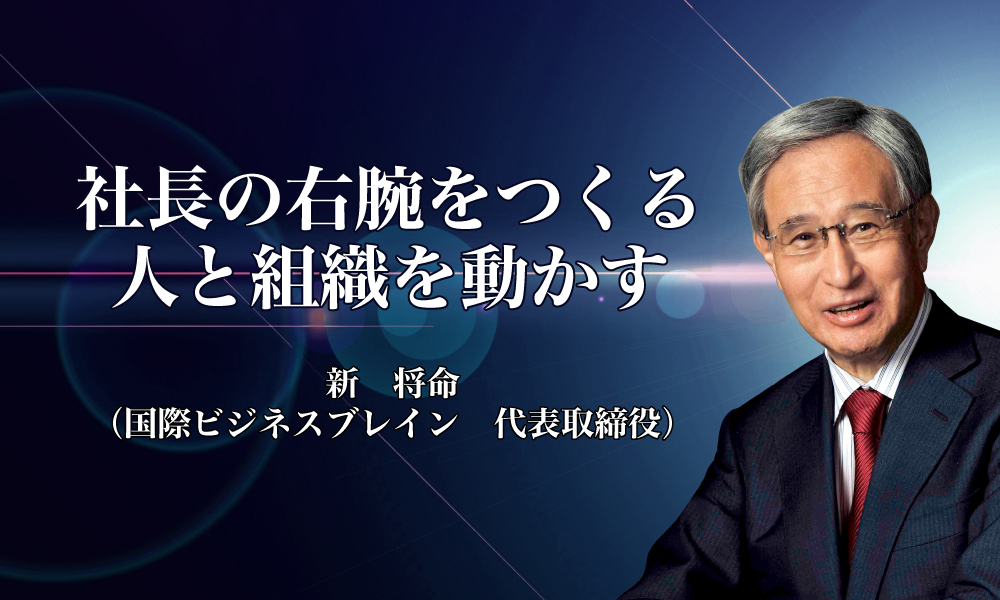二代目はつらいよ
一族経営の大組織を親から引き継いだ二代目ほど窮屈なものはない。一般的に事を起こした創業者は、自分の成功体験に対するうぬぼれが強いから、自ら作り上げた組織運営、経営システムへの修正を許さない。跡取りには、そのままの事業継承を強要する傾向が強いものだ。
一方で、親が一代で築き上げた新興の巨大組織が永続するかどうかのカギはまさに二代目が握っていると言ってもよい。潰れる組織は大概、二代目で傾くものだ。『貞観政要』(じょうがんせいよう)の項目で触れたように、「創業」よりそれを引き継ぎ発展させる「守成」の方が難しい。永続にしくじった組織の崩壊責任はおよそ二代目の責任に帰せられることが多い。
徳川幕府を開いた家康は、すこぶる付きのカリスマ経営者であったから、若くして二代目に指名された秀忠(ひでただ)は、自由裁量のなさにさぞかし辟易(へきえき)としただろう。映画「男はつらいよ」ではないけれど、「二代目はつらいよ」である。
しかし、徳川政権が十五代、二百六十年の命脈を保ったのは、まさに二代目の秀忠の我慢と親への理解があったからでもある。
関ヶ原の勝利で事実上、天下を手にした家康の意中には後継者候補として秀忠だけがあったわけではない。秀忠の兄の秀康(ひでやす)、弟の忠吉(ただよし)はともに武勇に優れ、行動力もあった。
あるとき、家康は五人の側近たちに、「三人のうち誰を跡目にするのがよいか、遠慮せずに思うところを申せ」と問うた。譜代の重臣・大久保忠隣(おおくぼ・ただちか)は、こう進言した。
「三人のお子の武勇の優劣はつけがたいが、ひとり秀忠殿は謙遜、御孝心が厚く文徳を兼備されており、跡取りに相応しいかと」。おとなしめだが、家康の言うことを聞くだろうと言う意味だ。後日、家康は五人を前に、「大久保の言うところはわしの心と同じだ」と宣言した。二代目は、やんちゃで才気走ったものでは難しいと判断したことになる。
用意されたシステムを守り発展させる
1603年に征夷大将軍に就いた家康は、2年でその職を秀忠に譲る。秀忠27歳。だが、秀忠は、駿府(すんぷ=静岡)の隠居先から次々と出される指令をただ受け取り、忠実に江戸城から公布する作業を続ける。一人前の男が、操り人形の地位に甘んじるのは並大抵の我慢ではない。
しかし、秀忠は屈辱とは思わなかった。実直な性格そのままに耐えた。
〈自分には、父のように戦いでの実績もカリスマ性もない。であれば、今は父の権威を借りて、その統治方式を学ぶことに徹する。自分の役割は、学びつつ、父がやり遂げられなかった部分を補い、発展させること〉。そう考えた。
父は父で秀忠に引き継ぐべき統治システムの構築を急ぐ。〈創業間もない体制は弱い。全国の大名たち、朝廷、寺社を押さえ込む政治、経済システムの骨格を作り上げて、子に引き継ぐ〉。そう考える家康にとって、秀忠の学ぶ姿勢は2代目として打ってつけだった。
独自色の打ち出し方
事業を引き継いだ二代目は往々にして、父にない独自色を打ち出したくなる。二代目にもプライドがあるから、ともすれば背伸びして無理矢理に新規事業に手を出して痛い目にあう。秀忠は違った。組織の統治、経営はシステムの踏襲、維持と強化だと割り切っていた。じっくりと父の統治方式を学習することに徹した。
秀忠が独自色を打ち出すのは、家康の死後である。父が没したのは、秀忠38歳のとき。足かけ12年にわたる江戸と駿府の二元政治が解消されたとき、秀忠はしっかりと家康流の統治テクニックを体得していた。まず手をつけたのは、父が目指しながら中途半端に終わっていた外様大名に対する圧倒的支配だ。
例えば、安芸広島藩に封じられていた福島正則(ふくしま・まさのり)の改封がある。福島は、豊臣恩顧の大名でありながら関ヶ原で家康について手柄を立て、家康が亡くなると怖いもの無しの状態で、武家諸法度で禁じられた城壁の改築に乗り出していた。秀忠はこれを見逃さず、福島を津軽に配流(はいる)する。
家康でさえ二の足を踏んでいた、暴れん坊大名の処分に乗り出した。これを手始めに、全国41の大名家を取り潰した。合わせて439万石の所領を没収し、徳川一門、譜代の家を大名に取り立てて全国に配置する。これにより幕府の権威を高め、外様大名を封じ込めることに成功する。若様として軽んじられてきた二代目よるこの力技によって、幕府は揺るぎない地位を確立することになる。
そして7年後、四十五歳の秀忠は、息子の家光(いえみつ)に将軍職を譲り、大御所として君臨することになる。
まさに父の政治手法を踏襲して見せる。これで徳川将軍家の世襲は、もはや揺るぎない既定の事実として天下に宣言された。
(書き手)宇惠一郎 ueichi@nifty.com
※参考文献
『徳川秀忠 徳川政権の礎を築いた男』百瀬明治著 P H P文庫
『徳川三代99の謎』森本繁著 P H P文庫