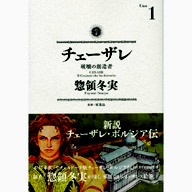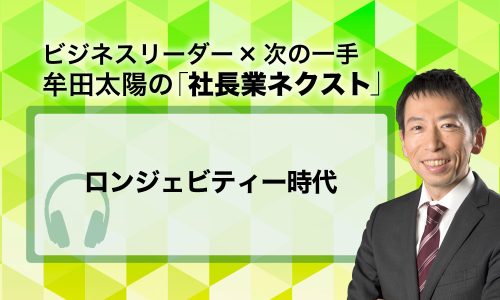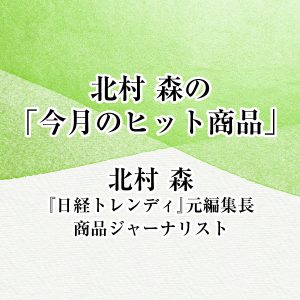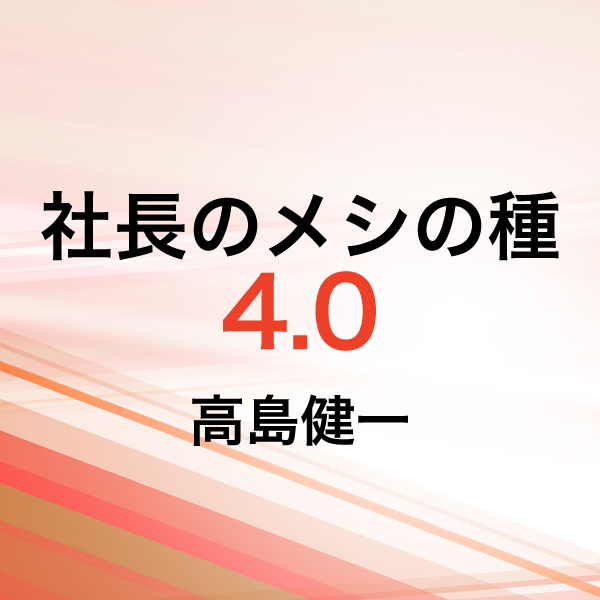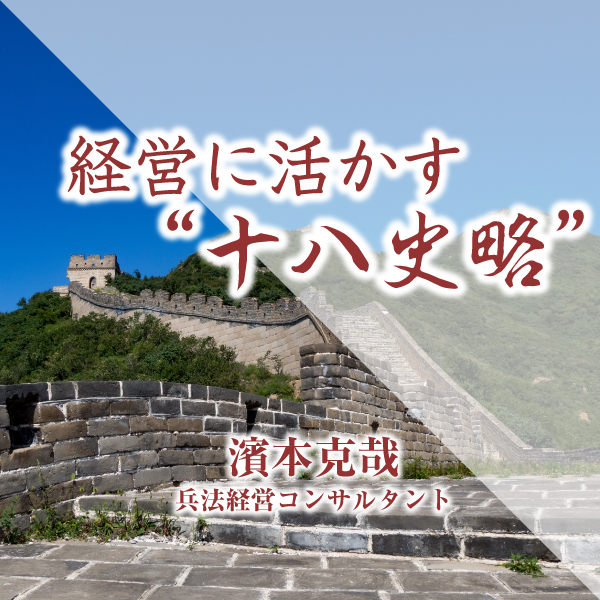国防と外交は表裏の関係
日本という国は、古代から開国と鎖国を繰り返してきた。遡れば、邪馬台国の時代から、中国という強大な隣国と外交を続けて先進の文物を取り入れ、古代における「近代化」を図ってきた。しかし、7世紀に始まった遣唐使も9世紀末に唐が衰退すると廃止され、復活することはなかった。より身近な朝鮮半島との交流も途絶えたままの時代に「刀伊(とい)の来襲」は起きている。
中国には唐に代わって宋が、半島には新羅のあと高麗が統一を果たしているが、わが国は国交を閉ざしたままで、東アジアの国際情勢から取り残されていく。ウクライナの情勢を見ても国防と外交は国際関係の表裏なのだ。平安王朝時代の日本は、対外交易も途絶えて孤立状態にあった。朝廷の官僚貴族たちは全く外交に無関心で宮廷内序列をめぐる権力闘争に明け暮れている。「国を閉ざしておけば安全、安心だ」という、島国ならではの特殊な環境にあればこそだ。
海賊レベルではあったが、刀伊を追い返した後も、朝廷が外交の安定、国防強化に乗り出した形跡はない。こんなエピソードがある。
日本と同じく、海岸線で刀伊の襲撃を受け撃退した高麗は、日本人の人質を保護して送還し日本との外交の糸口を探ったが朝廷は無視した。また、数十年後、高麗王は、病気の治療のためにわが国から名医を送ってほしいと、信書と進物を添えて太宰府に連絡役を送ったが、朝廷は応じていない。交易を開く善隣外交は国境の安全に不可欠だが、そういう外交センスは朝廷にはなかった。
平清盛の登場と日宋貿易の開始
わが国が対外開放政策に舵を切り替えるには、新感覚を持つ平清盛(たいら・きよもり)の登場を待たねばならなかった。12世紀後半になると、宋は皇帝神宗のもとで、国威発揚のため、周辺国に国書を送り入貢を求め始めた。大国による積極外交だ。日本にも、宋の商船が瀬戸内海各地に出没するようになる。朝廷は、国書の受領さえ拒んだが、動き出したのが清盛だ。兵庫港(神戸福原)を改修して宋船を受け入れるようにした。1170年(嘉応2年)には、朝廷のトップである後白河法皇を福原の別荘に招いて宋人と会わせ、日宋貿易の必要性をアピールした。
だが、公家たちは強く反発する。右大臣の九条兼実(くじょう・かねざね)は、「こんなことは(遣唐使を廃止した)延喜以来のことだ。天魔の仕業か」と嘆いた。鎖国政策にどっぷり染まった朝廷官僚貴族たちの外交音痴ぶりもここに極まれり。大国・宋の大きな商船が、瀬戸内海を奥深く京の近くまで出没している。皇帝の国書を無視し続ければ、いつ軍船が押し寄せて開国を迫るかもしれない。まさに幕末に攘夷を叫び回った国粋主義者たちを思わせる。外交と国防を、平安期を通じて続いた「鎖国=国防」の幻想に踊らされていた。
貿易、経済立国=国防の発想
太宰府長官の経験がある清盛は、日宋貿易の拠点として博多の有用性を熟知しており、その地の港湾建設に力を入れた。かつて異賊と戦った地が交易拠点になる。
保守的な貴族たちは、清盛の交易熱心を「私腹を肥やすためだろう」と批判した。しかし、清盛の発想は、貿易立国、商業立国を目指すものだった。それこそが強い国を作ること、究極の国防だと考えていた。
交易品を見れば、それが裏付けられる。宋からの輸入品で最も多いのは宋銭で、あと香料、薬品、陶磁器、織物、さらに絵画、書籍などの文化関連品もある。先進国から学ぶ姿勢だ。宋銭は、国内流通に使い貨幣経済を盛んにさせようとしたものだ。日本からは、金、銀、木材、水銀、硫黄など、宋が求める、国内の特産品を送り出し、宋を喜ばせる。
それまで密貿易は細々と行われていたが、これを国家間の公式ルートに乗せることで、国家の財政も潤う。
経済力、貿易力をつけることこそ、国家の安全と繁栄につながる。戦後日本の国家理想を清盛は先取りしていた。軍備増強だけが国を守るのではない。
(書き手)宇惠一郎 ueichi@nifty.com
※参考資料
『日本の歴史6 武士の登場』竹内理三著 中公文庫
『刀伊の入寇 平安時代最大の対外危機』関幸彦著 中公新書