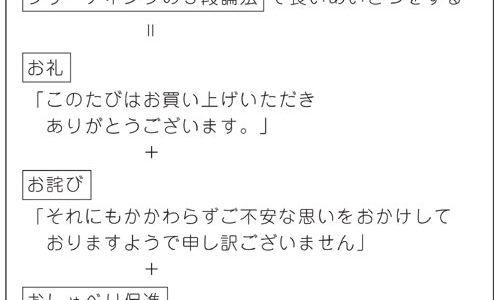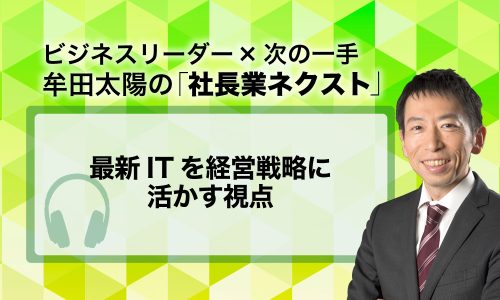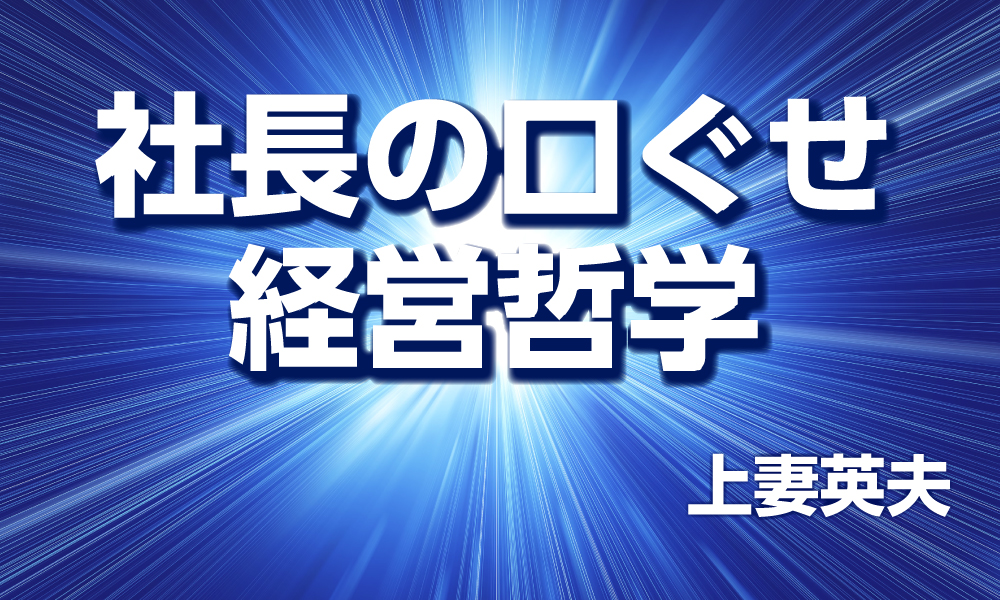経営自主決定権のない奇妙な鉄道会社
子供のころから鉄道ファンだった筆者にとって、学生時代を過ごした1970年代の国鉄の姿は異様だった。帰省先から上京する切符を新大阪駅で求める。学割証明を見せようものなら、カウンターの中の若い出札係員、チェッと舌打ちして切符を投げてよこした。上京して朝の通学時、山手線は無ダイヤ状態が日常のことで、池袋駅のホームに向かう階段は人が溢れ、やっと入線した電車には、「順法闘争中」とペンキで殴り書きしてあり、学生の「尻押し」アルバイトにぎゅうぎゅうと車内に押し込められる。職員はみな殺伐としていた。これが国民の足なのか、慄然としたものだ。
昭和24年、国鉄は鉄道省から切り離されて、独立採算制の公共企業体(公社)として再スタートしたが、幹部人事、運賃は国会の承認が必要で、政治の思惑で運賃は低く抑えられていた。職員の賃金も自ら決定できない。こんな体制で、営利の感覚など経営者が持てるわけがない。不採算新線も政治家から建設を押し付けられる。
経営陣は、矛盾をはらんだ企業組織のままで「自主再建」に取り組んだが成就する展望もない。「民営化」という荒療治は必然だった。
分割民営化への障害
行政改革推進を目指す第二次臨時行政調査会(土光敏夫委員長)は1982年(昭和57年)7月に政府に提出した第三次答申の中で、「国鉄の経営状態は、危機的状況を通り越して破産状態である」と厳しく断じた。そして、「経営の改善するためには、抜本的経営形態の変更しかない」として、5年以内に分割による民営化に踏み切るよう提案した。
国鉄の収支欠損(赤字)は、1980年段階で1兆円に達している。主な赤字の要因は二つあった。一つは、モータリゼーションの波によって、地方の鉄道離れの進展だ。戦後復旧の足として貨物、旅客の輸送を担ってきた国鉄だったが、輸送シェアは、赤字転落前の1960年に50%、そして1985年には23%と半分以下に落ちている。二つ目の要因は、過剰な要員を抱え込んでいることによる人件費の圧迫にある。
この二つの障害を乗り越えなければ、民営化しても、元の木阿弥になる。とくに人員整理は、1986年段階で27万7千人だったが、18万3千人までスリム化する必要があると試算された。9万4千人もの大量解雇が可能なのか。
官僚的精神を逸脱した若手リーダーたち
労働組合の中で最も強硬に分割民営化に反対したのは国労だった。民営化が浮上した当時、18万7千人の組合員を抱える日本最大の労組だった。最大野党・社会党を支える総評の中核的存在だ。国鉄の経営陣はこれまでも手をつけない聖域だった。
国鉄は、巨大な官僚機構だ。特別採用された優秀な一部のトップエリートたちが、27万人を超える巨大組織の現場を束ねる。一糸乱れぬ結束で指示を末端まで届け統率する。戦後一貫して「国鉄一家」と呼ばれてきた。その官僚機構のおかげで、世界にも稀な定時運行率を誇ってきたのは事実だ。
しかし、この連載でたびたび触れているように、官僚機構は減点主義で出世昇進の道が決まる。平時は鉄の結束をリードするが、危機あるいは新規の事態に遭遇するとリスクを背負いたがらない。労組と対立してまでの大規模リストラには二の足を踏む。そこに三人の若手エリートたちが立ち上がる。
葛西敬之(のちJ R東海社長)、松田昌士(同J R東日本社長)、井出正敬(同J R西日本社長)の改革三人衆だ。
三人は、首相官邸と連絡を取り合いながら、分割民営化の道を突き進む。組合への対処でも、「国鉄職員は一旦全員が退職し、新会社は新たに契約を結ぶ。望まないものは、関連会社で職を準備しよう」と揺さぶりをかける。鉄労など多くの労組は組織ごと新会社と労使協約を結び、国労からは、脱退が相次いだ。希望退職者は実に7万人を超えた。国労にはさらに、活動家を狙い撃ちして再契約を拒否する。あまりに強引で、マスコミからは、「分割民営化は労組潰しが目的ではないのか」と指摘されるほどだった。民営化には渋々賛成したものの、「国鉄は一体であればこそ再生も可能」として分割には最後まで反対したエリートの多くは、国鉄とともに鉄道マン人生を終えた。強引な改革だった。
1987年(昭和62年)4月1日、国鉄は姿を消し、旅客鉄道会社6社と貨物鉄道会社1社の7社体制でJ Rが発足した。
当時の分割民営反対派は、「サービスが落ちる」を理由に挙げたが、あの1970年代と今を比べて、さてどう思うだろうか。
「戦後政治の総決算」を掲げる中曽根康弘内閣の元で実現した国鉄の分割民営化。ここに一つの戦後は終わった。
(書き手)宇惠一郎 ueichi@nifty.com
※参考資料
『国鉄―「日本最大の企業」の栄光と崩壊』石井幸孝著 中公新書
『国鉄改革の真実―「宮廷革命」と「啓蒙運動」』葛西敬之著 中央公論新社