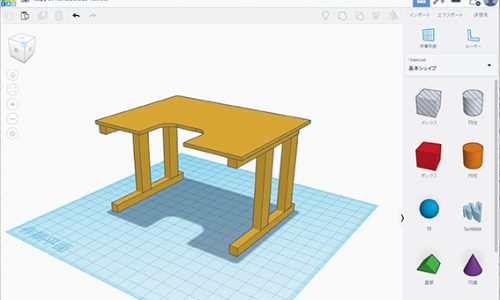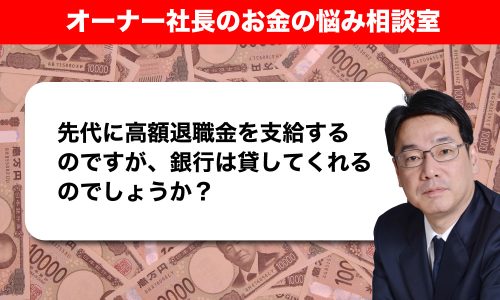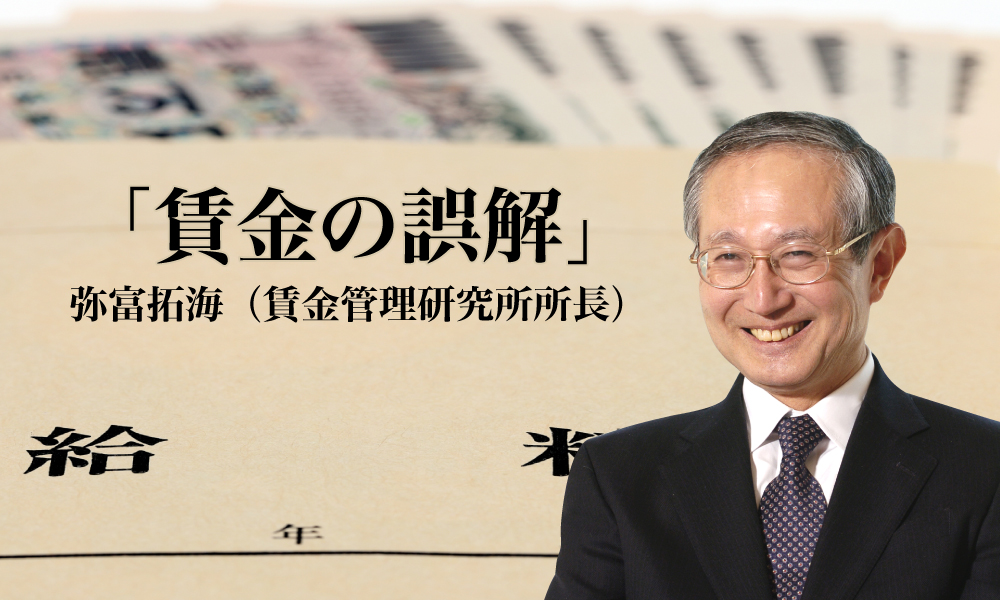激動の明治期への対応
明治維新後、近代化へ向かう日本では産業需要に合わせて多くの企業グループが勃興し、政治と結びついて財閥化して行くが、江戸期から続く豪商は時代に合わせた体質転換を迫られた。
前回取り上げた創業家の「総有制」によって、資産、事業の分散を防いだ越後屋・三井家も激動にさらされる。呉服商から身を起こし為替・金融に進出して蓄積した潤沢な資金は常に為政者からあてにされた。幕末期には、大名家への貸付金の不良債権化が経営を圧迫していた中で幕府から莫大な御用金の用立てを割り当てられた。また。続いて戊辰戦争では、新政府軍の軍資金も負担することとなる。もちろんその見返りとして種々の利権も得ることになるが、そのつど政治側の思惑に振り回される。
本家と分家の連合体11家の結束は維持されていたものの、江戸中期以降になると、次第に運営は番頭、手代に任せるようになり、11家は、資産、事業の管理に専念する「君臨すれども統治せず」の形に傾き、時代の激動に対応できず、危機を迎える。
外部経営者による経営多角化
幕末の経営危機に際して三井家は、山形・庄内藩の武家の生まれで幕府の勘定奉行と懇意だった三野村利左衛門(みのむら・りざえもん)を大番頭として迎える。三野村は幕府の御用金を減免させることに成功した。さらに幕府崩壊後は三野村に維新政府との政治折衝に当たらせ、政府の財政を握っていた長州出身の井上馨(いのうえ・かおる)に食い込ませた。三野村は井上とはかって業績不振の呉服業を切り離し、主力を銀行業に置いた。外部人材の登用で新時代に合わせた転針を成し遂げたことになる。
三野村と井上馨は、さらに外部の経営人材を次々と三井に送り込み、経営と資本の分離を進めていく。これには、創業家である三井一族の抵抗は強かったが、進取の精神に富む気鋭の経営者たちによって、製紙業、運輸業、炭鉱、紡績業、貿易など経営の多角化に乗り出し発展の道を切り開く。
創業家と経営のバランス
一方で、越後屋創業以来の伝統である「財産の総有」の思想は、営業財産は個人の所有権の上に立脚するという民法の規定にそぐわないという問題が生じた。創業家の各家が財産権を主張すれば一族分裂含みのトラブルに発展する可能性が出てくる。三井家顧問として同家の運営方針に影響力を持ちはじめた井上馨が中心となり、三井十一家の合意による「家憲」が明文化された(1900年)。
家憲は、全10章109条からなるが、要点は、「民法上は個人が財産の持ち分を主張し、分割請求する権利を持つが、三井11家の戸主はその請求をしない」という内容だ。
一族の資産運用方針は、「三井家同族会」で決定される。同族会はのちに法人化され、1909年に「三井合名会社」(三井本社)に衣替えするが、出資者は11家の戸主11人だけが社員のホールディング・カンパニーとして全事業を統括した。
オーナー一族は結束して財産を一括管理、運用し、マネジメントは専門経営者を抜擢して委ね、利益はオーナー各家で応分の配当金として受け取る。資産を運用、投資するオーナー一族と、外部から能力本位で抜擢された経営プロのコンビネーションが旧三井の強みであった。
あくまで旧時代の“閉鎖された企業所有”方式における運用原則だったが、この三井システムは、時代の変化に対して柔軟に寄り添う永続的な企業運営を可能にしたのだった。
(書き手)宇惠一郎 ueichi@nifty.com
※参考文献
『日本の15大財閥 現代企業のルーツをひもとく』菊地浩之著 平凡社新書
『三井財閥の人びと 家族と経営者』安岡重明編著 同文館出版
三井広報委員会ホームページ