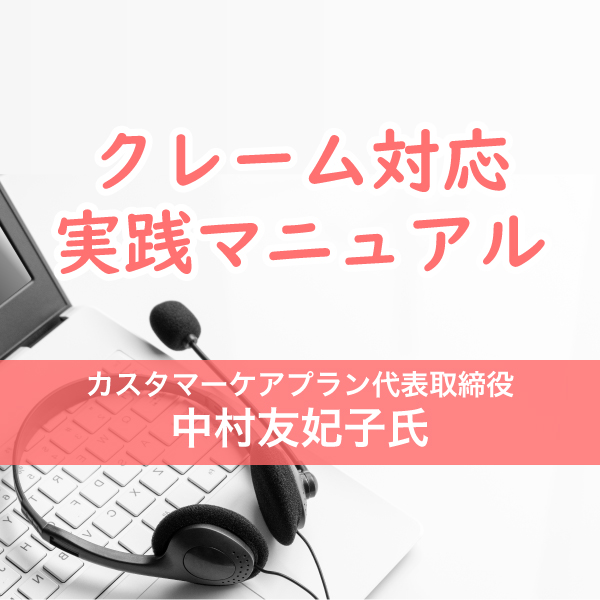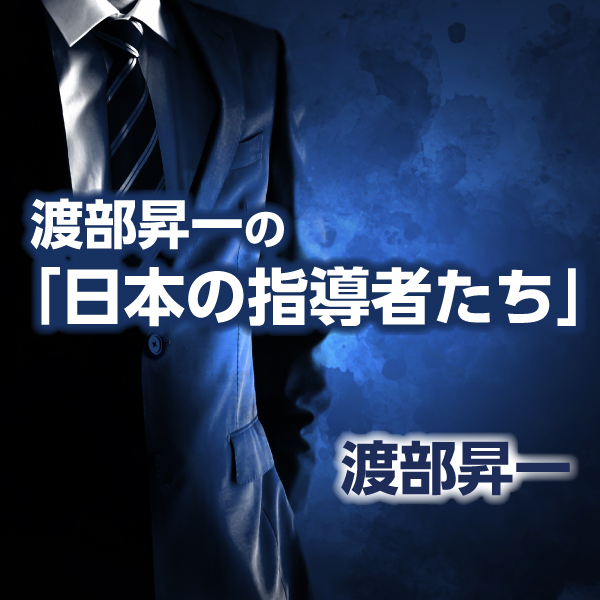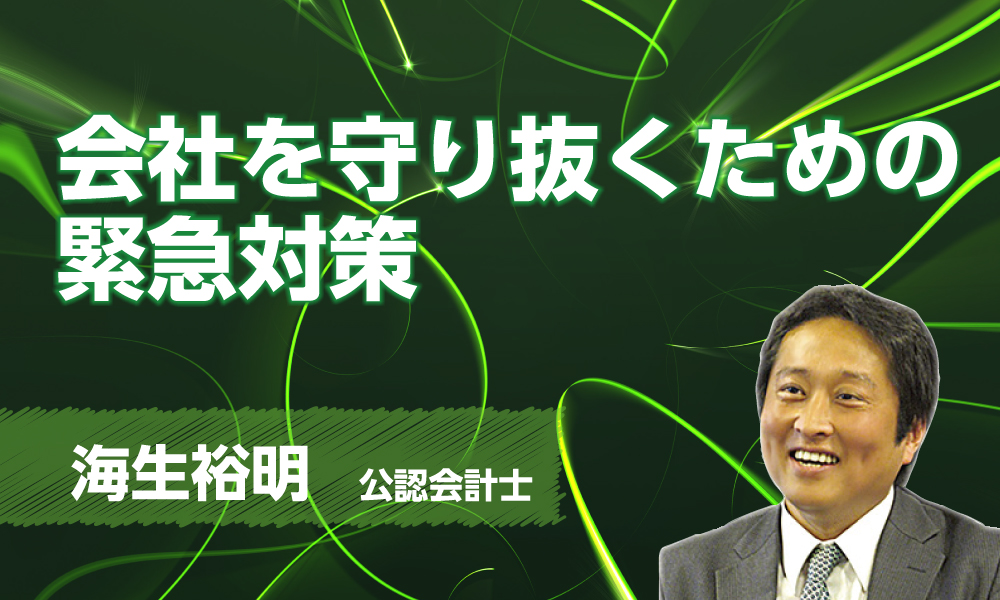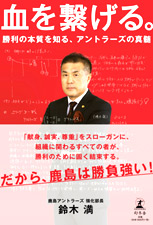昭和期に活躍した俳人・中村草田男(なかむら・くさたお、1901~1983)の代表作の一句「降る雪や明治は遠くなりにけり」。草田男がこの句を詠んだのは昭和6(1931)年、30歳の折で、「明治」が終わって約20年後のことだ。
今の人口比率では、「昭和」「平成」「令和」と三つの時代を生きている方が圧倒的に多い。テレビなどで懐かしい風景が若いタレントなどに「昭和っぽい!」と言われるが、日本で一番長い元号「昭和」がその幕を閉じたのは1989年、31年前のことになる。時あたかも「バブル経済」の終焉に近く、今の感覚では信じられないような事態が数多く起きていたと同時に、エネルギーに満ちていた時期でもあった。しかし、泡沫(うたかた)のように消えた「泡」は、のちの日本経済に大きな爪痕を残すことになった。
もはや戦後生まれが圧倒的な比率を占める昨今、いたずらに昔を偲ぶつもりはない。言葉をはじめ考え方や行動が、時代と共に変容するのは歴史の宿命に他ならない。その中で、今までにも折に触れ「温故知新」の大切さに触れてきたが、先人の知恵は豊かな財産である。
間もなく「令和三年」を迎えようとしている今、昭和元(1926)年生まれの方は94歳になる。戦地へ召集されたかどうかは別に、「戦争」体験者だ。こうした貴重な経験や「記憶」をお持ちの方々がどんどん少なくなり、曖昧なまま、あるいは何も語られぬままに歴史の彼方に消えてゆく。
ことは戦争に限らない。64年という長い期間の中で、「昭和20年8月15日」を境に、物の考え方は大きく変化を遂げた。昭和6年生まれの映画監督の篠田正浩氏は、「私は『軍国少年』として、敗戦までは『国のためにいかに死ぬか』を教わった。敗戦後は『いかに生きるかを教わった』と語った。終戦当時14歳だった篠田氏の体験は、その後の思考に大きく影響を与えていることは想像に難くない。
こうした「生きた談話」が聞けなくなるのは、残念ながらそう遠い話ではないだろう。後6年で、昭和元年生まれの方は100寿を迎える。戦争体験だけではなく、90年以上にわたる人生の経験で得た「智慧」は、単なる「知識」ではなく、それを活かし実践した経験からくるものだ。豊かで深い、時に哀しみや苦しみを伴う先人の経験を、単なる「むかし話」や「懐古譚」と片付けてしまうのはあまりにももったいない話だ。
幾つからを「老人」と呼ぶかは意見の分かれるところだが、最近は、老人を敬い尊ぶ気持ち、敬われるような振る舞いをする老人、共に少なくなっているような気がする。「暴走老人」という、耳障りの悪い言葉も生まれる一方で、遡って考えれば、敬老や労わりの気持ちを持っていらば、電車に「シルバーシート」をあえて設置する必要もなかっただろう。
昭和の高度成長期を必死で牽引し、支えてきた年代の人々の体験に基づく話の中には、今のビジネスに活かせる話題やきっかけが豊富にあるはずだ。後は、それを引き出し、現在のビジネスに活かす発想を持ち、実践に移せるかどうか、だろう。無常に時が流れるのは誰の身にも同じで、日々の仕事に忙殺されている間に「昭和」もどんどん遠くなる。
意外にも、昭和を知らない世代の若年層は、感覚的な部分で昭和が持っていた豊かさや優しさ、幅の広さや厚みなどを感じ取り、そこにシンパシーを感じているのかもしれない。もちろん、すべてがバラ色の時代だったわけではないが、学ぶべき点が少なからずあるのは事実だ。
同じ昭和生まれでも「何年代」に生まれたかにより、眼にした光景は大きく変わる。私は昭和37年の生まれだが、40年代はじめに、今もある新宿駅の東口と西口をつなぐトンネルの入り口に「傷痍軍人」の姿を見かけことは少なからずある。子供にはその意味はわからなかったが、後年、戦後20年以上経っても癒えない傷跡があることを知った。それは、戦後75年を経た今もなお、数は少なくなりつつも厳然と残っている。
学校教育から抜け落ちている近・現代史から学ぶべきことは実に多く、無闇に歴史上の出来事の年号を暗記するよりも遥かに「生きた」学問だと言えよう。今や、日本とアメリカが戦争をしたことを知らない、習わない大学生も存在する冗談のような時代だが、それを一律に断罪することはできず、嘆いてばかりもいられない。
ただ、組織のトップ、あるいは多くの人々をまとめるべき立場にいる方々は、改めて「昭和」がどんな時代だったのかに想いを致し、歴史的事実や流れを俯瞰的な視野で眺めた上で、若い人々に教える「義務」がある、とも思う。
古臭い繰り言だと批判をされるのは構わない。しかし、学び得るものの大きさを考えれば、そんな言葉は一向に気にならない。むしろ、自分に新しい「眼」を開かせてくれる機会があることに遅蒔きながら気付いたことに感謝したいとも考えている。そんな感覚で過ぎ去った「昭和」を考えることができるのは、昭和生まれの特権ではないだろうか。過去の膨大な事象の数々は、歴史の中で沈黙を守っているが、こちらが気付き、近寄って教えを乞えば、重い口を開いて我々が知らなかった「事実」や「真実」を語ってくれるはずだ。しかし、それができる時間はもはや数えるのも怖いほどに短い。
その中で、鳥のように高い視点から、若い世代に何を伝えるべきなのか。昭和生まれに課せられた宿題は大きく、重い。