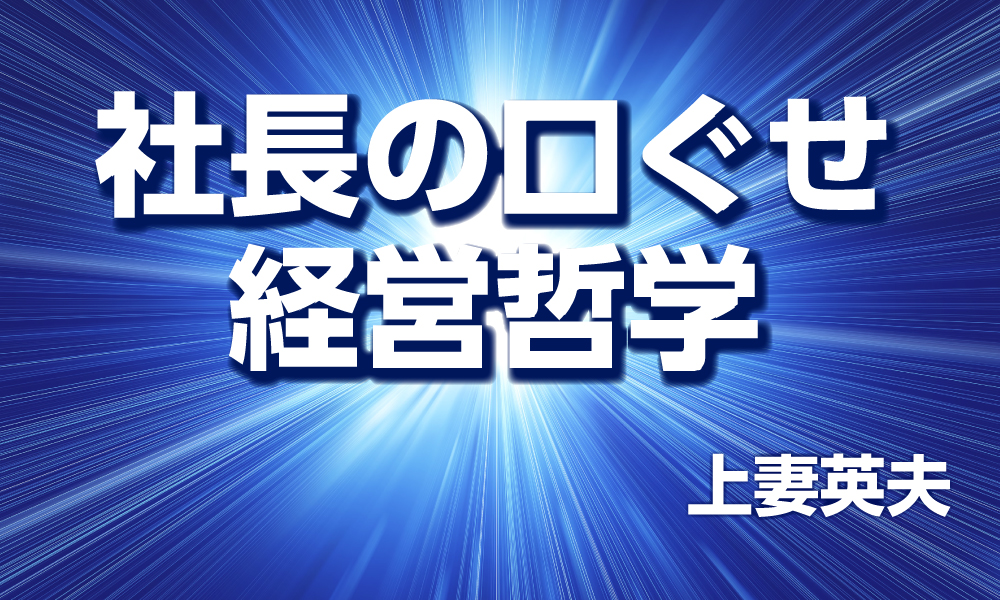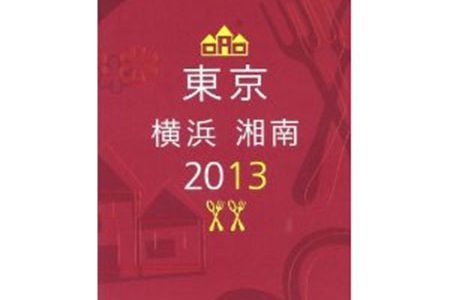ある程度の年齢になると、「自分のルーツはどこにあるのだろうか」と知りたくなるケースも多いようだ。私が自分で意識し出したのは60歳前後ではなかったろうか。調査の方法などによって、ある程度の金額はかかるが、辿れるだけ遡り、立派な巻物に仕立ててくれる業者も多い。個人でもできない仕事ではないが、それ相応の知識に加え、あちこちへ戸籍を取りに行く手間も経費もかかる。そこまではできなくとも、自分がどのような一族のどこの場所に位置しているのかは知りたいと思うことがある。
日本で一番古い家系図を持つのは、言うまでもなく天皇家だ。初代の神武天皇(紀元前660年2月11日即位)以来、今上天皇まで126代の歴史を重ねている。2600年を超える家系を連ねている王朝(海外から見ればこの表現になる)は、世界でも天皇家だけだ。
* * *
日本人の多くは、その源流を辿ると「源平藤橘」のいずれかにたどり着く、と言われている。源氏、平氏、藤原、橘だ。ただ、仮に「源氏の末裔」と言っても直接に源頼朝や義経に繋がるわけではなく、仕えていて名字を賜ったなどの場合も多く含まれる。また、「源氏」と言っても「清和源氏」「村上源氏」「宇多源氏」など、二十一に及ぶ「源氏」が存在する。更には、その「源氏」の中に、多いものでは10以上の「名字」を持つ一族があり、これらをすべて合わせると相当な数に上る。
鎌倉期に発生した武士であれば、どこかへ仕える時には、自分がどういう氏素性の末裔にいるかを記した家系図は必須だ。就職する時に履歴書が必要になるのとほとんど意味は変わっていない。唯一の違いは、自分がいかに立派な出自であるかを示すための「経歴詐称」が半ば公然と許されていたことぐらいだろうか。
現在の感覚ではとんでもない話だが、これはあくまでも現代の感覚でしかない。今のように法的に個人情報の概念もない時代のこと、過去へ遡って「系図の創作」を行い、かつての公家や名家の一族と結び付けることが悪いとの意識はない。多くの人々が当然のようにしていたことで、責めるには至らないだろう。
江戸時代も半ばになると、武士だけではなく、富裕な商人や農民などの家系図が盛んに作成されるようになった。こちらの場合は、婚姻の時の「釣り書」などにも使われた。相手がどういう一族の出で、どれほどの財産を持っているかなどを記した「釣り書」は、昭和期までは使われていたが、今は個人情報保護法違反になるのだろうか。個人よりも家の釣り合いを重視したため、系図だけではなく、財産まで記さないと成立しない。これは、結婚がいかに「家」の結び付きを重視されていたかを示す材料でもある。
* * *
「氏素性」との言葉があるが、一般庶民が「名字」を持つようになったのは江戸期ではなく明治に入ってからの話だ。もちろん、先に述べたように、家系図を残すほどの地位や、富を持っている人は別だが、多くの人には正式な名字はなかった。せいぜいが住んでいる場所や、その家の商売の屋号などを代わりに用いていた程度で、家のそばに柿の木があれば「柿の木の五郎兵衛」だろうし、「駿河屋」の長男であれば「駿河屋の太郎助」だろう。これは、言うまでもなく正式な名字ではない。
明治3(1870)年、明治政府から「平民苗字」が許可され、5年後の8年には「平民苗字必称義務令」が発令され、この時点で日本人全員が名字を持つことになったのだ。我々一般庶民が名字を名乗るようになってから、まだ150年ほどなのだ。
* * *
こうした要素が時代と共に変化を見せ、家系図の内容も充実してきたが、昨今シビアな問題となっている少子化で、一人っ子も多い。また、経済的な環境の影響もあり、未婚、あるいはパートナーがいても籍を入れない場合もある。
ある調査によれば、もう100年もすると「いとこ」、つまり兄弟や姉妹の子供同士という関係性はほぼ絶滅するという意見もある。確かに、一人っ子では「いとこ」は存在し得ない。また、少子化で子供がいない家も多く、家系が途絶えるケースも増えるだろう。これは、善悪で判断する問題ではなく、日本が織り成す歴史の一つ、と考えるべきだろう。「家」の概念が薄れ、我が家の家紋や菩提寺の感覚が希薄な今、少子化だけを責めるには当たらない。私事にわたって恐縮だが、かくいう私が子供を持たず、私の系図は、ここで終わり、ということになる。それはそれで何となく寂しいものでもある。
* * *
家系図は、自分を基点に過去へ遡る旅でもある。樹形図のように、遡るほど広がりは大きくなるが、自分から先のことはこれからの歴史であり、どうなるかは誰にもわからない。
「自分」を基点に考えた時、両親がいる。祖父母は親の親であり、自分より二代遡っただけで、親が2人、祖父母が4人、最低でも6人の先祖がいる。一代遡るごとに倍々ゲームで増える計算だ。その中の誰か一人が欠けていたら、自分が存在していなかったことになる。先祖というものは有り難いとの想いもあるが、不思議な縁の連続で自分が今ここにいることの方に不思議を感じる、と言えばご先祖様にお叱りを蒙るだろうか。