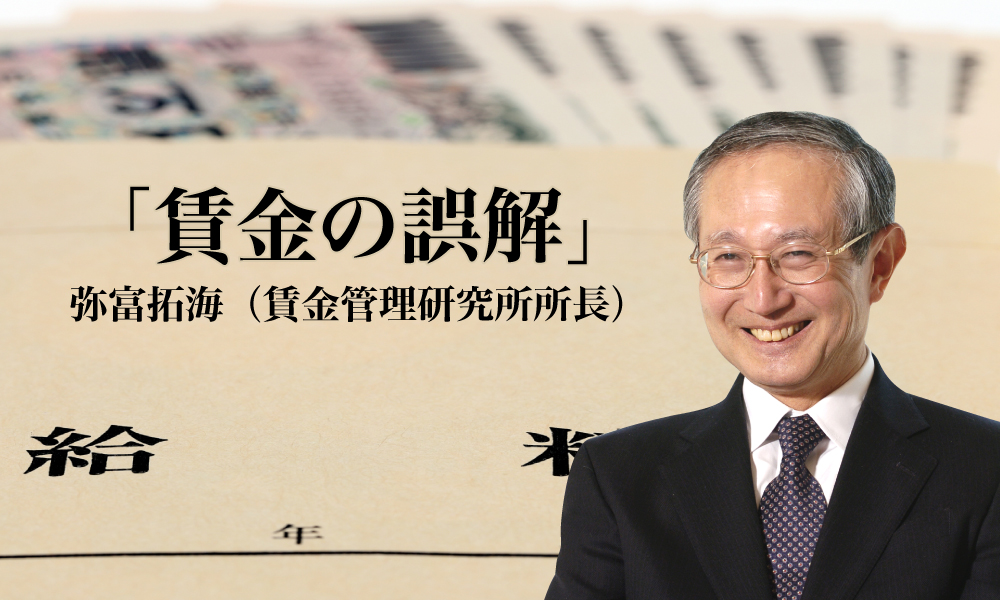我々は、「学校」という教育機関でさまざまな学問分野を学んできた。それが身に付き、今も役立っているかどうかはともかく、一通りの入り口だけは覗いたような気がする。
学校で教わる学問は、その道の専門の研究者の知識を時にシャワーのように浴び、そのうちのどれほどが理解できるか、あるいは共鳴できるかなどで興味の持ち方が違う。
しかし、どの場合も我々が「受動的」な立場であるのは間違いがない。
数は少ないが、知識に関係なく自らが能動的に行える学問もある。「読書」はその代表だが、場合によっては「知識を得る」段階で終わることもある。もちろん、これは素晴らしいことだ。
次のステップの「考え」、「問い学ぶ」学問。その代表が『哲学』だろう。とは言え、大学の専攻と会社の業務内容との関係を重視する企業もあり、イメージ先行で「潰しが効かない」と思われたり、
学生自身の興味や指向の問題で『哲学』や『思想史』、『海外文学』などの学科が受験生が集まらなくなり、各大学から姿を消しているのは何とも寂しい限りだ。
噺家の立川談志が「学問は貧乏人の暇潰し」と語ったが、これは談志流の諧謔であろう。自らが落語のみにとどまらない広範な知識に裏打ちされた
「芸」を持っていたからこそ、こうしたことが言えたのだ。
我々が日々の生活を送る中で、意識無意識に関わらず、ふと頭を持ち上げていつの間にか実践しているのが『哲学』だ。その際に、ソクラテス、プラトン、デカルト、カント、
ショーペンハウアーなど、名だたる哲学者の著作を読んでから臨むわけではない。一口に言えば、「何かの問題について考える」ことがすでに『哲学』なのだ。現在、自分が
置かれている状況、過去の経験、先の予想などを踏まえて、ある問題について想いを致すことは立派な『哲学』である。
ビジネスの世界には「経営哲学」との言葉があり、生活には「人生哲学」がある。比較的目にする機会が多いはずなのに、もう一歩踏み込んでその内容を
考えることは少ないとも言える。決して難しい話ではない。もちろん、洋の東西の名だたる哲学書を読破し、そこから自分なりの考えを導き出す「正面玄関」からの
方法を取れば、歯ごたえどころではない大仕事になる。しかし、そうした形ばかりではなく、気軽に行える学問でもあるのが哲学の魅力ではないだろうか。
『哲学』が面白いのは、能動的なだけではない。数学において「1+1=2」という数式は、時間を経ても新しい解答が見付からない。対照的に、同じ問題でも
考えるタイミングや年代により、出てくる解答が違い、どれが「正解」とは言えない一方、どれも「正解」とも言える。また、一人静かに瞑目しながらもできれば、食事や
酒席で互いの考えを語り合い、披歴するのも立派な『哲学』だ。しかもその折に、専門分野の参考書を持たずに、自分の人生経験を基に考えることができる。見方を考えれば、
時も所も相手も選ばない、もっとも「手近な学問」とも言える。
ただ、「手近」と「簡単」とは違う。何度考えても答えが見つからない命題もある。例えば、「人は何のために生きるのか」。「働くために生きる」「生きるために働く」。
この命題一つでさえ、永遠に結論の出ない「タマゴとニワトリ」のようなものだ。しかし、この問題とて無理に答えを出す必要はない。永遠に答えが出ない問題がもあるのも
『哲学』の面白みかもしれない。
これは私見だが、『哲学をする』ためには、小難しい知識や理屈は必要ないと考えている。折々の自分との「対話」や、社会の中での役割、果たすべき任務を
考えるだけでも充分な『哲学』だ。考える行為そのものであり、専門的な領域とは少し違った部分で、我々は考え、『哲学』をしながら生きているのだ。
ビジネス・リーダーにはそれぞれの「経営哲学」があるはずだ。曰く「人を大切に」「曰く「誠意を持って」曰く「社会のために」などなど…。こうした言葉は、額に入れて
飾っておいても意味はない。実践して初めて生きた学問となり、その動きを見せる。「生きて動かす」ことにこの学問の面白みと意味がある。難しい書物を繙くことも時には
必要だが、自らの生き方や振る舞いが反映されるのも哲学の魅力でもあり、怖いところでもある。こういう学問は他の分野ではあまり目にすることがない。
だからこそ、哲学は「する」学問なのだ。
「実学」という言葉があるが、哲学は実学の最たるものとも言えるだろう。パスカルの「人間は考える葦である」との名言は多様な解釈ができそうだが、「考える」ことの
素晴らしさを改めて教えてくれる。机上で本を繙くのも悪くはないが、「タイム・イズ・マネー」のスピード感にいささかの疲れを感じた時、ふと立ち止まって来し方行く末に
想いを致し、「哲学」をすれば辺りの光景も違って見えることもある。
牽強付会と言われそうだが、いかようにも解釈が可能な芭蕉の「古池や蛙飛び込む水の音」の句は、哲学的俳句の最たるものかもしれない。