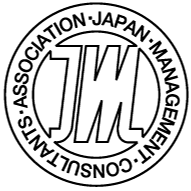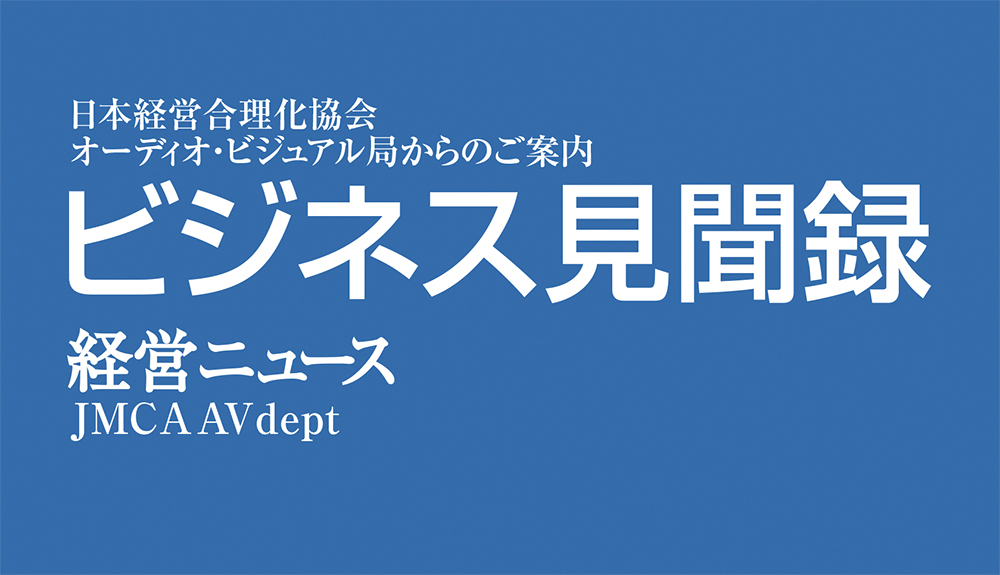人材はコストではなく資本。2023年3月期以降の有価証券報告書から、「人的資本に関する情報」を開示することが義務づけられ、「人材育成方針」「社内環境整備方針」「両方針の指標・目標」「女性管理職比率」「男性育休取得率」「男女間賃金格差」の6項目が記載されるようになり、大きな話題になりました。 一方、国際標準化機構(ISO)は、人的資本情報開示の国際規格「ISO 30414」を発表。米国証券取引委員会などでも人的資本の情報開示が進んでいます。どうして世界的に人的資本の開示が広がっているのでしょうか。そもそも人的資本経営とは、どんな経営なのでしょうか。人事の現場もよく知るルヴィアコンサルティング株式会社 共同経営者/COO 岡田幸士さんに伺いました。
一方、国際標準化機構(ISO)は、人的資本情報開示の国際規格「ISO 30414」を発表。米国証券取引委員会などでも人的資本の情報開示が進んでいます。どうして世界的に人的資本の開示が広がっているのでしょうか。そもそも人的資本経営とは、どんな経営なのでしょうか。人事の現場もよく知るルヴィアコンサルティング株式会社 共同経営者/COO 岡田幸士さんに伺いました。
戦略的な領域で活躍できる人事を増やしたい
――昨年、出版されたご著書、『図解 人的資本経営』は、すでに6刷と大ヒットしていますが、どのようなきっかけで執筆しようと思われたのですか。
主なきっかけは二つあります。一つは、人事部門のコンサルティングをしていく中で、人事部門には、コンサルティング会社のサポートが無くても戦略的な領域で企画ができるようになって欲しいと考えるようになったことです。
私はマクドナルドの人事部から社会人のスタートを切りましたが、人事部門の仕事は、給与計算のようなミスを犯したら大変なことになるような重大なルーティーン業務の繰り返しです。そうした業務をしながら、戦略的な発想を生み出すことは難しい。
だから、人事制度や人事業務の改善、人事組織の変革など、組織の根幹にかかわるようなことをコンサルティング会社に丸投げすることになる。すべてをお任せいただくのは、コンサルティング会社にとってはありがたい話ですが、人事部にとって本当にそれでいいのでしょうか。人事部が会社を良くするための戦略的な企画をたてる力。それを身につければ世の中の会社がもっと元気になるのではないかと思ったのです。
――確かに。会社の根幹でもある人事や教育などをコンサルティング会社に全部任せてしまうのは不自然ですね。それで問いに答えながら、自社の人的資本経営とは何かを考えさせるという形式の本にしたのですね。二つ目のきっかけは何ですか。
独立して中堅、中小企業のコンサルティングをするようになったことです。これまでデロイトで付き合っていた大企業中心のクライアントとの情報量や人材などの格差にあらためて愕然としました。
それは、ある程度、仕方がないとしても、「このツールを知っていれば」「このフレームワークの考え方を少しでも知っていれば」、もっと会社がよくなる。そうした部分がものすごくありました。
しかし、多くの中堅・中小企業は、コンサルティングにそんなにお金をかける余裕もない。どうしようかと思っていたその頃、20年くらい前に登場した「人的資本経営」という言葉が流行しはじめたんです。
――『人的資本経営』と岡田さんのキャリアが結びつくわけですね。
もっとも「人的資本経営」に対する反応は、中小企業なら「どうせ大企業向けの話でしょ」、大企業なら「他社の事例や先進的事例を知りたい」といったものばかり。
人的資本経営は中小企業においても必要なのですが、他社のやり方を真似してもあまりうまくいかないことがほとんどです。
結局は自分たちの会社のことをよく知って、考えるということが何よりも大切ですので、何とかそういう方向に導けないかと思ったことがもう一つのきっかけです。
――50の問いが用意されていますが。
それは、いずれも人的資本経営を実践していくために考えておくべきテーマです。単に問いを並べるのではなく、問いに答えるための考え方や事例なども紹介しています。
たとえば、書籍の中で「人材のパフォーマンスをどのように高めるか」という問いを設定していますが、その問いに対する答えを考えられるように、「そもそも個人のパフォーマンスはどうやって決まるのか」「パフォーマンスを決める要素」「個人のパフォーマンスを高める観点」「やりぬく力を伸ばす方法」など、個人のパフォーマンスに関する基本的な考え方をコンパクトに紹介しています。
それを理解し、自社にあてはめて考えていくことで、それぞれの会社にとって理想の組織を実現できるという仕組みです。
1
2