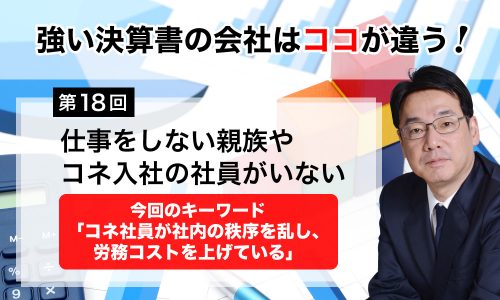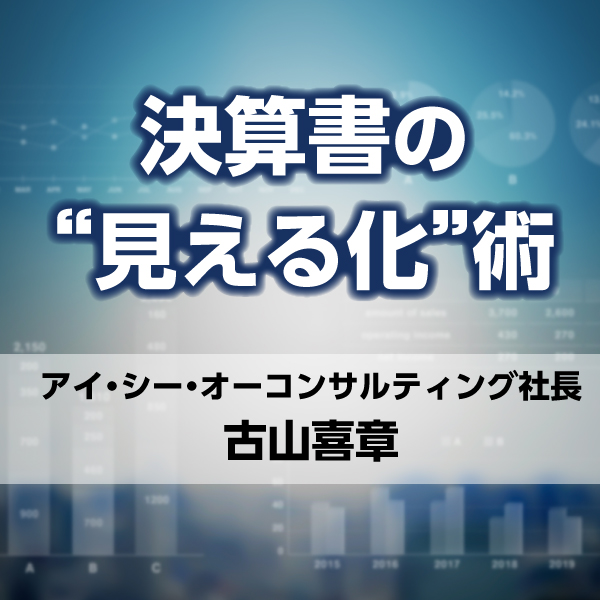「雪の日に雪のせりふを口ずさむ」。俳句をよくした昭和初期の歌舞伎の名優・初代中村吉右衛門(1886~1954)の句だ。
三月ともなれば、関東圏では山間部でない限りは雪の話はもう終わりだが、南北に長い日本列島では五月の連休までスキーができるほどの雪が残る地域もある。加えて、気候変動の幅が激しい昨今、ふだんはそれほど降らない場所に突然大雪が降り、大渋滞を起こしている様子がニュースで写されたりもする。
我々は、すぐに映像などでその状況を把握することはできても、雪国の感覚を共有することはできない。東京近辺で10センチの積雪で転倒者が続出し、怪我人が数10名出たというニュースに、雪国の人は「あれあれ」と我々の雪に対する無防備な生活を笑うかもしれない。その一方で、一晩で1メートルに近い積雪が当たり前の豪雪地帯の冬の生活が、どれほどに過酷なものかを感覚として共有することはできない。
今は、屋根を電気やガスの力で暖め、雪が積もらないように溶かしてしまう「融雪屋根」が広まってはいるが、昔ながらの構造で雪下ろしをしなくてはならない家も依然として多い。水気を含んだ雪は重く、50センチ程度の立方体でも「これほどか」と思うほどだ。慣れない私などは、30分もすれば身体中が悲鳴を上げるが、雪国の人は当然のように黙々と手際よく片付けてしまうし、そうでなくては仕事にならない。
「風景は旅人が発見する」との言葉があるが、我々が雪景色を美しいと思えるのは、通り過ぎる旅人が目にする風景だからで、そこに生活する人々には、冬は雪との闘いである。呑気に「綺麗だね」とは言っていられない。
* * *
200年近く前、今よりも格段に情報伝達の手段が劣っていた時代に、この感覚の差を埋めることは容易ではなかった。それどころか、我々の想像を上回るほどに理解の差があっただろう。
今も豪雪地帯である代わりに、その清らかな水で銘柄米「コシヒカリ」や銘酒「八海山」の産地としても知られる新潟県・魚沼。ここで、名産の越後縮の仲買をしていたのが鈴木牧之(1770~1842)だ。仕事柄、江戸との行き来も多く、客先などで冬の越後の様子を話すものの、誰もまともには受け取らない。「いくら何でも、そんな話があるもんけぇ」という調子だったのだろう。
今と違って江戸湾が開け、風でも雪でも埃でも、赤城おろしの風ですぐに海へ飛ばされる「吹きっさらし」の地形が、当時の江戸の特徴の一つでもあった。そういう人々に、「ある年の冬の雪が、解けずにそのまま積み上がったとすると、高さは18丈(54メートル)にもなる」といくら真剣に説いたところで、信用はされないだろう。今、私がこのエッセイを書くために調べても、俄かに信用しがたい数字だ。
* * *
いくら言葉を費やしても理解されない感覚の余りの乖離に業を煮やした鈴木は、28歳の時に冬の雪国の様子を克明に伝えた本の出版を思い立った。ナイス・アイディアではあるものの、出版自体が今ほど容易ではなく、幼少から書画の嗜みはあっても、文章を書く仕事をしているわけではない。当時、江戸で名が売れていた戯作者の山東京山(1769~1858)などの助力を仰ぎ、アドバイスをもらうものの、何度も計画は頓挫した。
しかし、雪国の人の粘り強さも手伝ってか、冬の雪国の生活を食、風景、伝説、地形、方言、雪にまつわる道具まで、あらゆる分野にわたって述べた『北越雪譜』が完成した。この時、鈴木は67歳、何と、発想を得てから40年近い歳月が経っていた。
しかし、雪が積もらない地域の人にとっては嘘のような本当の話が満載で、それが話題となり、ベストセラーになったという。もっとも、当時の出版事情から言えば、1,000部近く売れれば大ベストセラーで、700部ほど売れたとの記述もある。何部売れたかはともかくも、ほとんど情報がない時代に、同じ日本でありながら信じられないような生活を伝えた書物は、さながら「雪国博物誌」とも言える貴重さをも備えることになった。現在でも、岩波文庫で手軽に読めることからも、その価値が重視されていたことがわかる。
* * *
同じ日本人だからと言って、すべての感覚を共有する必要はない。しかし、これほど情報網が発達し、多くの手段を持つようになった今でも、200年前と変わらない感覚がある、というのが面白くも感じる。「季節感」と一口に言うが、人により感じ方が違うのは当然だ。それも、極端になると話題としての興味も増す。
多くの記録を塗り替えるほどの猛暑だった夏、京都の外国人観光客が減った、という話を聞いた。それもドバイやインドネシアなど、温暖との言葉を超え、気温も日本より高い地域の人が減ったそうだ。その理由は、「暑いのはまだ我慢できるが、この蒸し暑さは異常だ。まだ、自分の国の暑さの方がマシ」という理由だったとか。
暑さに対する感覚は比較的共有できるようだが、寒さやそれに伴う雪などの感覚は、どうも難しそうだ。2018年に「世界演劇フェスティバル」で招かれたカザフスタン共和国の首都・アスタナの冬は、-40度にも達すると言う。世界で最も寒い首都だそうだが、その感覚は私には想像も付かない。
そうした観点から、日本列島を眺めてみるのもまた一興、かもしれない。