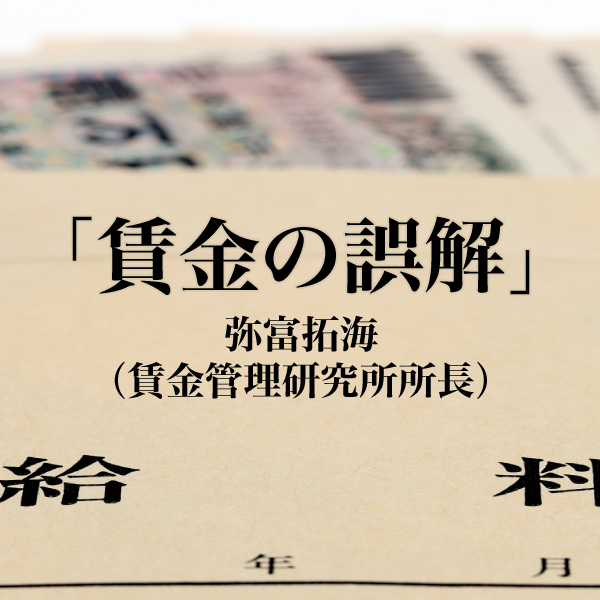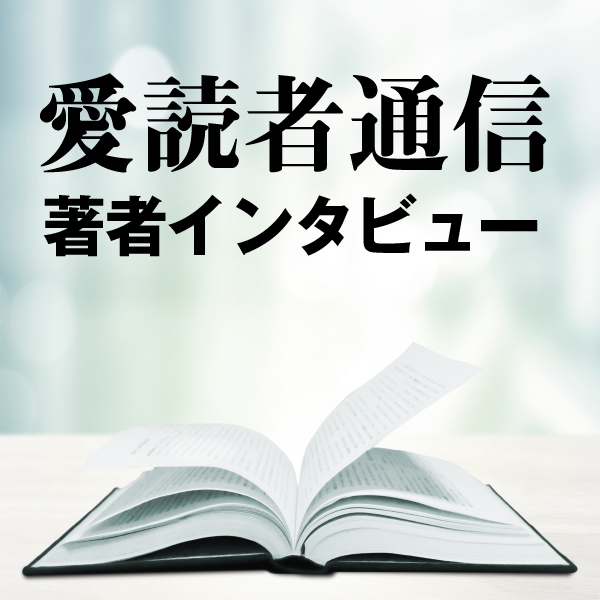我々日本人が、こと宗教に関しては柔軟性が高く、場合によっては「いい加減」ないしは「あまりに多くのものが混在し、本質が見えない」などの指摘を海外からされることはしばしばあるケースだ。
お国柄により、信仰の対象や厳しさはさまざまで、中でも日本は最も鷹揚な国であると言える。島国という立地、限られた面積の中で、多くの宗教を受け入れてきた歴史は古い。加えて、それらの信仰が「共存」できるような「神仏習合」、つまり「神と仏は一緒」という素晴らしい発想を持った先人の智慧には感嘆せざるを得ない。
当然、そうした事態が当たり前になるまで、あるいはそれ以降に、何のトラブルもなかったわけではない。「信仰」は民族や思想を反映する鏡の中でも大きな力を持ったもので、いくら柔軟な国とは言え、そのぶつかり合いは数知れず行われて来た歴史がある。動機や詳細はともかく、織田信長は石山本願寺を焼き討ちにした。近いところでは長崎県の「隠れキリシタン」が「世界遺産」に認定された。多くの艱難辛苦を乗り越えて今に至るまでに、同じ信仰心を持ちながらも認定されなかったケースもあり、その矛盾が論議を呼んだのは記憶に新しい。
ビジネスシーンにおいて、「政治と宗教の話は禁物」とも言われる。お互いの思想、信仰について対話を交わし、意見が一致すればよいが、噛み合わなかった場合は平行線をたどるばかりで、発展がなく、関係性は悪くなる。こうした話題をビジネスの場に持ち出さないのは言わば「大人の常識」だ。
その一方、この多様な信仰心を持つ日本人の「精神性」は、海外からは不思議でならない部分も多く、分かりやすく「こういう考えに基づいているのだ」と説明する程度の知識は欲しいものだ。
クリスマスを祝った一週間後には寺院へ除夜の鐘を突きに出かけ、翌朝には神社へ初詣をする。また、秋のハロウィーンも盛んになって久しいが、日本ではその根源や本来の意味を知らずに「キリスト教の仮装パーティ」ぐらいに考え、騒ぐ人々がいるのも事実だ。表層の事実だけをとらえてみれば、日本人の信仰心は何といい加減なのかと思われても不思議はない。
しかし、日本には元来、固有の神々がおわしまし、仏教の流入とともに「仏様」が伝えられた。そして、混乱と対立を避ける智慧だろうか、「神仏習合」という見事な離れ業が取り入れられた。「神様に、仏様の役割も担っていただこう」という、人で言えば一人二役だ。神道の「天照大神」は仏教では「大日如来」として姿を現わしていただくという日本のローカルルールだ。これが日本人の体質に合ったのだろう。今でも急場の折に「神様仏様」と思わず一緒にしてしまうほど、我々の感覚に馴染んでいる。
さらに言えば、日本には「八百万の神々」がいるとされ、日常生活では神棚に祀られているだけではなく、台所やトイレにまでも神様がいる。唯一神、絶対神が大きな力と意味を持つ西洋の宗教に比べ、日本ではその権力を分散しているとの考え方ができるかもしれない。
そうした歳月を重ねてきた結果、日本人は神様をフレンドリーな存在として考えるような感覚を持ったのだ。キリスト教では信仰者と神の間には「契約」が交わされ、それを破ると業罰が待っている。日本にもこの考え方はあるものの、多くは「神頼み」という言葉に代表される神様への一方通行の「お願い」が多い。
これは民族性の問題であり、どちらが良い悪いではない。ただ、この根っ子をよく理解しておかないと、誰かに説明する折に焦点がぼやけた曖昧なものになってしまう。宗教によっては、神様とフレンドリーとの感覚さえすでに「罰当たり」かもしれない。しかし、この柔軟性は誇るべきところでもある。こうしたものだけではなく、仏教の中の「山伏修験道」では、まさに命を賭けた厳しい修行が行われることも忘れてはならないだろう。
近年、動物由来の食品を一切口にしない「ビーガン」と呼ばれる完全草食主義が盛んだ。その一方で、植物にも命があり、人間は生きとし生けるものの生命をいただかなければ生き延びることができないのだ、との考えもある。キリスト教の「原罪」にも似た感覚を仏教では「業」と表現することが多い。
70億を超える人々が生きる地球に、どれほどの宗教があるのか、もはや正確な数は把握のしようはないだろう。国内でも不可能なはずだ。
現世をよく生き、来世ではさらに恵まれたい、これは、今期の売り上げを増やし、来期はさらに…と願う会社と同じである。信仰者を社員と考えれば、同じような構造を持っているとみることも可能だ。これは牽強付会ではなく、リーダーが社員の多様な個性を把握・理解し、活かすためにはあながち的外れとも言えないだろう。現在の状況が混乱して見えたり、なぜそうなっているのか考えあぐねた折には、時間を遡って「根っ子」を探すこともまた、重要なのではないだろうか。物事が複雑になった場合は、謙虚な考えでシンプルに戻ることも必要なのではないか。