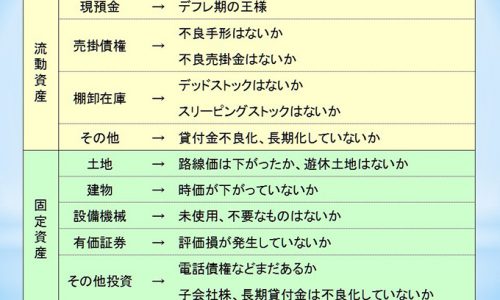どうも最近「ムダ」が多いような気がしてならない。「ムダ話」「ムダ遣い」まではよくあるものの、年齢のせいか「ムダな動き」も増えてきたようだ。暫く前に「余韻」をテーマにこのコラムを書いたが、「ムダ」と「余韻」では言葉の響きも内容も大きく違う。多くのムダを省いて効率的に変えるほどのエネルギーもなくなって来た昨今、この「ムダ」をどうすべきか、今の私の生活での大きな問題になりつつある。とは言いながらも、恐らく時間の経過と共にムダは増える一方なのだろう。
「無駄」。「駄」は「荷物」のことだから、「荷にもならない=役に立たない」の意かと思ったが、これは当て字だという。本来は「徒」の一文字で、「むだ」とも「いたずら」とも「あだ」とも読む。いずれにせよ、プラス思考の文字ではない。「むだ」と「いたずら」では、かなり趣が違って来るような気がするが古の人はどう使い分けていたのだろうか。同時に、「ムダ」にも有用と無用があり、私の場合は、編集者とムダ話に興じ、時にはアルコールが入ることもある。そこから、新たな企画が生まれることも少なくはない。となると、厳密に言えば仕事になった場合はアルコールの力を借りようが「打ち合わせ」であり、何も成果を得なかった場合は「ムダ」になるのだろうか。そうではない「ムダ話」の実例を一つご紹介しよう。
「履き道楽」とは言えないが、夏になると下駄を買い替えたくなる。柾目の通った桐の木は柔らかく、アスファルトの道だとすぐに減ってしまい、ガタガタになる。さりとて、チビた下駄を引きずるのも見っともなし、年に一度の贅沢で下駄を買いに馴染みの呉服屋へ出かけ、ムダ話に興じていたら、主人がこぼしていた。
最近は葬送儀礼も簡略化され、特に「コロナ禍」を挟んだために、疫学上の問題も加わり、「家族葬」などのこじんまりした送り方が増えた。しかし、会社関係の大きな葬儀はまだ残っている。ある会社に勤める若い女性が、会社お偉いさんの葬儀の手伝いを命じられ、「割烹着」を買いに来たそうだ。主はざっと女性の身体つきに目を走らせ、奥から二、三種類を持ち出して、「この辺りでいかがでしょう」と差し出したところ、お客の女性は困ったような顔をして暫く眺めた後、主人に、
「黒い割烹着はないんですか?」
と尋ねたと言う。
「えぇ。昔から割烹着は白と決まってますから」
「でも、お葬式の手伝いだし、お葬式ってみんな黒を着てますよね。…すみません、上司に相談して、また伺います」
と言って、店を去ったそうな。
主人は「まぁ、今の若い人には割烹着自体がもう馴染みがないですからね…」ひとしきりこぼした後、「でもね、この話には続きがあるんですよ」と言った。
このやり取りによほど納得が行かなかったのだろう、出入りの問屋に話したところ、問屋からは「今は黒い割烹着、ありますよ」と予想もしない返事があったそうだ。先の女性のような感覚の持ち主が増えており、あるメーカーが「洒落」で創ってみたところ、これが意外に売れ、もはや定番化しつつあるのだという。私は主人と若い女性のやり取りよりも、後半の話に驚いた。そして、文化やしきたりはこうして変わって行くのだ、との実感を覚えた。
現在、葬儀の場はほとんどが黒かダークな色合いの衣装に身を包んでおり、「白」を着ているのは故人だけだ。葬祭の場で黒白の「鯨幕」を見掛ける機会も激減した。しかし、「黒」が正式だ、とのイメージで葬送の場で黒が用いられるようになったのは明治維新以降のことだ。しかも、当初は貴顕の人々だけで、一般庶民にまで広まったのは大正期と言われている。事実、時代劇などで切腹の座に就く侍は、「死に装束」として全身を白の衣装で身を包んでいる。しかし、令和の世の中、通夜や葬儀に白い衣装で出かければ、間違いなく「常識知らず」と白眼視される。しかし、その「常識」が変わってから、わずか100年と少ししか経っていないのだ。
私が驚いたのは、我々の一般教養では、「死にまつわる物は黒」という常識が固定化していたことだ。内容は違うが、「霊柩車を見たら親指を隠さないと、親の死に目に会えなくなる」という俗信がある。これなども、モータリゼーションの発達で「霊柩車」が走り出す前には有り得なかった「常識」だ。更に言えば、固定化して100年経ったからと言って、もう変わらない保証がどこにもない。
困るのは、こういう「常識」の出どころが判然としていないことだ。今のようなネット社会では、さらに混沌としていることは言うまでもない。何十年かすれば、若い女性を無知だと笑うことはできなくなり、「過去の変な習慣にこだわり続けている」と笑われるのは私かもしれない。
このエピソードに限らず、我々が精神的な拠り所だと考えている「常識」とは、それほど危なっかしいものの上に立っているのだ、との現実を思わぬ形で認識しなくてはならないケースだ。これからは、良い意味で「常識を疑う」必要もあることを痛感した。新たな視点を与えてくれた呉服屋の主人の「ムダ話」は、こうしてムダにならずに済んだ。