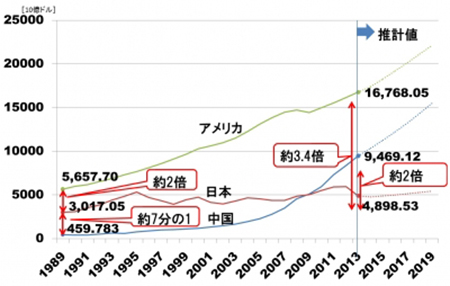堯舜禹(ぎょう・しゅん・う)の伝説
大唐帝国の第二代・太宗(たい・そう)は、人事の公平さがいかに大事かについて口を酸っぱくして側近たちに説いている。しかし、究極の人事である後継決定については心が揺れ、そして恵まれなかったことは、先に書いた通りである。
『貞観政要』の公平篇で、太宗が考える理想の人事について語る場面がある。太宗が天下を平定して皇帝に即位して程ないころ、側近の房玄齢(ぼう・げんれい)が、「旧来の功臣たちから、天下取りの功績に見合うポストにつけないという不満の声が出ています」と訴えたのに対する答弁である。そこで太宗は、古代の伝説上の聖王である堯(ぎょう)と舜(しゅん)の後継者選びに対する態度を引用している。
「昔の公平と称えられる為政者を考えてみると、人事に際して思いやりはあっても私情は挟まなかった」とした上で、伝説を引き、「黄帝の子の堯は嫡男の丹朱(たんしゅ)がいたがこれを廃し、舜に禅譲した。舜も子の商均(しょうきん)がいたが廃嫡して庶民あがりの禹(う)を後継に立てた」、と指摘した。そして太宗は言う。
「人を任用するには、ただその人が任務に堪えられるかどうかが問題なのであって、旧知のものであるかどうかに左右される必要はない」
太宗が、側近人事に関する話題であえて後継者選びの要諦に触れたのは、その後、自身の後継問題で不肖の息子たちに振り回されることを予見していたのか。いやそれよりも、貞観政要は太宗の徳を讃えるための書物であるから、著者の呉兢(ご・きょう)が、太宗への直接の批判を避けて、不肖の息子があらわれた場合に後継人事を差し替える決断の重要さを教訓としてそっと忍ばせて後代に伝えようとしたとみるのが妥当だろう。
〈後継は直系の嫡子から選ぶのが穏当だが、その子が後継に相応しくなければ、ためらうことなく、切れ〉
北条政子の嫡男切り
鎌倉幕府を開いた源頼朝の妻である北条政子(ほうじょう・まさこ)が、貞観政要を和訳させて読んだことは、連載の第一回で触れた。頼朝亡き後、「尼将軍」として幕府を取り仕切った政子だが、将軍の後継者に恵まれなかった。彼女が貞観政要から後継者問題について知恵を得ようとしたことは間違いないだろう。
政子は頼朝との間に二人の男子をもうけている。1199年に頼朝が急死すると、嫡子の頼家(よりいえ)が18歳で家督を継ぎ、やがて第二代の将軍職を継いだ。頼家は政治経験もなく、独断で専制的な政治を進めたため、関東の武士団の棟梁たち13人の合議制が取られ、政子が後見役となる。放映中の大河ドラマに見るとおりだ。
しかし、頼家は父に似て女ぐせが悪く、しかも政治をさぼって蹴鞠(けまり)に熱中し遊びほうける。周囲の意見も聞かず、十三人衆との溝も深まるばかりだ。まるで家業の経営を放り出してゴルフ三昧の若社長に見る振る舞いである。たまりかねた政子は、頼家を出家させ、伊豆修善寺に幽閉し(3年後に暗殺)、第三代将軍に次男の実朝(さねとも)を据える。その実朝も文学狂いで形だけの将軍だったが、やがて頼家の子、公暁(くぎょう)に暗殺される。これで頼朝の男系は途絶え、京都から公家の将軍を迎えて北条氏が執権として政治を動かす変則政権が幕府崩壊まで続くことになる。
貞観政要から教訓を学んだ男まさりの政子も、後継者問題という難題から抜け出すことはできなかった。
教育係の重要性
家族的経営体で最も安定的な後継体制は嫡子が後を継ぐルールを確立することである。その後継者に不安がある場合、選択は二つある。
一つは他に適材を求め禅譲することだ。先に触れた堯舜(ぎょう・しゅん)の政治である。そのために必要なことは、組織内の合意であろう。だがこれは往々にして組織の中に権力抗争を生む。誰もがトップに上り詰めるための「社内政治」に奔走するためだ。また、禅譲を決めた直前トップが後継者の組織運営に口を挟む危険もある。いわゆる院政の弊害だ。禅譲をルール化するなら、去ったトップの介入を制限するルールが必要だ。日本史を見ても中世の入り口で、皇室内で院政がまかり通り政治が歪んでゆくのは、直近天皇の介入制限のルールが形骸化したからだ。
さて、血族内の後継者の資質に不安がある場合の選択肢の二つめは、適切な教育係を置くこと、それに尽きる。
太宗は、理屈は説きながらもそれに失敗した。北条政子もそれを学びながらしくじった。「帝王学」とだれもが言葉ではいうが、不肖の息子にそれを身につけさせることは、それほどの難事なのだ。
心してかかるべし。
(書き手)宇惠一郎 ueichi@nifty.com
※参考文献
『貞観政要 全訳注』呉兢著 石見清裕訳注 講談社学術文庫
『貞観政要』呉兢著 守屋洋訳 ちくま学芸文庫