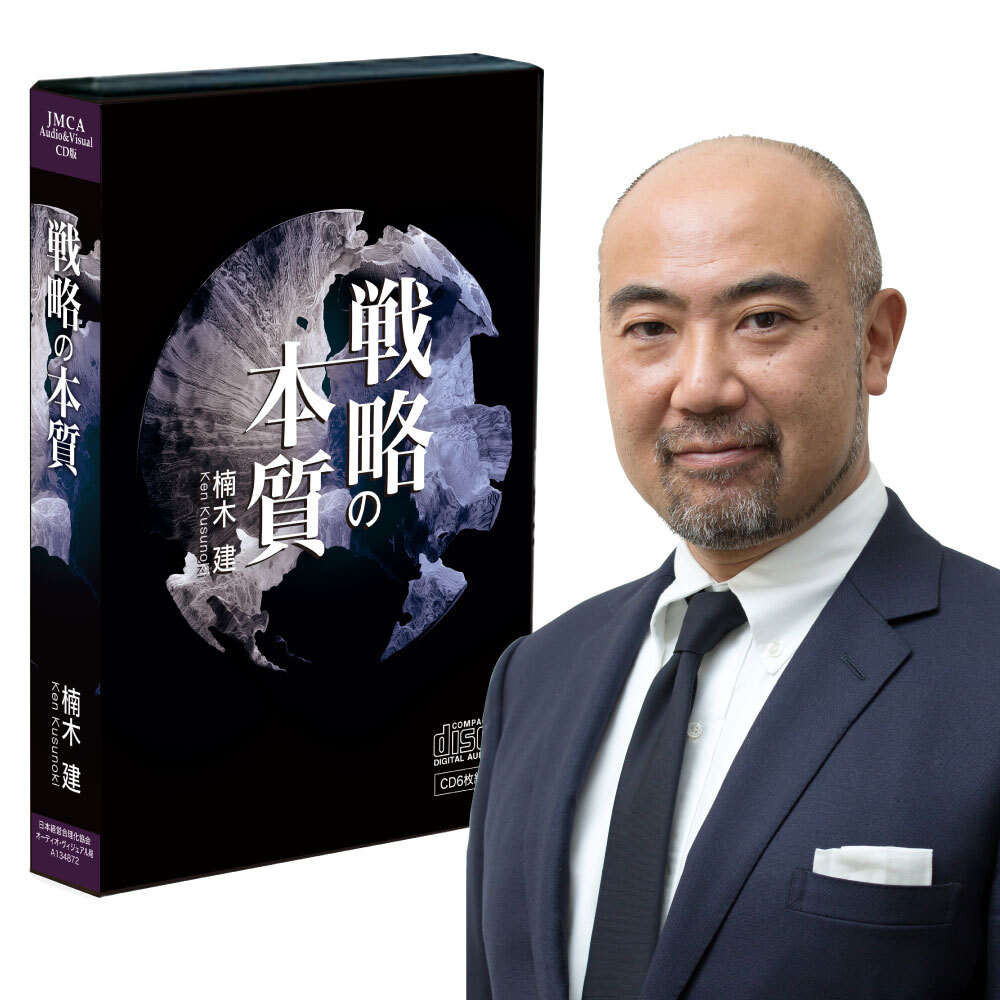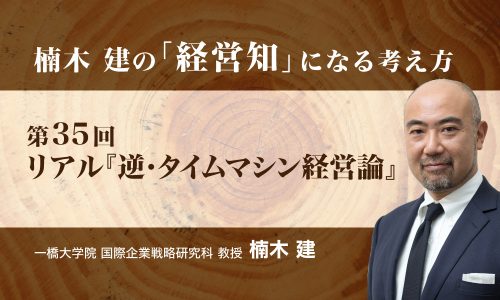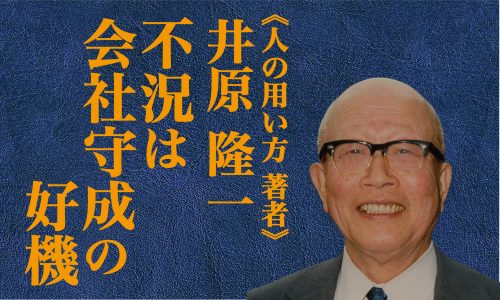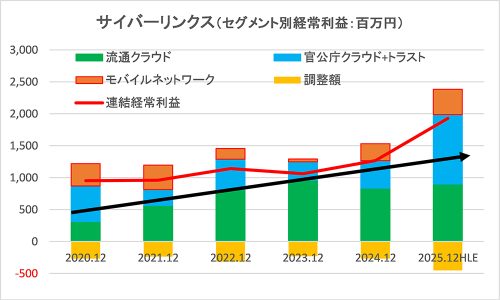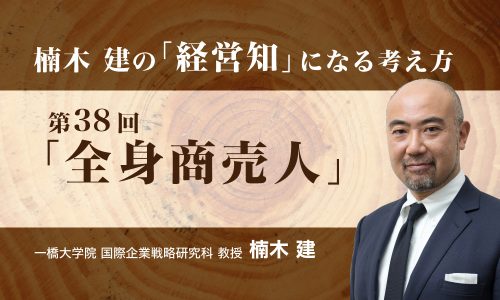「情けは人のためならず」は意外と奥深い
アダム・グラントという組織心理学者の書いた『GIVE & TAKE』という本を監訳したことがある。ようするに「情けは人のためならず」。ありきたりの話に聞こえる。ところが、これがなかなか奥深い。
議論の基底にあるのは、「ギバー(与える人)」「テイカー(もらう人)」「マッチャー(バランスをとる人)」という、人間の思考と行動の3類型だ。実にシンプルな分類だが、字面だけだと誤解する恐れがあるので要注意。
「ギバー」といっても「ひたすら他者に与えるだけ」ではない。同様に「テイカー」にしても「人から取ろうとするだけ」ではない。これでは世の中と折り合いがつかない。どのタイプでも最終的にはタイトルにある通り「ギブ&テイク」になることには変わりはない。いずれにしても人はギブしたりテイクしながら仕事をしている。世の中は「ギブ&テイク」で成り立っている。
しかし、ギバーとテイカーとマッチャーでは、「ギブ&テイク」に至る筋道がまるで異なる。本書の3分類は、「ギブ&テイク」という仕事の場面でごく日常的にみられる相互作用に対して人間が持つ前提の違いに焦点を当てている。
相手のためのギブを優先するか、自分のためのテイクを優先するか
3つのタイプの本質的な違いを理解するためには、それぞれのタイプの意図や行動を時間軸においてみるのがよい。ポイントは、ギブとテイクのどちらが先に来るかいうことだ。テイカーであったとしても、ギブすることも少なくない。しかし、テイカーが前提とする因果論理はこうなる。彼らにとっては、目的はあくまでも「テイク」にある。何でも自分中心に考え、自分の利益を得る手段としてのみ、相手に「ギブする」。裏を返せば、テイクという目的を達成する手段として有効だと考えれば、テイカーは実に積極的にギブすることもあるわけだ。
これに対して、ギバーは思考と行動の順番が逆になる。まずギブしようとする。相手のことを考え、真っ先に相手に与える。その時点では頭の中に、目的としてテイクがあるわけではない。それでも、結果としてギブが自分に返ってくる(テイク)。
つまり、テイカーの頭に中にあるのは、ひたすら「テイク&テイクン」である。自分から奪いとる。それでも、テイクするためにはその過程で手段としてとられるもの(テイクン)が出てくるのも仕方がない。これがテイカーの思考と行動だ。一方で、ギバーは「ギブ&ギブン」だ。見返りなど関係なしに、まず先に人に与える。その結果、はからずも「どこからかお返しをもらえる」というわけだ。
頭の中に損得のバランスシートを持つ「マッチャー」
「人間関係の損得はお互いに五分五分であるべきだ」と考える人たちもいる。これが著者のいう「マッチャー(バランスをとる人)」だ。彼らは、いつも頭のなかに「バランスシート」をもっている。自分と相手の利益・不利益を、その都度公平にバランスし、ギブ&テイクの帳尻を合わせようとする。「これだけしてもらったから、私も同じくらいお返ししよう」という思考と行動のパターンとなる。
だから、マッチャーというタイプではギブとテイクの間に時間的なズレがあまりない。ギブが先行すればすぐにテイクで補完しようとする。逆に、こういう人々はテイクが先行することも好まないので、そう感じると意識的にギブをする。
「ギブ&テイク」という言葉を聞いて、多くの人がすぐにイメージするのは、ギバーでもテイカーでもなく、マッチャーだろう。ただし、この第3のタイプは本書の分類でいえばギバーでもテイカーでもない人々なのである。
ビジネスにおいては、「ゼロサムではなくプラスサムにしなければならない」とか「ウィン―ウィンの関係を構築して……」というような言い回しがよく出てくる。グラントの議論の美点は、定量的・定性的データの分析から導出される論理を駆使して、われわれが何気なく口にしている「プラスサム」「ウィン―ウィン」といわれる現象の背後にあるメカニズムについての深い理解を与えてくれるところにある。
「速効性」「確実性」を求める人は、ギバーにはなれない
「ギバーこそが成功する」という話なのだが、「速効性」や「確実性」を求めている人は、ギバーにはなれない。人に与えたことは、のちのち返ってくる。しかし、ギブの後のテイク(というかギブン)が起こるのは、ずっと先の話だ。しかも、いつ帰ってくるのか、果たして返ってくるのかこないのか、事前の期待や意図はない。もっといえば、そういう「取引」を持ち込まないのがギバーのギバーたるゆえんなのだ。
ようするに、時間的に鷹揚な人でないと、ギバーにはなれない。ところが、インターネットに代表されるITの進展にともなって、私たちは「時間的なゆとり」「鷹揚さ」を失いつつある。すぐに答えが出たり、時間をおかず返事が返ってきたりすることが当たりまえになっている。だから待てない。
そういう意味では、ITの発達は両義的だ。著者のいうように、ITは世の中を便利にし、ギバーであることのメリットを加速させる面をもっている。しかし、その一方でゆっくり構える鷹揚さを阻害し、ギバーであることを難しくしているともいえる。ギバーでいることの、非常に重要な条件――「心のゆとり」「人間関係において想定する時間軸のゆとり」が、必要なのではないかと改めて考えさせられる。