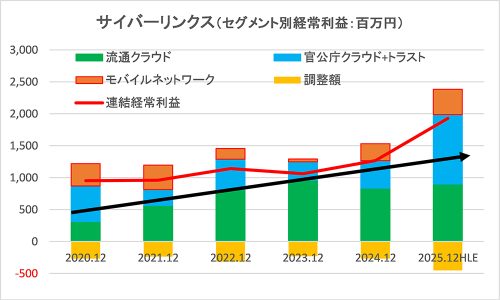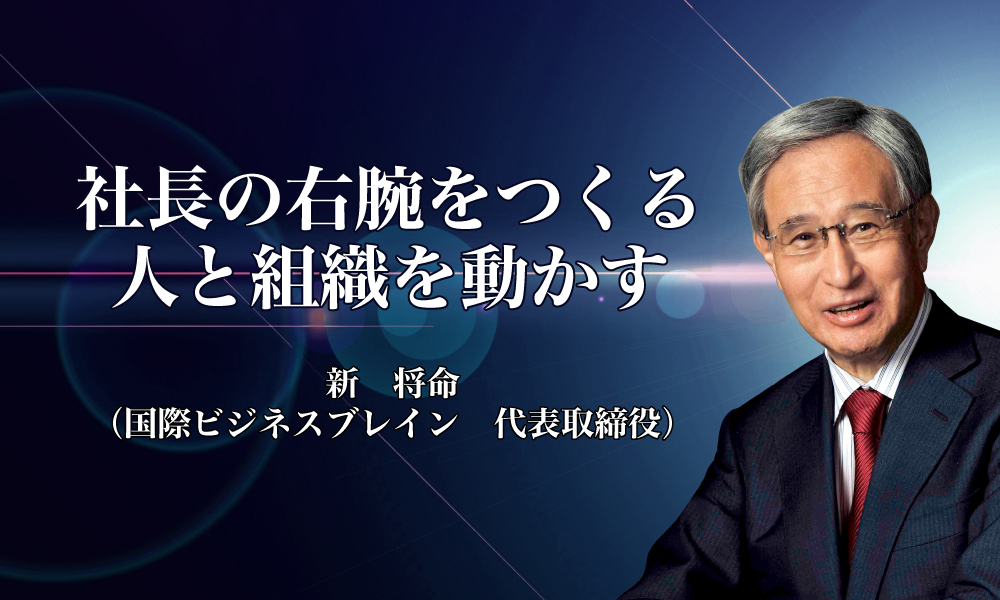「それでだ……おじさん」の戦略思考
前回の続きである。「シナジーおじさん」は信用できないが、僕がイイと思う経営者は「それでだ……おじさん」だ。「社長、この商売はなんで儲かるんですか」と聞くと、こう返してくる。「まずこういうことをやる(A)。そうすると、お客がこうなってくる(B)。で、こっちもこういうことができるようになる(C)。で、そうこうしているうちに、競争相手はこういう出方をしてくる(D)。それでだ……」。
この「それでだ……」のあとに決め技が出てくる。これが「それでだおじさん」の戦略思考である。「シナジーおじさん」と違い、このような思考には時間的な奥行きがある。打ち手が時間軸に沿って配列されている。私見では、戦略構想力の8割がたは時間的な奥行きにある。
ポイントは、ここでいう時間的な奥行きとは、物理的な時間というよりも、論理的な時間だということだ。上の「それでだ……」でいえば、AというアクションがBという状態を促す。それがCを可能にし、さらにそのアクションがDという状態を生み出す。だから他社との違いが明確になって儲かる。ここに流れているのは、A→B→C→Dという因果関係についての論理であって、「2週後に……」とか「3か月ぐらい間を置けば……」という物理的な時間ではない。
もちろん物理的にもAがBに先行して起きるのだが、「それでだおじさん」の思考の焦点は、AがBを生み出し、BがCを可能にする(逆に言えば、BがなければCはできないし、そのためにはBに先行してAが必要になる)という論理にある。論理は必ず時間を背負っている。
究極の「それでだ……おじさん」ジェフ・ベゾス
たとえばアマゾンの創業者のジェフ・ベゾス。私見では、この人は究極の「それでだ……おじさん」である。とくに事業(最初は書籍のネット販売業)を立ち上げるときの「それでだ」思考が味わい深い。
アマゾンがサービスを開始した1995年当時を思い返してみよう。インターネットは爆発的に普及する。それは誰にも分っていた。世の中の人々がインターネットを使うようになれば、ネット経由でモノが売れる(つまりはEコマース)。Eコマースに向いている商品カテゴリーは何か。そのひとつは本ではないか……。「インターネットで本を売る」、ここまでは火を見るよりも明らかな商機であり、誰もが思いついくビジネス・アイデアだった。その証拠に、無数の企業が書籍のEコマースに雪崩を打って参入した。アマゾンはその1社に過ぎない。さらに言えば、アマゾンはとりたてて「先行者」でもなかった。
「24時間365日店を開けておける」「顧客の地理的なリーチが格段に広がる」「店舗に物理的な制約がないので、品ぞろえを無限に広げられる」。多くの競合他社は、こうしたことをリアルな店舗での販売に対するEコマースの優位と考えて商売を始めた。要するに、競合他社はEコマースを「購買のインフラ」と考えていた。比喩的にいえば、「自動販売機」である。品ぞろえが膨大な自動販売機を低コストで家庭の中にばらまく。そのチャンスがインターネットによって訪れたというわけだ。
ところが、こうした多くのEコマース企業がやろうとしたことは、既存のリアル店舗でも「やろうと思えば(ある程度までは)できること」だった。「24時間365日」にしても、リアル店舗の多くが「やっていないだけ」だ。コンビニがやっているように、やろうと思ったらリアルでもできる。きわめて大きな敷地に巨大な書店をつくれば、相当程度まで品ぞろえは拡張できる。ベゾスのような戦略家にとって、「やろうと思ったらできてしまうこと」には意味がない。確固たる違いにならないからだ。
ベゾスが意図した独自のコンセプトは「購買意思決定のインフラ」
本やCDやDVDやおもちゃ、こうしたやたらと種類が多いものの中から、顧客が自分の欲しい商品を探し、見つけ、比較し、意思決定をし、発注し、決済する。本やCDという商品を売るのではなく、一連の購買意思決定を支える。単なる「購買のインフラ」ではなく、顧客にとっての「購買意思決定のインフラ」になる。ここにベゾスが意図した独自のコンセプトがあった。
顧客がアマゾンの店舗に入ってくる。その途端に本屋さんのフロア構成から棚の配置が、その特定の顧客に合わせて一瞬にして変わる。0.1秒後に別の顧客が店に入ってくる。途端に、今度はその新しい顧客に合わせて書棚の配置が一斉に変わる。しかも一人ひとりの顧客に合わせて、そのお客さんが好みそうな本を勧める販売員が来店する顧客全員にアテンドする。入口にある「今週のベストセラー」も一瞬にして変わる。こうした顧客の購買意思決定プロセスに深く踏み込む売り場づくりは、他の自動販売機的なEコマースとはっきりと違っていた。ましてや、これまでのリアル書店にしてみれば、宙返りしてもできないことだった。この意味で、アマゾンは独自だったのである。
他のEコマースの経営者とベゾスとでは、物事が起きる順番についての考え方が決定的に違っていた。多くの人々は、このような順番で考えていた。「インターネットで物理的な制約がない。だから、品ぞろえを思いっきり増やせる。で、顧客にとって便利になる。だから、お客が来る」。
「そんなわけないだろ!」とベゾスは考えた。やたらと品ぞろえが充実していても、自動販売機を置くだけなら人々は魅力を感じない。従来の売り場との本質的な違いはない。
ベゾスが考えた事の順番はこうだった。「購買意思決定のインフラをつくる。そうすると、これまでになかった利便性を提供できる。だから、お客が(その利便性を求めて)集まる。いきなりアマゾンでどんどん物を買ってくれないかもしれない。それでも日常的にアマゾンのサイトにある情報を見に来るようになる。そこに多くの人が集まっているので、アマゾンで売りたいという人々(メーカーやセラー)が出てくる。で、品ぞろえが充実する」。
戦略を突き詰めた先にようやく見えてくる「利便性の正体」
他社は「品ぞろえの充実」を差別化として意図した。そこに利便性の原因を求めた。しかし、そんなにふわふえわしたものでは話にならない、というのがベゾスの考えだった。利便性の正体は購買意思決定支援にある。それがまず顧客を惹きつけ、その上で次にセラーを惹きつける。アマゾンにとって「品ぞろえの充実」は原因ではなく、結果に過ぎない。
ここでのポイントは、論理的な時間軸を取っ払って平面上にやっていることを並べてしまえば、意図している事の順番はまるで違うにもかかわらず、アマゾンと競合他社との間には(とくに初期の段階では)さしたる違いはないように見えたということだ。
外から眺めている他社にしてみれば、アマゾンの打ち手や施策は見えても、時間的な奥行きを持つ順列は見えない。だからアマゾンの真の競争力がなかなかわからない。部分的に似たようなことをやっても、その配列が異なるので、アマゾンが意図したような論理が作動しない。
前回も話したように、その本質が順列にあるという意味で、戦略は料理に似ている。素材やその組み合わせは見える。しかし、その背後にある順列、とりわけそれらを結びつける論理は当事者以外にはなかなか見えない。他者から容易には「見えないもの」にこそ、独自の顧客価値の源泉がある。