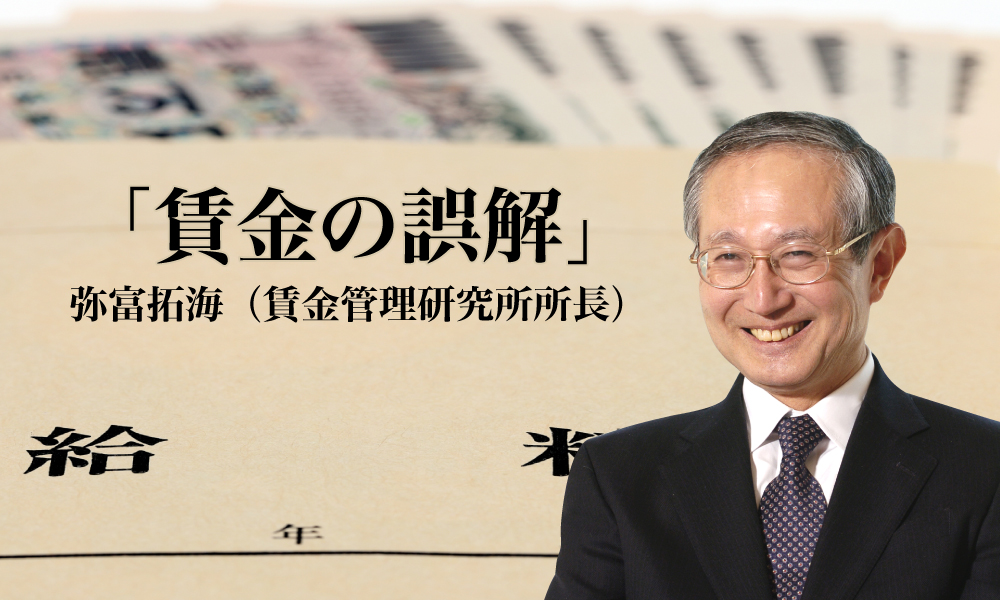政商としての三菱創業
戦前の「財閥」の代名詞でもある「三菱」の創業は、幕末・維新期の革命期に波乱の人生を送った岩崎弥太郎(いわさき・やたろう)の活躍とともに語られることが多い。しかし、現在に続く巨大な三菱系企業群の歴史は、兄・弥太郎から二代めとして経営を引き継いだ岩崎弥之助(やのすけ)の功績なしには語れない。
土佐藩の最下層の貧乏士族出身の弥太郎は、維新直後、土佐藩が大阪に設立した大阪商会の経営を任されたのを足がかりに、傑出した商才と強引な性格を生かして財界に船出する。財を築いたのは、海運事業だった。1870年代に佐賀の乱、西南戦争など不平士族の反乱が起きると、いまだ不安定だった明治政府に全面協力して兵員、軍需物資の輸送を引き受け、大久保利通、大隈重信ら政府中枢に取り入る。こうした政府とのコネを最大限に利用し、1874年の台湾出兵の軍需輸送では、政府系の日本郵便蒸気船会社が消極的だったのを尻目にロジスティックを一手に引き受けた。この一事によって同蒸気船会社は解散させられ、その持ち船は全て三菱に払い下げられて、三菱は、内外航路の海運利権を独占することになる。
政商としての三菱の発展は、3年後に大久保利通の暗殺で後ろだてを失うと一気に暗転する。薩長の藩閥政府は弥太郎の締め付けに転じて、それまでのやりたい放題を許さなくなる。三菱への特権を取上げにかかる。事業発展の原動力だった海運にも三井を中心に設立した新会社をぶつけ、三菱つぶしに乗りだした。両者間で激しい値下げ競争が勃発し、三菱の汽船事業は青息吐息の状況となる。ストレスから胃がんを患った弥太郎は無念の思いを抱えて憤死した。まだ52歳の若さだった。
海から陸へ、事業を多角化
16歳離れた弟の弥之助が事業を引き継いだが、三菱の屋台骨はぐらぐらだった。中核の海運業は、弥太郎の死で二社の値引き“戦争”は終戦を迎え、両社は政府の斡旋で合併し、日本郵船会社となった。しかし、三菱の権限は大きく制限されていた。
34歳で新総帥についた弥之助の決断は鮮やかだった。政府が干渉を強める海運業から完全撤退し、事業の多角化に活路を見出そうとする。
経営多角化の芽は、兄・弥太郎がまいた種に大きく伸びる兆しがあった。海運業には船の修理がともなう。弥太郎は長崎に政府が設立した長崎造船所の貸与を受けて自社船舶の修理拠点としていた。弥之助は、そこに未来を見た。
〈海国の日本が世界に伍して海洋に進出するためには、先進的な造船力の強化が必要だ〉
海軍の軍艦も英国などからの輸入に頼っていた。大きく国に寄与できる可能性を見ていた。弥之助は2年後に長崎造船所を国から払い下げを受けて、積極的な設備投資と海外からの技術導入を行い、世界的水準の造船所に成長させた(現・三菱重工業長崎造船所)。
また、弥太郎が手をつけていた船舶燃料用の石炭を手に入れるための鉱山経営もさらに推進する。これが、のちの燃料革命を担う石油販売、さらには、石炭、石油を原材料とする三菱化成へと発展してゆく。さらに、海運事業につきものの損害保険の事業拡大にも投資を惜しまなかった。
死にかけていた巨龍は、海から上陸することで、さらに巨大なコングロマリットとして日本経済を左右する存在までに成長する。
二代目が決める企業の未来
弥之助は兄と違い堅実で温厚な性格であったという。兄のような強引さで鳴り響くカリスマ性はなかった。二代めが持ち合わせていたのは、事業の未来を見抜く非凡な先見性だった。
もし、苦境にあった三菱を引き継いだ弥之助が、初代が築いた事業の中核であった海運業の再生にこだわり、先代が関連事業として種をまいていた枝葉の諸事業の将来性に気づいていいなければ、今につながる三菱の発展はなかった。
創業初代は、企業発展の礎を据える。永続企業として花開くかどうかは、二代めの先見の明にかかっているのだ。
(書き手)宇惠一郎 ueichi@nifty.com
※参考文献
『もう一人の「三菱」創業者、岩崎弥之助 企業の真価は二代目で決まる』河合敦著 ソフトバンク新書
『日本の15大財閥 現代企業のルーツをひもとく』菊地浩之著 平凡社新書
『財閥の時代』武田晴人著 角川ソフィア文庫