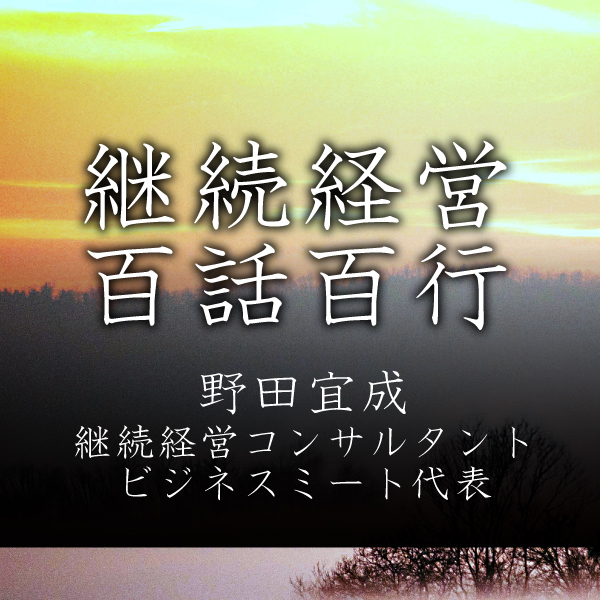- ホーム
- 指導者たる者かくあるべし
- 逆転の発想(40) 負けっぷりをよくする(吉田茂)
占領統治下の日米関係
日本は、第二次世界大戦でポツダム宣言を受け入れて無条件降伏し、1945年(昭和20年)9月2日、重光葵(しげみつ・まもる)外相が戦艦ミズーリ号甲板で降伏文書に調印して連合国による占領統治下に入った。
同月、東久邇宮(ひがしくにのみや)内閣の外務大臣に任命された吉田茂は、終戦時の首相を務めた鈴木貫太郎海軍大将を訪ねている。助言を求める吉田に鈴木は言った。
「戦争は勝ちっぷりも良くなくてはいけないが、負けっぷりもよくしないといけない。まな板の上に上がった鯉のように」
その後、1952年まで続くG H Q(連合国軍最高司令官総司令部)治下で、外相、首相として国の舵取りを担った吉田は、この言葉を深く胸に刻んだ。
米国を中心とする連合国は民主化の名のもとに日本を弱体化するため、非現実的な無理難題を強要したが、日本が米国の植民地とならずやがて独立し、その後経済発展の道を突き進むのは、吉田の柔軟でありつつ剛直なまでに粘り強い対米交渉術にあったと言ってもよいだろう。
相手の組織を把握する
吉田はまず、乗り込んできた米国の占領行政組織を分析、把握することに全力を挙げた。初対面の段階からG H Qの最高司令官であるマッカーサーが強大な権限を持ち、その前に出ると米軍人、官僚たちのだれもが直立不動で「イエス、サー」を繰り返すのを見て、難題はマッカーサーとのサシでの話し合いによりしかあるまいと見抜いた。
G H Qの組織が大きく二つの勢力で分裂していることもわかった。終戦前から米本国で日本占領計画を練り上げてきた民政局と、大戦中から、軍人としてマッカーサーを補佐してきた参謀部だ。民政局のメンバーたちは、理念的で準備してきた政策を日本政府に押し付け、反論を許さない傾向が強い。対して戦場で生死をかけてきた参謀部の人脈は、現実的で、どうすれば、日本の戦後復興と民主化を進められるか、日本側の意見に耳を傾ける。
占領初期の段階では、民政局では対ゲリラ戦も想定し、日本政府の裁判権を取り上げ米国の軍事法廷で裁く軍政を携えてきたが、まったく現実にそぐわないものだった。また、米本土でも進歩的とされるニューディーラー(革新派)たちが民政局には潜り込んでおり、教育制度の改革、労働者の権利拡大などを“民主化実験場”としての日本に持ち込むことを目論む。
参謀部では、日本をいかに早く経済復興させ独立させるかに意を注ぎ、そのために治安維持を含めて日本側の協力を求める。どこまでも現実的なのである。
しかし、日本の官僚、政治家との交渉の前面に出てくるのは民政局の面々である。官僚たちは、強面で融通の効かない命令に手を焼いていたが、吉田は難題が起きると参謀部のメンバーを通じてマッカーサーにアポイントを取り直接交渉した。
吉田の命を受けて対G H Q交渉にあたっていた白洲次郎はある時、民政局長のホイットニーに呼び出された。農地改革問題や財閥解体、要人の公職追放をめぐって過度の要求を振りかざすG H Qと日本政府との間の溝は深まっていた。会議室では民政局の幹部たちがずらりと白洲を取り囲む。そしてホイットニーは言い渡した。
「近ごろ、吉田の日本政府はG H Qを軽んじている。これまでマッカーサー元帥は日本に対してソフト・ポリシー(柔軟策)で対応してきたが、このままだと元帥もハード・ポリシー(強硬策)に転換せざるを得ないと考えている」
脅しである。白洲は吉田に伝える。信頼するマッカーサーが豹変するとは由々しき事態である。吉田は二、三時間のちにマッカーサーと面会する。マッカーサーは驚いた表情で言った。
「そんな話は言った覚えもないし、聞いたこともない」
官僚というものは、事態が動かなくなると権力者の存在を背後にちらつかせて強引に施策を進めようとするものだ。交渉ごとでは、交渉に出てきた権力を笠に着る“役人”の脅しにひるまず相手トップの真意を直接、探ることが重要なのだ。
真の負けっぷり
吉田は、冒頭の〈負けっぷり〉の信念についてこう回想している。長いがそのまま引用する。
〈負けっぷりを立派にするということは、何もかもイエス・マンで通すということではない。また表面だけはイエスといっておいて、帰ってから別の態度をとるという、いわゆる面従腹背などは、私の最も忌むところであった。要は出来るだけ占領政策に協力するにある。しかし時に先方に思い違いがあったり、またわが国情に副(そ)わないようなことがあったりした場合には、出来るだけわが方の事情を解明して、先方の説得に努めたものである。そしてそれでもなお先方の言い分通りに事が決定してしまった以上は、これに順応し、時来って、その誤りや行き過ぎを是正しうるのを待つという態度だったのである。換言すれば、言うべきことは言うが、あとはこれに従うという態度だったのである〉
いかがだろうか。痛快ではあるが作りごとのテレビドラマ「半沢直樹」にはない現実のドラマ「吉田茂」がここにはある。
(書き手)宇惠一郎 ueichi@nifty.com
※参考文献
『回想10年(1)』吉田茂著 中公文庫
『マッカーサーと吉田茂 上、下』リチャード・B・フィン著 内田健三監訳 角川文庫