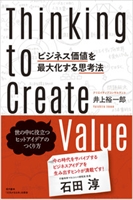- ホーム
- 指導者たる者かくあるべし
- 逆転の発想(16) 最後の勝負は商品力(サントリーの挑戦)
寡占のビール業界に殴り込み
赤玉とウイスキーで洋酒業界を席巻していたサントリー(旧寿屋)が、ビール製造販売に乗り出したのは、1963年4月のことだった。ビール業界への進出は創業者の鳥井信治郎以来の悲願だった。
しかし、当時の業界は、キリンビールを筆頭に、アサヒ、サッポロの三社による寡占状態で、販売網は牛耳られ、つけ入る隙がなかった。二代目を継いだ息子の佐治敬三が目をつけたのは、三社の製品の味が似たり寄ったりで、例えば、ドイツのように土地土地で味が違うビール文化とは程遠かったことだ。
「ウイスキーだって産地、醸造元によってそれぞれ個性がある。これまでにない新しい味で攻めれば活路はある」
佐治は、ヨーロッパへの調査旅行を繰り返し、味に惚れ込んだデンマークのビール会社と提携契約を結び、同社の技術協力で武蔵野工場の突貫工事に着手した。デンマークの技術者の指導は、徹底した無菌工場建設で、佐治も辟易とするぐらいだったが、「ビールの味を決める微生物の管理にはそれが常識」という指導に従った。
宣伝だけでは売れない
出来上がった製品の味には絶対の自信があった。これまでにない爽やかさがあった。
さらに寿屋時代からの宣伝力には自信があった。赤玉ポートワインでの艶かしい女性の写真ポスター、さらに戦後のウイスキー大衆化に寄与したトリスの発売に際しての、「うまい、安いトリスウイスキー」「トリスを飲んでハワイへ行こう」などなど、数々の名キャッチコピーが、販売を支えた。
今回も発売に際して、一面ぶち抜きの新聞広告で、〈これで私たち日本人の技術に新しい「なにか」が加えられたのです〉とビール新時代の到来を高らかに歌い上げた。
しかし、「宣伝が効きすぎた」(宣伝部員だった開高健の回想)。評判は良かったが、売れすぎて店に商品が届かない。既成三社は販売網を締め付け、販売店もサントリービールを扱わなくなる。
売れない5年間は長かった。「所詮ウイスキーメーカーのサントリーがビールで戦うのは無理、ビールから撤退か」の噂も流れた。
不屈の初心と周到な準備
「新鮮な味は消費者に受け入れられたはずだ」と考えた佐治はさらなる味の改革に取り組んだ。それまでの瓶ビールは最終工程で高熱殺菌して出荷され、どうしても味が落ちた。生ビールに近い味の瓶ビールはできないものか。技術的には網の目の細かなミクロ・フィルターで濾過する製法がある。しかし、雑菌を濾すにはフィルター通過に時間がかかり、生産効率が悪いから、各社とも導入に二の足を踏んでいた。
しかしサントリーの工場は、無菌工場化されている。試してみると、効率よく濾過できることがわかった。工場立ち上げ時のデンマーク技術者のアドバイスに従った準備段階の周到さがここで生きてきた。技術を学ぶなら徹底的にまねろという教訓だ。
「純生」と銘打った新製品は、新時代のビールとして評判を呼び、独走状態となった。年間販売量は、前年比126%増の飛躍的な伸びを見せ、既存社の締め付けに二の足を踏んでいた販売店からも次々と出荷要請が来るようになる。
佐治自ら先頭に立って販売店をまわり、営業社員も親身に販売店の相談にも乗るようになった。
ビールがダメでもウイスキーがある。そんな甘えが全社的に巣食っていたのかもしれない、と開高も回想している。かつて鳥井信次郎自らハッピを着て、ポートワインを大八車に積んで売り回った。なにがなんでも売るという初心と、味という品質への絶対の自信こそが商売の基本であるということに気づかせたのが、ビール挑戦の一番の成果だったのだろう。
2代目の佐治も、その経験を通じて、父の口癖だった「やってみなはれ」の精神を今いちど強く感じたのに違いない。
(書き手)宇惠一郎 ueichi@nifty.com
※参考文献
『へんこつ なんこつ』佐治敬三著 日本経済新聞社
『やってみなはれ みとくんなはれ』山口瞳、開高健著 新潮文庫