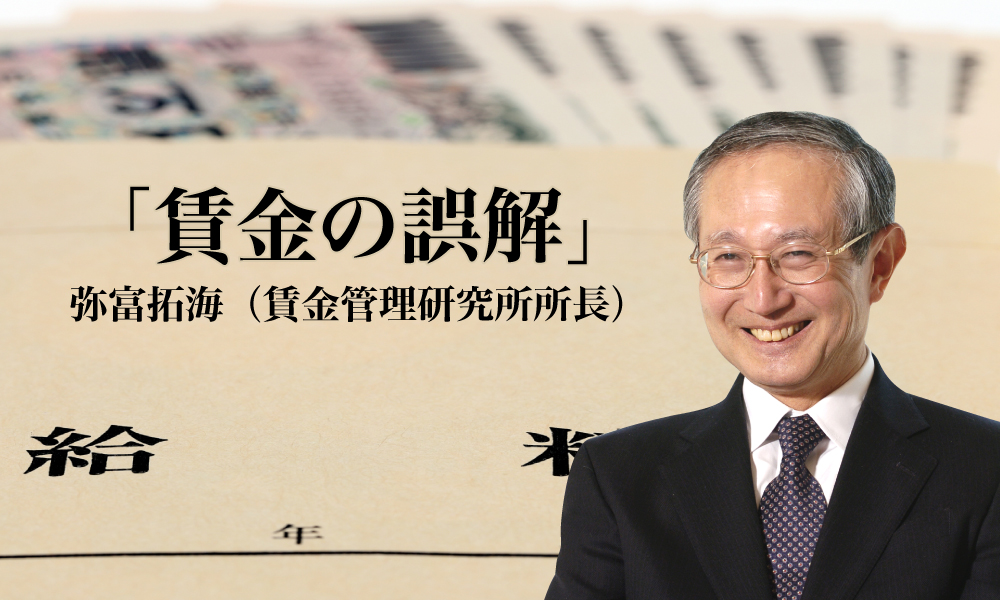- ホーム
- 指導者たる者かくあるべし
- 挑戦の決断(5) 体制永続の後継システムを確立する(徳川家康)
豊臣政権失敗の教訓
創業者に共通で最大の悩みは安定的な後継体制であろう。15代260余年にわたり安定的な経営を築いた徳川幕府は、初代徳川家康によって考え抜かれた体制構築のたまものだった。
関ヶ原の戦いに勝利し、1603年に征夷大将軍となり江戸に幕府を開いた家康にとって反面教師となったのは、豊臣秀吉の失敗だった。
子宝に恵まれなかった秀吉、いったんは甥の秀次を後継に定め、関白職を譲った。ところが淀君との間に秀頼が生まれるや、方針を覆し、あろうことか秀次に謀反の疑いありとして冤罪を着せ、一族もろとも殺した。この無慈悲なやり方が、広く家臣に動揺をもたらしたことは間違いない。安定的な後継体制の確立が組織永続の条件として不可欠であることを家康は思い知ることになる。
嫡子継承の明確化
嫡男(男子の長子)に家督を譲る。昔から日本社会に根付いた風習である。しかし、ことはそう容易くもない。長子が無能であれば、あるいは無能と言わぬまでも、より能力の秀でた兄弟がいれば、そちらに譲りたくなるのが親の真情でもある。家督を譲った子に後継が生まれなければどうするか。だれしも悩むところだ。原則がなければ、後継者をめぐって派閥抗争が起きて内紛と分裂を招きお家騒動の勃発となる。
さて家康はというと、家臣の信望が厚かった長男信康がいたが、早くに織田信長から謀反の疑いをかけられて自害に追い込まれていた。次男の秀康は結城家に養子に出しており、後継に見込んだ三男・秀忠は、肝心の関ヶ原の合戦に遅参して、譜代の家臣らの不興を買っている。さてどうしたものか。
家康は決断する。「現状においては秀忠が嫡男、嫡男後継の原則を貫こう」。決断すれば行動する。権力掌握の源泉である征夷大将軍の地位を2年で秀忠に譲り、〈大御所〉として駿府(静岡)に隠居する。
隠居とはいっても、自らの周りに茶谷四郎次郎、三浦按針といった政策ブレーンを集め実質的な院政を敷いた。権威は息子に譲ることで、天下に「後継は秀忠」を示す。それは淀君・秀頼の豊臣方に将軍職は徳川が代々世襲することを見せつけることにもなる。そして秀忠のいる江戸城には、三河領国以来の譜代の重臣たちを置いて合議体制を取らせ、能力未知数の秀忠の独断専行を防止した。後を任せたとはいえ、心から信頼しているわけではない。秀忠に政治修行を強いたのである。
後継者としてはたまったものではないが、創業者としての用心深さは、ある意味で参考になろう。
秀忠は、自ら後継を気に入りの庶子に指名しようとしたが、家康は「家督は嫡子が継ぐべきだ」といさめて、家光を3代将軍に決めて世を去った。また秀忠に不満を持つ弟を配流し自殺に追い込むなど、家康は、後継の嫡子を一族で支える原則を決して揺るがせにしなかった。
万全の補佐体制
徳川の後継システムはさらに巧緻である。将軍に世継ぎがいない場合は、近親分家である御三家(尾張、紀伊、水戸)、御三卿(領地を持たず江戸城住まいの田安、一橋、清水)から養子を迎える体制を整えている。後継人事は全て“徳川グループ”内で完結させ、外部からの干渉を排した。
こうして家康が目論んだ通りの相続原則によって、徳川の世は260年の栄華を誇ることとなるが、しかしそれも安定の時代のシステムに過ぎなかった。黒船来航と言いう外圧によってもたらされた激動の時代には安定のシステムは柔軟な発想の足かせとなる。
家康以来、外様として、政策合議から遠ざけられてきた長州、薩摩といった雄藩から噴出した体制批判が爆発し、徳川の世はあっけなく滅びてしまう。
激動の時代の組織には、ダイバーシティ(多様性)こそ大きな力を発揮することを、決してお忘れなさらぬように。
(書き手)宇惠一郎 ueichi@nifty.com
※参考文献
『織豊政権と江戸幕府』池上裕子著 講談社学術文庫
『歴史と旅 徳川十五代の経営学』秋田書店