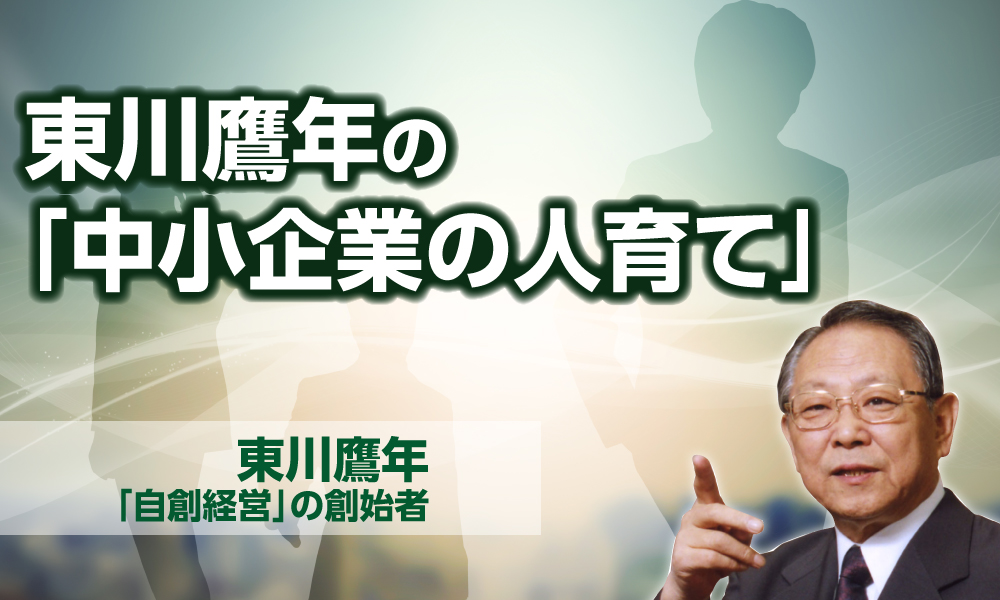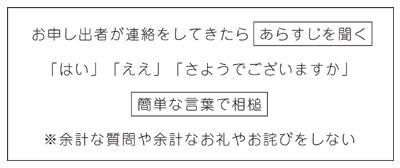■乳白色の濁り湯が自慢の混浴野天
長野と新潟の県境、妙高山の麓に湧く燕温泉。標高1100mの高所に位置する温泉街には、山の斜面にへばりつくように数軒の宿と土産物屋が並んでいる。訪れたのは残暑が厳しい季節だったが、2000m級の山々に囲まれた温泉街は、ひんやりとした空気が漂っていて清々しい。
燕温泉に宿泊する観光客や妙高山の登山客の多くが立ち寄るのが、温泉街から10~15分ほど歩いたところに湧く「黄金の湯」と「河原の湯」という2つの野天風呂だ。
とくに「河原の湯」は文字どおり渓流沿いにあり、野性的なロケーションが感動的だ。緑に囲まれた湯船は、10人以上が一緒に入浴できる岩風呂で、ミルクのような白濁の湯が輝きを放っている。硫黄泉特有の香ばしい匂いも強く、パンチのきいた見た目だが、実際に入浴すると、泉温は40℃弱で、肌触りもマイルド。思わず長湯したくなる泉質である。
湯船はひとつしかないので、当然、混浴だ。簡易な脱衣所があるうえに、透明度の低い濁り湯なので、女性でも比較的入りやすいようだ。筆者が初めて訪れたときには、熟年夫婦や女性グループ、外国人の若いカップルなど入浴客も多かった。
居合わせた入浴客のマナーもよかったため、初対面の人同士で会話が弾み、和気あいあいとしたムードが流れていた。老若男女が性別や世代を越えて心を通わせる。これぞ混浴の醍醐味だろう。河原の湯には、混浴の原点がたしかに存在していた。
■衰退しつつある混浴文化
そもそも混浴は、日本独自の温泉文化といわれ、かつて日本に開国を迫ったペリー提督は男女が混浴する風習に驚いたという。海外の温泉にも混浴はあるが、水着を身につけて入浴するのが通常だ。
思い返せば、これまでも数多くの混浴風呂に浸かった。福島のある鉱泉宿では母親ほど年が離れた女性と、2人で一杯になるような小さな湯船に一緒に入り、宮城のある露天風呂では中年女性の集団から質問攻めに遭い、山梨のある宿では老夫婦との会話に花が咲き、1時間も同じ空間をともにした。いずれも混浴だからこそ心が通い合い、今でもいい思い出として記憶に刻まれている。
しかし、混浴は減る一方である。混浴文化が色濃く残る東北でさえ、男女別の時間を設定したり、湯船に壁を設けたりするのが時代の流れだ。やはり混浴は入浴しづらいという女性客の要望も強かったのだろうが、一方で男性客のマナーが悪化しているのも原因だといわれている。
実際に各地の混浴で、女性のほうを無言でずっと見ている人、男性の大事なところを隠さず見せつけるかのように歩きまわる人、ペットボトルを持参して長時間居座っている人など、あきらかに温泉ではなく、女性の裸が目的でやってきている人たちを目にしてきた。男性の目から見ても、恥ずかしくなる破廉恥な行為だ。
こんな行為をする人が増えると、女性の混浴離れが進むだけでなく、純粋に温泉を楽しみに来た男性客も居心地が悪くなる。温泉文化を守るためにも、気持ちよく温泉を楽しむためにもマナーを守ってもらいたいものだ。
■男女別の野天風呂「黄金の湯」
なお、河原の湯は2022年の災害によって湯船へと向かう橋が落ちてしまい、しばらく利用できずにいたが、2024年に復活を遂げた。湯船に張られた美しい白濁湯は相変わらず。今年も冬期閉鎖が解除される6月頃には混浴を楽しむ老若男女でにぎわうはずだ。
もうひとつの野天風呂「黄金の湯」(冬季閉鎖)は妙高山の登山口にある岩風呂だ。秋になると周囲に黄金色の葉が舞い落ちることから名付けられたという。こちらも野趣あふれる露天風呂に乳白色の湯が掛け流されるが、男女別なので混浴に抵抗がある人にはこちらがおすすめだ。