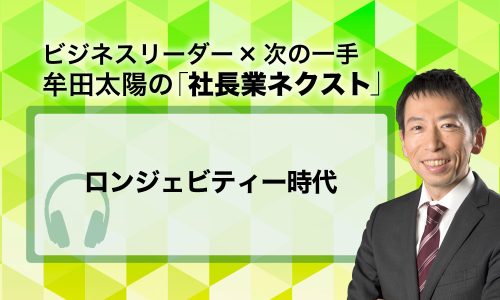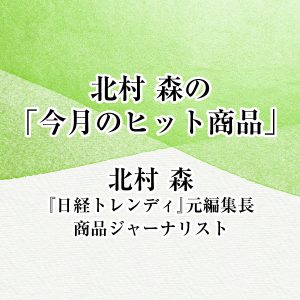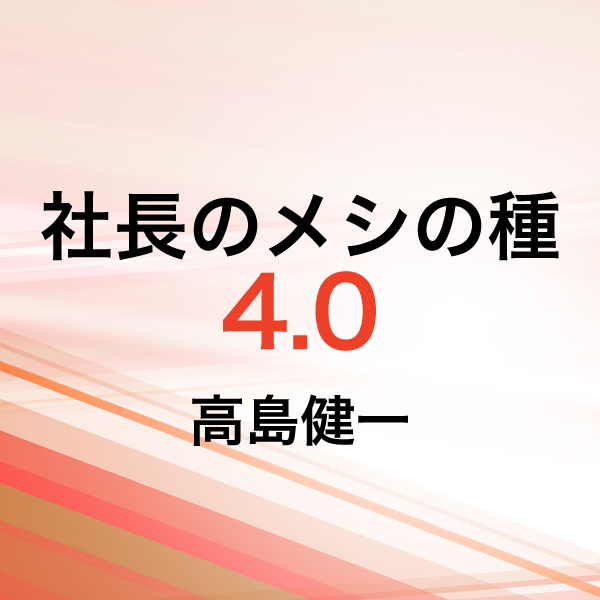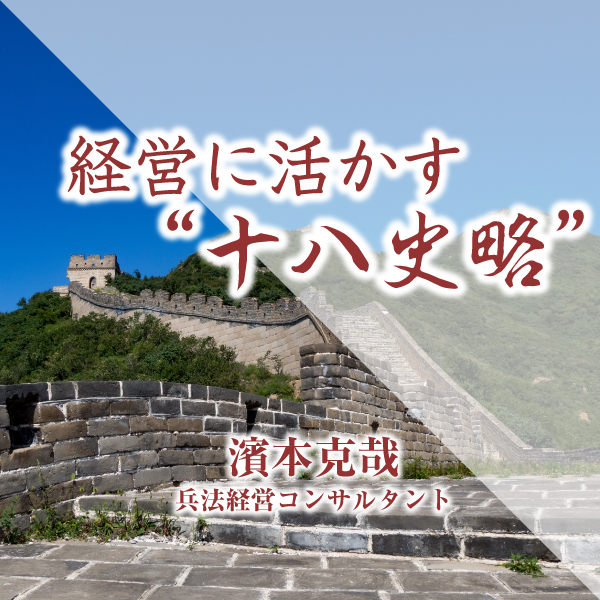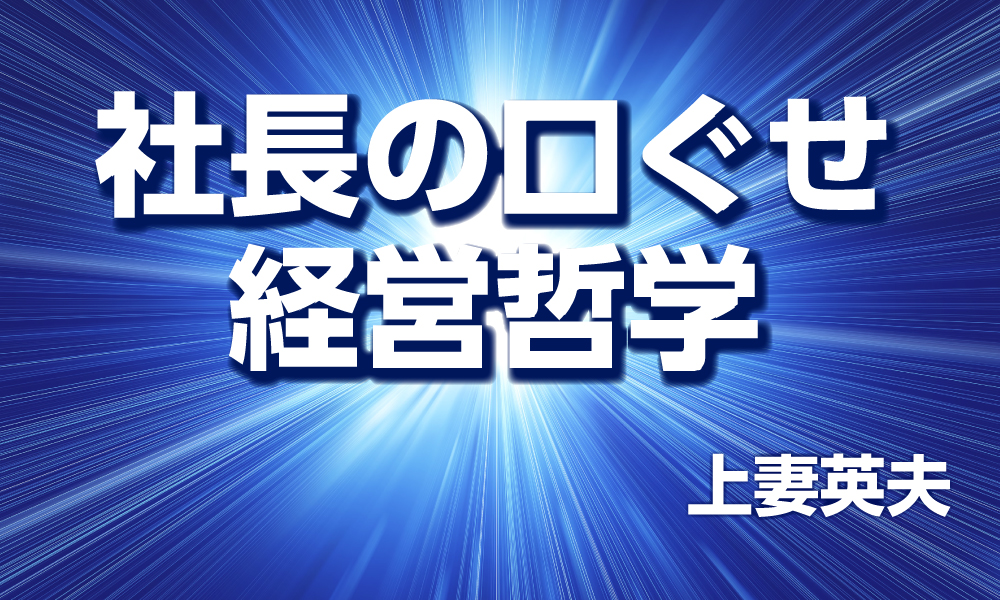鉄道発祥の国
鉄道発祥の地といえば英国である。1825年に世界で初めて蒸気機関車による鉄道の営業を開始した鉄道王国は、経営の効率化をめぐり民営と国営の間で揺れ続けた。100年経った今も経営安定の処方箋は確立していない。
運河を利用した舟運に代わる大量貨物輸送機関の担い手として注目された鉄道だが、1830年に、イングランド北西部の二大工業都市であるリヴァプールとマンチェスターを結ぶ鉄道で本格的に旅客輸送がはじまると、産業革命を支える足として脚光が集まり、全土で投資対象として鉄道敷設ブームに火がつく。1848年には、鉄道の総延長は8,200キロに伸びた。十数年で、東京―大阪間の実に15倍に当たる線路が敷かれた。まさに「鉄道狂時代」の到来だ。
当初、地域ごとに無数の民間会社が乱立していたが、第一次世界大戦後、政府の方針で、120あった鉄道会社がロンドンからの方面別に4社に統合された。
しかし、第二次大戦前後から、道路網の拡大と自動車の普及で鉄道需要は頭打ちとなる。さらに、大戦中にドイツ軍の爆撃で大きく損傷した線路の補修の負担も重なり、4社ともに赤字経営が続き、設備投資もままならない苦境に陥った。
国有化での立て直しも難航
大戦で大きな痛手を受けた経済基盤の復興を目指すクレメント・アトリー率いる労働党政権は、公共事業の国有化を進めており、1948年に鉄道事業も運営の効率化と、遅れていた設備投資、保守整備促進のため政府の一元管理下に置かれることになる。私鉄4社は「ブリティッシュ・レールウエイズ」という統一商標で運行された。さらに1962年には、「英国国鉄本社」という公共企業体として独立した。戦後日本の国鉄(日本国有鉄道)と似た立場となる。
しかし、英国国鉄には日本の国鉄とは違い、経営の一体感に乏しかった。日本の国鉄が戦前の鉄道省のもとで長年続いた一社体制を経験していない。4社統合後も、旧社の営業エリア別の管理局体制を敷いたため、縄張り意識が残った。機関車も旧社の車両を踏襲していた。電化も遅れ、国費支援頼みの経営が続き、国有化後も赤字体質は改善されなかった。
私鉄の群雄割拠運営でスタートした英国の鉄道は、同じ都市間を結ぶ鉄道も競合する複数社が到達時間を競い合ってきたライバル路線が多く、国鉄に統合された後も路線配置に無駄が多かった。
大胆な路線廃止と組織の組み替え
政府は鉄道国有化で当初1962年に黒字化を目論んだが、達成には程遠く、63年ようやく、不採算路線の大胆な廃止に取り組む。1970年までに全路線の三分の一を廃線とし、全営業駅の半分が廃止された。荒療治である。
1980年代に入ると、私鉄4社体制を引きずっていた地域別管理体制にようやくメスが入れられる。経営統合の障害となっていた地域別組織を課題部門別組織に改変した。新たに都市間鉄道、ロンドン・南東部、地域鉄道、郵便荷物、貨物の5部門が成立した。これにより、時代の要請に応じた設備の近代化、車両の高速化に取り組めるようになった。
巨大組織の統合・合併で重要なことは、まず旧態を引きずる組織を解体し大胆に組み替えることだ。それなしに寄せ集めただけでは経営の一体化、効率化など望むべくもない。
英国国鉄がもたつく間に、新自由主義を掲げる保守党から、鉄道事業の民営化の構想が持ち上がってくる。(この項、次回へ続く)
(書き手)宇惠一郎 ueichi@nifty.com
※参考資料
『折れたレール イギリス国鉄民営化の失敗』クリスチャン・ウルマー著 ウェッジ社