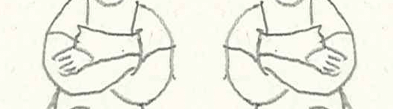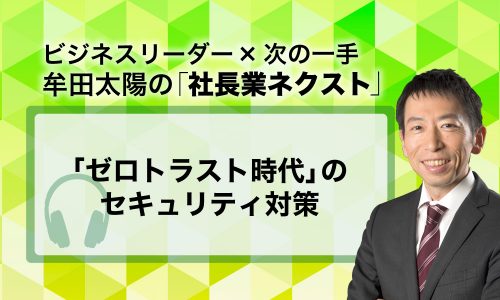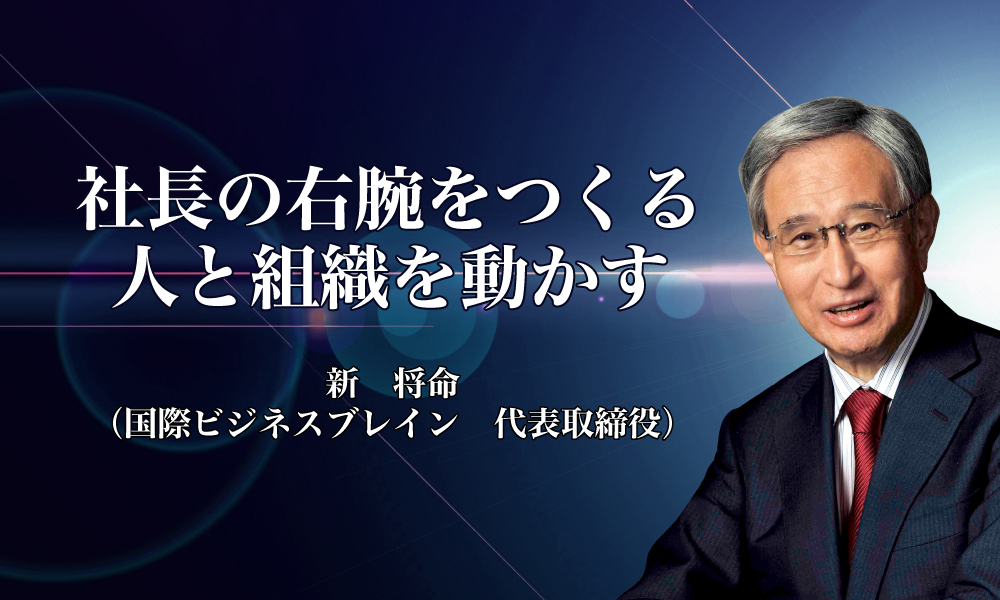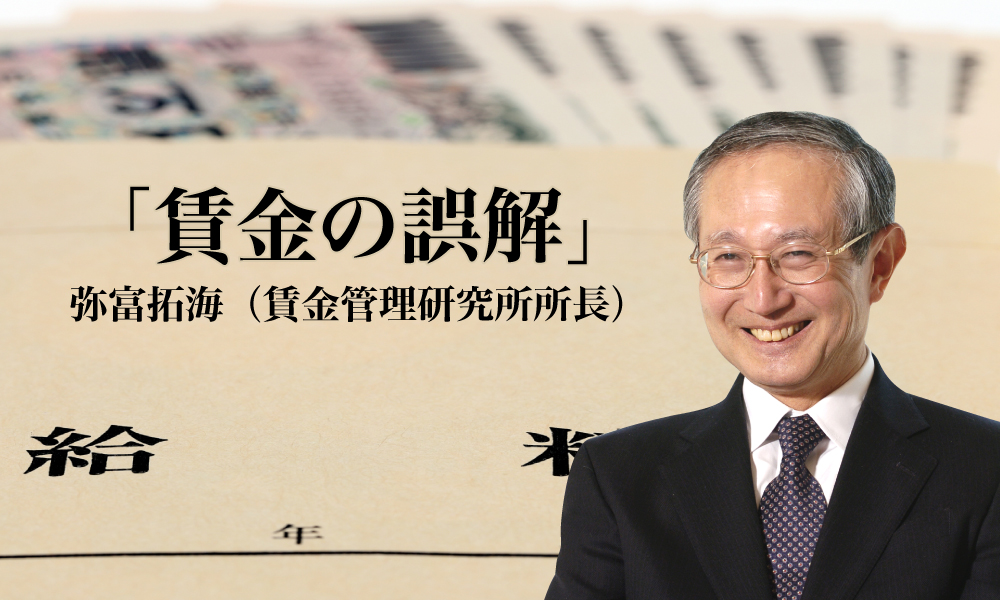時代劇を見ていると、時折「夜鳴きそば」の屋台が登場する。現代で言えば、乗り物の駅や商店街の「立ち食いそば」同様のファストフードだ。アメリカのハンバーガーやサンドイッチ、中国の点心など、各国に例はあるものの、日本はかなり古い歴史を持つ。大きな違いは、食材は元よりだが「企業」ではなく「個人経営」によることだろう。
江戸期に、江戸の人口は飛躍的に増えたものの、人口における男女比は圧倒的に男性が多く、そうなると手軽な食事が必要なのは今も昔も同じことだ。「早い、安い、旨い」という、どこかで聞いたフレーズは既に300年以上前の江戸で試みられていたのだ。「旨い」かどうかは、実食できないために判断はつかない。
「関西のうどん文化、関東のそば文化」と言われるように、江戸で最も馴染みが深いのは、冒頭に述べた「そば」だろう。落語にもよく登場するが「二八そば」と呼ばれ、価格が十六文だから、つなぎとそば粉の割合が「二八」だからなど、諸説ある。ここでは価格を例に考えることにする。「十六文」とは一体、現代のいくらぐらいに相当するのだろうか。
話は多少ややこしくなるが、江戸期の貨幣制度は「変動相場」で、関西では「銀本位」、江戸では「金本位」だった。江戸期の「金一両」は時期により現代の6万円から10万円の当たりを行き来していたようだ。「一両=4000文」であり、計算しやすくするために8万円とすると、一文は20円となる計算だ。十六文は320円、今の立ち食いそばの「かけ」とあまり変わらない。「立ち食いそば」は隠れた物価の優等生とも言える。
「江戸っ子だってね、鮨喰いねぇ」は有名な浪曲『森の石松』にあるフレーズだ。目の前に江戸湾が広がり、海水汚染が今ほど深刻ではなかった時代のこと、江戸湾で揚がる魚を主なネタにした「屋台」の寿司屋の登場と相成る。当時の風俗を描いた『守貞謾稿』によれば、主なネタは「煮穴子」「白魚」「小肌」「玉子」「玉子巻」「海苔巻」などで、「玉子巻」が十六文、他は八文とある。320円と160円、現在の回転寿司と良い勝負ができる価格だ。
「関西では箱寿司(押しずし)、江戸は握り寿司」との棲み分けが定着したのは江戸時代後期のことで、よく知られるように「江戸前」とは江戸湾で揚がった魚を使った旨だが、もう一つ前の時代には、「鰻」を指した言葉だとある。今は高くて手が出にくい鰻も、江戸期には庶民のためのファストフードとしての役割を担っていたことがわかる。「鰻」については、「特別枠」で別の回に触れることにしよう。
残るは「天婦羅」だ。元は長崎の出島の宣教師たちの料理、ポルトガル語の「テンポーラ」が訛ったもので、今のような料理ではなく、「フリッター」に近かったとの説もある。それが日本流になり、江戸前の「天婦羅」と呼ばれる頃のネタは「穴子、芝海老、貝柱、小肌、するめ」などとある。面白いのは、ネタの範囲に野菜が入っていないこと。野菜は天婦羅とは言わずに「揚げ物」と呼んで区別をしていたようだ。となると、「野菜天丼」は江戸期には成立しなかった、ということになる。
また、食べ方も現在とは違い、串に刺した材料を揚げたものを、丼などに入ったタレに付けて食べるもので、一串四文から六文とのこと。「二度漬け禁止」でお馴染みの、大阪名物の串揚げの食べ方のような感覚で天婦羅を食していたようで、価格も現在とさして変わらないか、やや安めだろうか。
これらはいずれも「立ち食い」で、店舗を構えているわけではない。背景の一つとして、江戸時代は朝・夕の一日二食が基本で、午後2時から4時の「八つ時」に小腹を満たすために食べるもの、ないしは早い夕食の後や寄席や芝居、お湯(銭湯)の帰りにつまむもの、という存在だったからだ。また、移動することで、時間帯により営業場所を変えることができる利点があった。この辺りは、昨今の昼休みに見掛けることの多い、ワゴン車などでの弁当の移動販売と同じだ。300年やそこらでは、人間の考えることはたいして変わらないようだ。
ただ、これらのファストフードは食事というより「おやつ」や「軽い夜食」に相当するもので、「八つ時」に食べる「おやつ」の習慣は一日三食が当たり前の現在でも続いており、江戸期の感覚で言えば、現代の我々は時には「一日四食」を食べていることになる。「飽食」と言われても仕方がない。
こうしたファストフードはもっぱら庶民のささやかな楽しみで、武士はこうした物を食べなかったともある。基本的に、よほど信頼のおける場所以外では武士は外食をしなかったからだ。あちこちで外食をし、食あたりでも起こし、「お上」のために働く大事な身体に、万が一のことがあっては、危急の時に思うような働きができないから、というのがその理由だ。
なるほど、と深く頷ける理由で、何かと言い訳を探しては自分を甘やかそうとする私には、何とも耳の痛い心掛けだ。しかし、「わかっちゃいるけどやめられない」のだ。