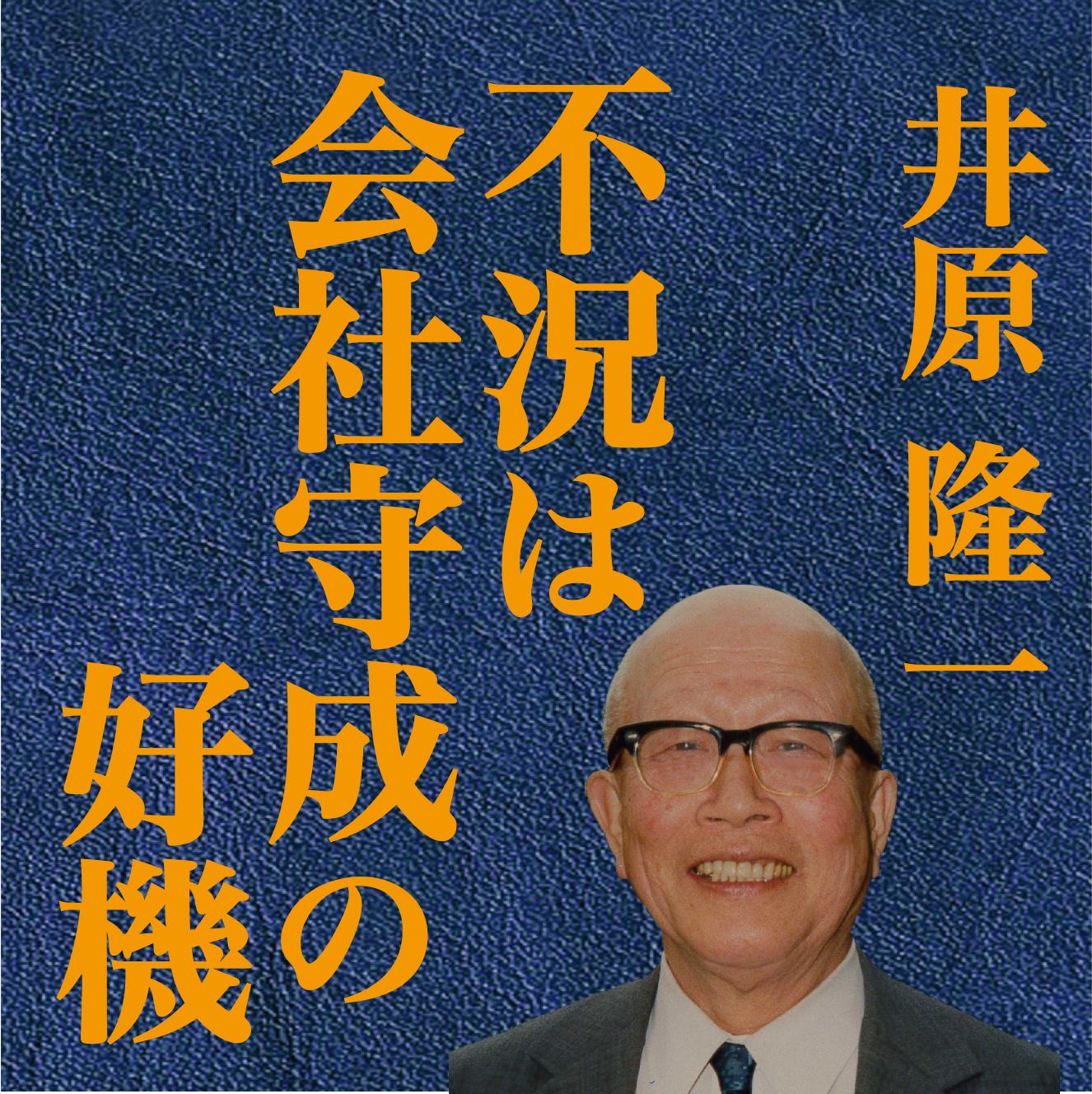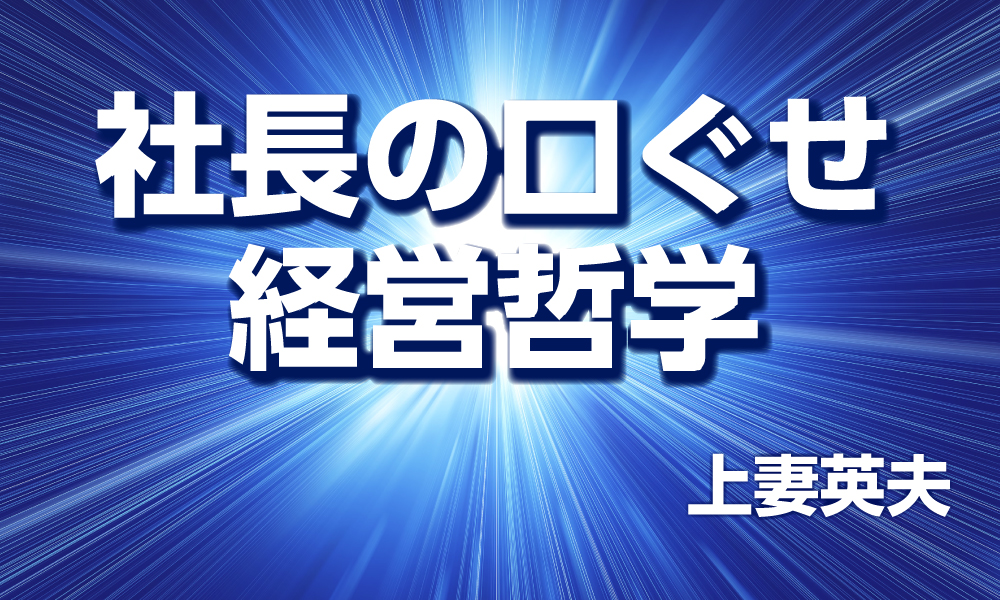二、三年に一度、老舗の和装小物店へ足袋などを買いにゆく。十年ほど前だったか、「十文七分(ともんしちぶ)の足袋を一足ください」と言ったら、主が「25.5センチですね」と言い、一瞬の間があった。「ご主人、これ、逆じゃないの? こっちが25.5センチって言って、あなたが、『和服の世界ではその寸法は十文七分と言うんですよ』ってなるんじゃない?」と言ったら、主曰く「今時、お客さんみたいな言い方される人はほとんどいませんよ。日本舞踊の方だって、センチでお求めになるんですから」とのこと。
我が身の時代遅れを嘆きながら店を出てそぞろ歩きをしながらも、どうも釈然としない。何がモヤモヤするのだろうと思ったが、主の言うことは今の時代の常識で、私が時代遅れなことは明白で、文句が言えた義理ではない。しかし、遥か昔になくなったはずの「尺貫法」という古来の日本独自の長さや重さ、体積などを計るために用いる度量衡が、実に合理的なだけではなく、今でも使われているところが沢山あることに気付いたからだ。
***
私は演劇関係の仕事をしている。舞台制作の現場では、古典芸能や現代劇に関係なく、まだ舞台の間口や高さなどをはじめとする長さを、「間(けん)=約1.8メートル」や「尺(しゃく)=約30センチ」で表現することはそう珍しくはない。「間口は三間か。じゃあ、両端は二尺ずつ殺そう」。「殺そう」とは物騒だが、「削る」「見えなくする」との意だ。
「三六(さぶろく)一枚」と言えば、幅三尺、長さ六尺(一間)の板などを指す。これは、建築の世界でも使われており、おおよそ90センチ×1.8メートルとなり、畳一畳の大きさだ。畳の寸法もさまざまで一概には言えないが、この寸法が主流ではある。この畳を二枚並べた正方形の大きさが3.24平米で、面積で言えば「一坪(3.3平米)」となる。
海外ではメートル、インチが主な長さの基準で、日本は明治24(1891)年に、それまでの「尺貫法」と併用する形で「メートル法」を採用した。当時は、なかなか新しい計量単位に馴染むことができず、「1メートル」が「三尺三寸(約99センチ)」に相当することから、「三尺三寸一命取る」と、刀の長さに引っ掛けた洒落で覚えた、とのエピソードも残っている。
インチが頻繁に使われるのは靴やパンツなどの服飾系だろうか。しかし、それから130年を経てもなお、日本古来の計測法は意外な場所で生きている。
今までは広さや長さの話だったが、容積を例に取れば、日本酒はいまだに「一合(180ml)」「二合」との呼び方が一般的だ。近年は「ml」単位で「90」、あるいは「120」など一合よりも少ない売り方をする店も増えて来た。これは、より多くの日本酒を楽しむためでもあり、自分のアルコール許容量を計るためには非常に便利だ。我々日本人は、こうしたものを巧く使い分けているが、それでも寒風吹きすさぶ日にはおでん屋で「熱燗で二合」と言いたくなる。
呑む話ばかりで恐縮だが、居酒屋の入り口などに「春夏冬二升五合」の看板を見ることがある。季節の「秋」がなく、酒の量が記してあるのは、「秋ない(商い)、升升(二升)半升(五合)」=「商い益々繫盛」の洒落だ。洒落や地口の講釈をするほど野暮な話はないが、優れたユーモア感覚だと思う。
変わったところでは、「登山」などがよい例だろう。頂上までをおおよその感覚で十に分割し、自分の現在地を「五合目」「七合目」などの言い方で表現する。この言い方は、登山だけではなく、他でも使われるケースがある。大きな仕事を抱えていて、現在の進捗状況を尋ねられた時、「そろそろ七合目かな」と言えば、そこに山がなくとも互いに共通した感覚は持てる。こうした形で定着してはいるものの、度量衡からはいささか外れるものかもしれない。
***
器用な日本人は、生活の中でメートル法と尺貫法を使い分けてきた。しかし、時代の変化と、度量衡の統一のために、法律で段階的に昭和33年と41年に「尺貫法を商取引に使用してはならない」と規定した。今までに私が例示してきたほとんどの物が、法的にはいけない行為だとなる。しかし、木造建築や和裁など、従来の測り方の方が馴染む仕事もあり、「例外」として認められてはいるものの、実際の運用に関しては役所への届け出が必要になっている。
これは、敗戦後の占領期を経て、急速にアメリカナイズした日本が、高度成長期を経て国際社会の仲間入りをするために必要だったのだとも考えられる。2回目の41年の法律は、土地・建物の取引に関する事項で、39年の「東京オリンピック」の後、45年の「万国博覧会」を控えたタイミングだ。こうした背景を考えれば、例外措置を残しながらも、法的に統一した国のやり方は無法とも言えない。
このこと自体に反対すべき理由は何もない。法は法で遵守する一方で、差し障りのない範囲でまだ「尺貫法」が我々の生活の中に生きているという現象が面白い。私がしばしば口にする「日本人の柔軟性」の素晴らしき点は、こうしたところにも現われている。日本人の考え方をいろいろな角度から眺めているのも飽きないものだ。