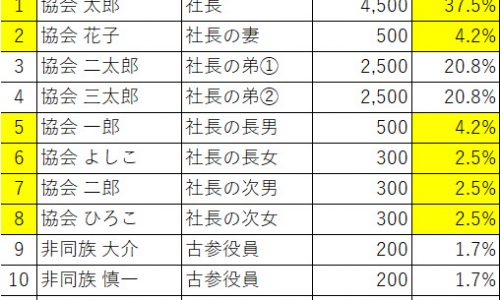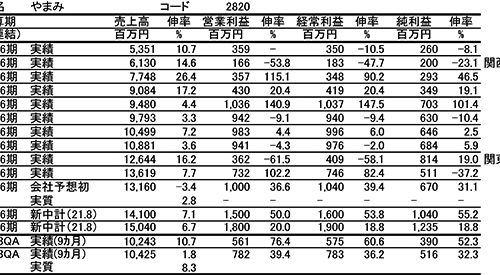「武士道と云ふは、死ぬ事と見付けたり」という『葉隠』の一節をご存じの方も多いだろう。これは、江戸時代中期、1700年代初頭に肥後国佐賀鍋島藩の藩士・山本常朝(1659~1719)が亡くなる数年前に口述した内容を、同じ藩の藩士が書物にまとめたものだ。
1868年、明治維新を迎え、「武士」は消滅した。しかし、「忠」「義」「礼」「孝」などの精神的支柱を基にした「武士道」は、日本発オリジナルの哲学・思想とも言える。「哲学」と言えば、デカルト、カント、ヘーゲル、ショーペンハウアーなど、ドイツを中心としたヨーロッパのもの、との感覚があるが、「武士道」は立派に日本が世界に誇れる哲学だと思う。
「武士道」の考えは江戸時代に発展・熟成し多くの書物で語られることになったが、武士自体は鎌倉時代にその政権が樹立しており、武士道「的」な考え方は、それ以前の平安時代にすでに萌芽があったとの説もある。江戸時代に盛んだった「朱子学」、「兵法」などが入り混じった上に、「武芸」の言葉が示すように、「武術」だけではなく「能楽」「茶道」などの芸術的素養も「嗜み」として加わり、「武芸百般」「文武両道」などの言葉にその面影を見ることができる。
「武士道」の文字が文献に登場するのは江戸時代以前、武田家の家臣・春日虎綱(1527~1578)が天正年間に口述したものを筆記した『甲陽軍艦』という兵法・軍学の書で、そこから前述のように多くの要素を呑み込みながら、発想自体が膨らみを続けた。
「武士道」に関する書物の中で特異な場所に位置付けられるのは、新渡戸稲造(1862~1933)による『武士道』だ。新渡戸は、幕末の生まれで、『武士道』を書いたのは明治33(1900)年のことで、当然ながら武士は存在していない。しかも著者の新渡戸は札幌農学校(現在の北海道大学)でクラーク博士から教えを受けたクリスチャンである。この書を著わした時期の新渡戸はドイツを経てアメリカ留学中で、静養のために休息していた時期に英文で書き上げ、帰国後、出版されたものだ。折柄、明治28年の日清戦争の勝利で大国を破った極東の島国、日本や日本人への関心が高まっていた時期でもあり、『武士道』はドイツ語、フランス語などに翻訳され、各国でベストセラーとなり、「サムライ」は世界的に認知されることになる。
国によっては、日本ではいまだに「サムライ」が歩いている、と思っているところもあり、私が2018年にカザフスタンの首都・アスタナ(現在はヌル=スルタン)で開催された「第二回世界劇場フェスティバル」へ招かれた折、「日本のクラシカル・パフォーマンスを見せてほしい」とのリクエストがあり、約90分のショーを構成・演出した。言葉の壁があるため、ノンバーバルに近い作品にしたせいもあり、侍と忍者が渡り合い、客席を走り回る場面では、劇場が総立ちになるほどの喝采を浴びた。親日国でもあり、大陸的な鷹揚さを持つカザフスタンの人々の歓迎は嬉しかったが、世界での日本文化の認知度を想った時、いささか複雑な気分になったのも事実だ。
閑話休題。新渡戸の『武士道』は今も読み継がれているロングセラーの名著である一方、キリスト教思想の上に立っている点で批判もある。そこに詳しく触れることはしないが、時代の変化と共に「ことば」の内容や意味合いが変わる中、どちらの意見が正しいという議論は不毛だろう。むしろ、明治以降、武士が存在しなくなってから、その根幹にある思想が、その時代や思想に都合よく使われてきた事実に関心を向けるべきだ。
第二次世界大戦中には、日本人には「大和魂」が求められ、「一人一殺」の精神での特攻が行われた。しかし、「大和魂」は『武士道』の本質とは関係がなく、中国的な物の考え方を意味する「唐心」に対する「やまと心」の表現の一種だ。それが、あたかも武士道の根幹のような錯誤を与えられたのも、「時代」によるものだ。「やまと心」は「一撃必殺」などの荒々しいものだけではなく、国学者・本居宣長(1730~1801)の「しき嶋のやまとごゝろを人とはゞ朝日にゝほふ山ざくら花」の名歌に象徴される繊細で儚い感覚までをも含んでいる。
昭和の高度成長も一段落した1970年には、作家・三島由紀夫が市谷の自衛隊で演説を行った後、切腹して自刃した。ノーベル賞候補の呼び声も高く、海外でも人気の作家が古の武士のように切腹をしたニュースは大事件として人々の記憶に残ることになる。三島の言う「益荒男」も、武士を意味する言葉とイコールではないが、あの衝撃的な映像や写真などで二つを結び付けるケースは多い。
こうして時代の変遷と共に「武士道」の根幹、あるいは周辺の思想は変容を遂げた。しかし、ここでスタートに戻って考えるなら、「忠孝」「信義」などの倫理的、道徳的規範の一つである。そこにある感覚は至ってシンプルで、教育現場に始まり、口を開けばハラスメントだらけで「物言えば唇寒く」、呼吸さえしにくいこの現代にこそ、「武士道」の基本を考える機会が必要なのではなかろうか。
侍は、ただ荒っぽく刀を振り回していただけではない。今に名を残す武将や兵法の学者たちの多くは、普遍的なインテリジェンスを併せ持っていた。その匂いが薄れると、本質が誤解され、修正できぬままに良くない利用のされ方もする。我々が「武士道」に学ぶべきことは少なくない。