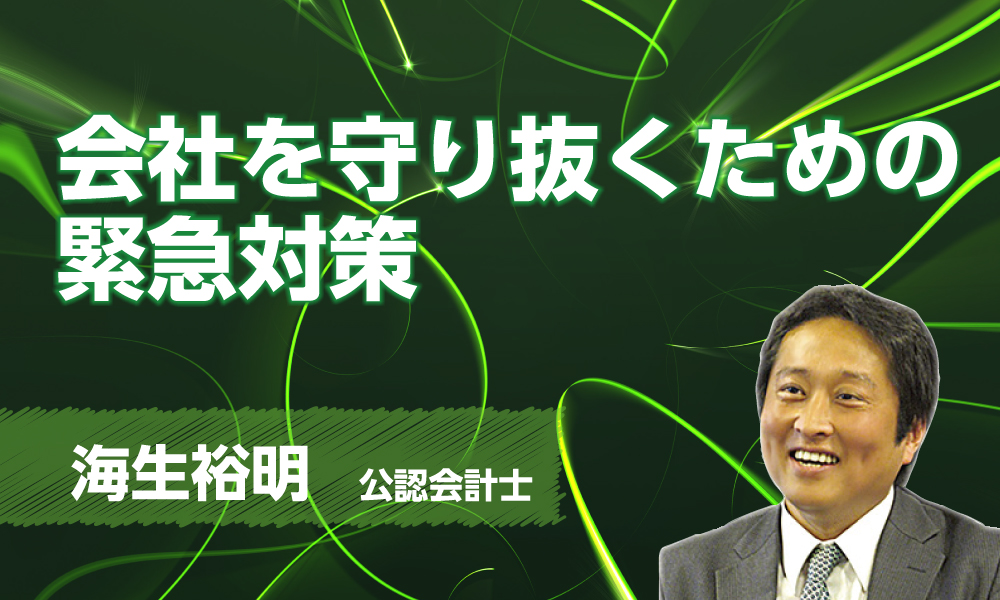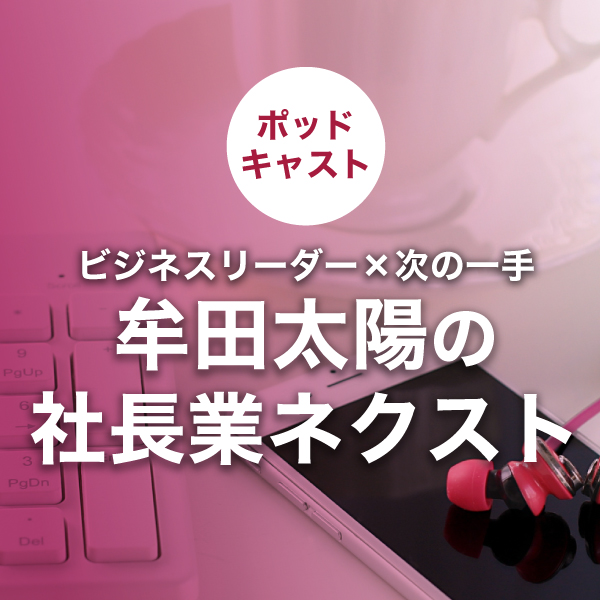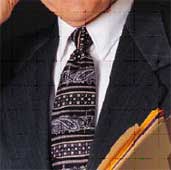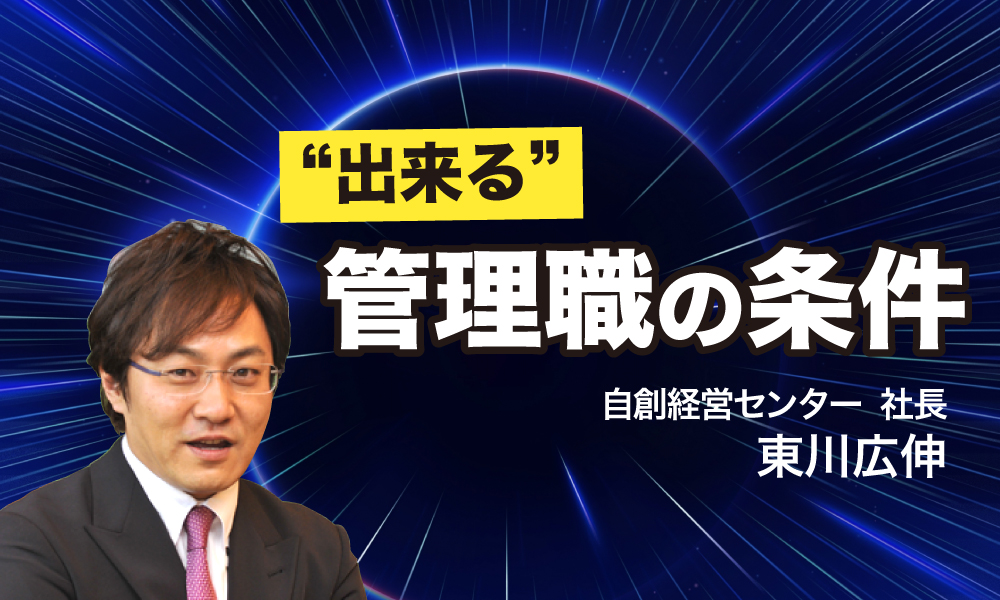俳優、平幹二朗(1933~2016)。女優・佐久間良子とも一時期夫婦であったことも知られる。82歳の時、入浴後、突然の死を遂げたが、それまでは元気に舞台を中心とした仕事で「名優」の評価を得ていた。亡くなる前に、最期の旅公演となった当たり役『王女メディア』では、旅公演にも同行し、3月に水戸で迎えた千穐楽を元気に終えた姿も観て、一緒に帰京した。それだけに、訃報を聞いた時は、誰かに騙されているようにも感じた。
ご本人の急逝で企画は幻と消えたが、私が旅公演に同行した理由の一つは、演劇批評家としての興味の他に、平さんの本を出そうという企画のためでもあった。当初、私の本を造りたいという申し出に対して、平さんは首を縦には振らなかった。
「有り難いお話です。そういうお話も何度かいただきましたが、みなお断りしています」
「それはなぜでしょう」
「私は、役者は泥沼の中の蓮のようなものだと思っています。お客様に観ていただくのは、泥沼を出て咲かせる花の芝居であって、わざわざ泥沼の中をお見せする必要はないでしょう」
平さんらしい、奥床しく、しかも付け入る隙のない答えだ。しかし、ここで納得してしまっては私の負けだ。
「お気持ちはよくわかります。失礼な事を申し上げますが、もう80歳を超えた大ベテランの経験談は、後へ続く俳優には立派な教科書になるでしょう。また、演劇に関係のない方々にも一つの道をひたむきに歩み続けた一人の人間の言葉から学び取れることは多いのではないでしょうか。まして、平さんは戦争を経験しておられます。それを語るだけでも、大きな意味があるのではありませんか」。
今度は平さんが沈黙し、その夜はそこで話が終わった。暫くして、プロデューサーから連絡があり、「平さん、中村さんのお話、受けるそうです。ついては、今度の『王女メディア』の旅公演にお越しいただいて、どこかの合間でお話されるのもいいのではないでしょうか」との予想を裏切る答えをもらった。その場で快諾したのは言うまでもない。
***
若い時期から劇団俳優座のホープとして活躍していた平が劇団を退団、初めて盟友の演出家・蜷川幸雄の演出で『王女メディア』を演じたのは、1978年、45歳の折のことだ。日比谷・日生劇場で、人形師の辻村ジュサブローのデコラティブな衣裳に包まれ、独特の表現が高く評価された。
以来、間を置いては上演を繰り返し、演出家も変わり、2012年には79歳で「一世一代」と銘打って東京だけではなく、地方公演も行った。この舞台が大好評で、2015年に「一世一代ふたたび」と題し、東京と、まだ廻り切れていなかった地域などを巡る旅に出た。この旅の東北公演に同行したのだ。
***
演劇の世界では、「新劇」と呼ばれるジャンルの芝居の旅公演は、予算も限られており、豪華なホテルに泊まるわけでもなく、時間の余裕も少ない。基本的に全員が同一の行動で、主役であろうと新人であろうと、同じビジネスホテルに泊まり、同じバスで次の公演地に移動する。そんな旅を長い間繰り返してきた平さんは、本来であれば特別扱いされてしかるべき立場であっても、いつも柔やかな微笑みを湛えていた。開演の2時間前には楽屋入りし、身体を温め、喉の調子、台詞の響きや動線の確認など、多くの事柄をチェックする。
82歳とは思えないエネルギッシュな行動力と、舞台に賭ける真摯な姿勢。多く人が観ているわけではないところでのコツコツとした日々の努力がいかに大事かを、無言で教えてもらったような気がした。夜の部の終演後、二人だけで食事に行く機会もあったが、過去の自慢話や何かを教えるという態度を取ることは一切なく、時折冗談を交えながら、幅広い豊富な芝居の話題で食事も進んだ。普段はアルコールを嗜む平さんだが、旅公演の間は、翌日の舞台を考え、アルコールは一切口にしない。この折も、いい気持で酔っていたのは私だけだった。
『王女メディア』は休憩なしで約2時間20分の舞台だ。主役であり、その間出づっぱりながら、どんな小さな囁き声でも、客席の一番後ろまではっきり届いたのは、最年長の平さんだった。ある俳優は、その様子を「平さんは全身が楽器だから」と例えた。そのコンディションを維持するために、人一倍の神経を使っただろう。俳優は肉体が資本で、健康維持のために稽古場まで10キロ程度の場合は歩くこともあると聞き、己の怠惰に恥ずかしい想いもした。
***
日々、それだけの努力を積み重ね、『王女メディア』と足掛け38年向き合ってきた、千穐楽の前の夜、一日早めの打ち上げがあった。キャストもスタッフも揃って美味しい夕食を楽しんだ後、ブラブラその日の宿舎へ歩きながら、翌日の舞台の話をした。「最後の一回をどうするか。今まで通りに演じるか、表現方法を変えるか」。私は、後者を勧め、平さんもそれを選んだ。
千穐楽の舞台の出来は「凄まじい」とも言えるようなもので、82歳という年齢ではあるが、まだまだこの作品を上演できる、と確信させるほどのものだった。東京へ帰る電車の中、平さんは言った。
「千穐楽の今日になって、ようやく初日が出た想いですよ」。
梅が終わる頃に公演を終え、秋から本づくりを再開しようとしていた折に、信じられない知らせが飛び込んだ。
平さんは、大輪の蓮の花を咲かせた後、結局、蓮の泥沼の中を見せることなく、再び戻ってしまった。人の生き方に「美学」というものがあるとすれば、平幹二朗のそれもまた、美学だったのではないだろうか。