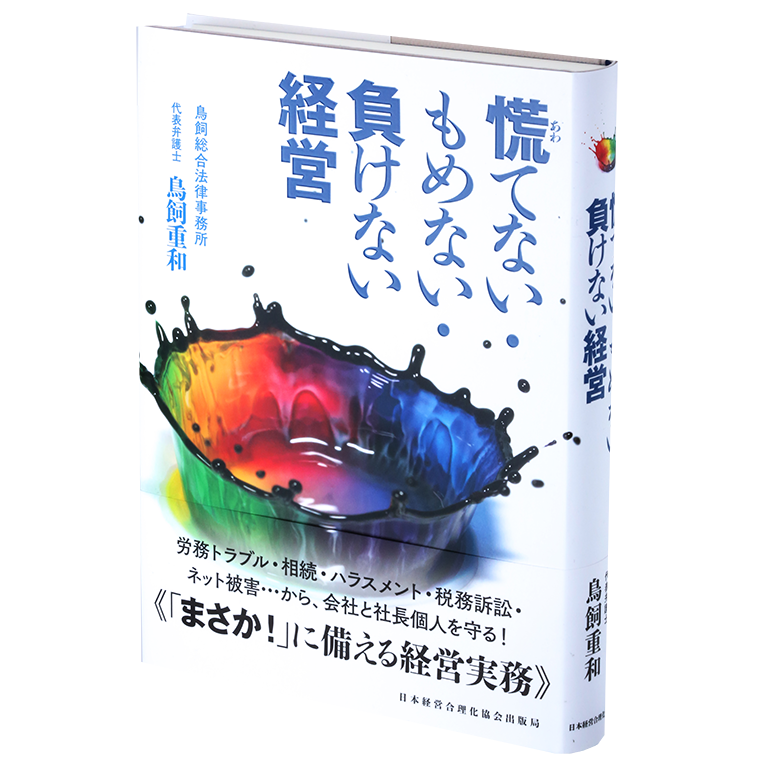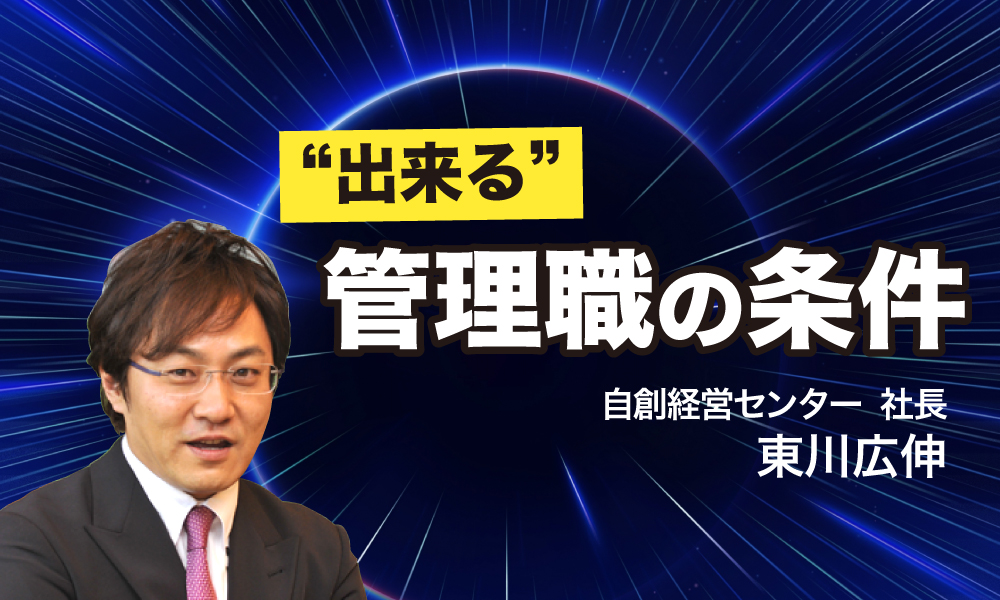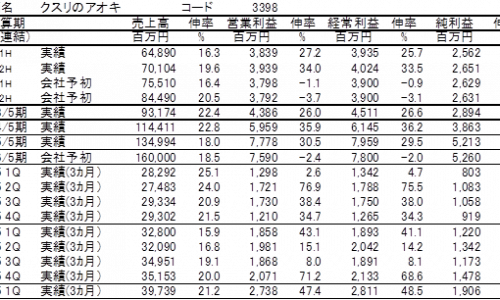生成AIの業務への活用を検討している田中社長は、賛多弁護士のもとを訪れました。
* * *
田中社長:最近、ChatGPTなどの生成AIサービスが注目されていますね。
賛多弁護士:生成AIは本当に便利ですよね。私も、今まではインターネット検索していたものを最近ではAIに質問するようになりました。たとえば、冷蔵庫にある食材から作れる料理のレシピを聞いたりしています。
田中社長:当社でも、業務に生成AIを業務に活用できないかと考えているのですが、導入にあたって留意すべき点はありますか。
賛多弁護士:会社の業務に外部の生成AIサービスを利用する場合、いくつか法的な留意点があります。今日は、特に重要な3点についてお話しします。
まず1点目は「個人情報保護法」に関してです。
個人情報保護法では、個人情報取扱事業者に対して、①利用目的の達成に必要な範囲を超える利用の制限や、②第三者提供の制限を課しています。
①利用目的との関係では、生成AIに個人情報を入力する行為が、会社のプライバシーポリシー等で公表している利用目的の範囲に含まれているか否かを確認する必要があります。利用目的の範囲内に含まれていない場合は、原則として本人の同意が必要となります。
②第三者提供との関係では、入力した個人データが、生成AIサービス提供者の利用規約や設定において機械学習に利用されることとなっている場合には、第三者提供に該当する可能性があります。そのため、利用規約や設定内容の確認が不可欠です。なお、第三者提供に該当する場合も、原則として本人の同意が必要となります。
田中社長:なるほど。生成AIサービスに個人情報を入力する際には、当社が定める利用目的の達成に必要な範囲内であることを確認することやAIサービス提供者の利用規約や設定内容を確認して、慎重に運用することが大切ですね。
賛多弁護士:そのとおりです。続いて2点目は『著作権』に関してです。
生成AIと著作権の関係については、「AI開発・学習段階で既存の著作物を利用することの適法性」や「AIの生成物に著作権が認められるか」など様々な論点がありますが、今回は「生成・利用段階での著作権侵害」に絞ってお話しします。
著作権侵害が成立するのは、①既存の著作物に依拠して(依拠性)、②当該著作物と同一又は類似する表現物が利用された場合(類似性)です。
そのため、 生成AIによる生成物を利用した場合、意図せず第三者の著作物と類似していたとしても、依拠性が認められなければ著作権侵害とはなりません。
ただ、高度に類似性が認められれば、依拠性が推認される可能性もあり、著作権者から権利侵害を主張される可能性も否定できません。
田中社長:知らないうちに、誰かの著作物と類似するものを利用してしまって、それが著作権侵害だと言われたら非常に困りますね。
賛多弁護士:おっしゃるとおりです。また、生成AIは「ハルシネーション(幻覚)」と呼ばれる現象を引き起こすことがあり、もっともらしい内容に見えても、実は誤った内容の生成物を作成することがあります。
そのため、生成AIの生成物をそのまま使用せず、自ら内容の確認や編集を行うことが重要です。そうすることで、内容の正確性を担保することができるだけでなく、既存著作物との類似性を避けることができ、著作権侵害のリスクを実質的に低減することにもつながると考えられます。
田中社長:なるほど。社内では、生成AIが出力した内容をそのまま使用することを原則として禁止する運用も検討すべきかもしれませね。
賛多弁護士:そうですね。そして、3点目は『不正競争防止法』に関してです。
不正競争防止法は、「営業秘密」に該当する情報を保護し、これを第三者が取得・使用することを不正競争として規制しています。もっとも、「営業秘密」としての保護を受けるためには、当該情報が秘密として管理されている必要があります(秘密管理性)。会社が秘密として管理している情報を生成AIに入力してしまうと、それによって秘密管理性が失われ,営業秘密としての保護が受けられなくなる可能性があることにも注意が必要です。
田中社長:よく分かりました。生成AIを安全に使うために社内でルールを定めようと思います。
賛多弁護士:それは適切な対応です。社内ルールを作成する際は、日本ディープラーニング協会が公表している「生成AIの利用ガイドライン」等を参考にしながら、社内でガイドラインを作成し、従業員への周知・教育行うことが大切です。
田中社長:ありがとうございました。
* * *
近年、生成AI技術が急速に発展を遂げています。それを上手く活用し業務効率化を図ることは、大企業だけでなく中小企業にとっても重要なテーマとなりつつあります。
一方で、生成AIの活用には、個人情報保護法違反や著作権侵害、営業秘密性の喪失などの法的なリスクも伴うため、これらのリスクを適切に管理したうえで、生成AIを活用することが求められます。
※参照資料
・生成AIサービスの利用に関する注意喚起等について(個人情報保護委員会HP)
https://www.ppc.go.jp/news/careful_information/230602_AI_utilize_alert/
・生成AIの利用ガイドライン(一般社団法人日本ディープラーニング協会HP)
https://www.jdla.org/document/#ai-guideline
・AI と著作権(文化庁HP)
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/aiandcopyright.html
執筆:鳥飼総合法律事務所 弁護士 橋本充人