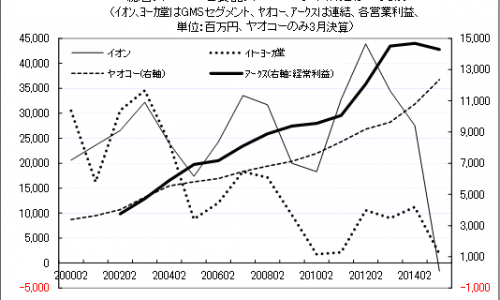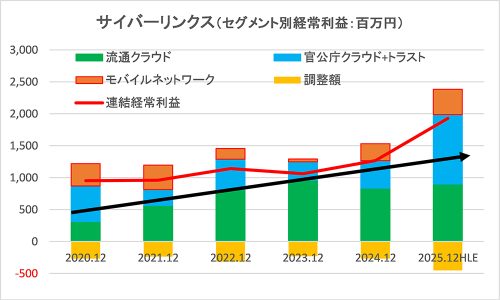本田宗一郎の「波瀾もない平凡な人生」
16歳で東京・本郷の自動車修理工場「アート商会」に奉公に出たのを皮切りに、22歳で故郷の浜松に戻り、自動車修理を創業――ホンダの創業者本田宗一郎の1955年時点での回想だ。
未だ私は、自らの人生を顧みるという、大袈裟なことの出来る年齢にはなっていない。人生五十年、教訓もなく、劇的な波瀾もなかった。ただ平凡にオートバイのエンジンに取っ組み、他愛のない悪戦苦闘を続けてきただけである。しかし、それでいて、ただ一つ言えることは――それは、一本に打ちこめる仕事をし続けてきた、ただそれだけなのである。
波乱万丈の半生を「波瀾もない平凡な人生」とさらっと言っている。それはホンダの本心だったに違いない。寝食を忘れ、親兄弟を忘れ、金銭を忘れ、名誉を忘れ、世俗の野心を忘れ、好きなことに思いっきり打ち込む。本田にしてみれば、好きなことをただひたすらにやってきただけのことだった。
まずは、こと程左様に、生まれついて誉められることをしたことのない私だったが、完全に魅入らせられ、参ってしまったものに自動車がある。小学校四年生頃、村に初めて動く車体が、青い煙を尻からポツポツとふきながら、通ったのである。
私はそのガソリンの匂いを嗅いだ時、気が遠くなる様な気がした。普通の人のように、気持ちが悪くなってではない。胸がすうとしてである。その耐まらない香りは幼い私の鼻を捉え、私はその日から全く自動車の亡者みたいに、走るその後を追っかけ廻した。金魚のふんだと笑われながら、自転車がすり切れる程、ペダルを踏み、自動車の後を追って、ガソリンの芳香をかぎ悦に入っていた。
道に油がこぼれていると、それに鼻をくっつけ、匂いを存分にかぎ、時間が経つのも忘れた。そしてその日のご飯の、何と美味しかったことか。
そのときから、いつか自分の手で自動車をつくり、運転して、思いっきりすっ飛ばすことが本田の最大の望みとなった。そして、現実にその望みを実現した。
「好き嫌い」の人、本田宗一郎
彼は徹頭徹尾「好き嫌い」の人だった。彼の記事や対談には、やたらと「好きだ」「好きになれない」「嫌いだ」「いやだ」「気に入った」「気に食わない」という表現が出てくる。30年後の『文藝春秋』1985年6月号の対談記事にある藤沢武夫との邂逅についての回想。
売ったつもりだけど、金が取れんのです。技術屋だから。つくることはやるけれど、金よこせって、どうも言いにくいんだな。遠慮するわけでもないのだけれど、なにか、こう、いやなんですね。(中略)どこかに、うまく金の取れる商売人がいないかなと友人に相談したら、商売上手な男がいて、たぶん遊んでいると思うからと、紹介してくれた。それで、その人物に浜松のわが家まで来てもらって、うちの女房がつくったソバを二人で食いながら僕の腹の内を話したわけ。
終戦直後の本田は、一年間何もせずに「毎日遊んで」いた。これからの世の中が分からなかったからだ。
一年間遊んでいて、頭を冷やして、戦後民主主義というものの考え方をみていたんです。私には、民主主義というものがよくわかりませんでしたから。一年たつうちにわかるだろうというので、アルコールをドラム缶に一本買ってきて、友人を大勢読んではそれを薄めてみんなで飲んで、ちょうど一年間で飲みつくしてしまった。(笑)(中略)一年で見事にわかった。民主主義がわかっていれば、私だってすぐ仕事をしていましたよ。ところが天皇制下の教育を受けていますから、すぐ民主主義といわれたって、わからないんです。世間がわからないのに仕事をするというのは、地盤の柔らかいところに物を建てるみたいなことだからやめた方がいい。
本田宗一郎の「経営者としての真髄」
経営者にとっていちばん大切な資質をひとつだけ挙げろと言われたら、「人間と人間社会についての洞察」と答える。この言葉に本田の経営者としての真髄を見る。
私は儲けたい、幸福になりたい、女房に内緒で遊びたいという、普通の男です。ただ、もし企業家として他人と違うとしたら、人に好かれたいという感情が強いということでしょうね。
本田は技術もバイクもクルマも好きだが、それ以上に人間が大好物だった。このことが尋常ならざる人と人の世に対する本田の洞察力の基盤にあった。どうすれば社員がやる気になるか。どうすれば取引先が気持ちよく協力してくれるか。何よりも、どうすれば顧客が喜び幸せになるか――本田の思考と行動は常に深い人間洞察に基づいていた。
一流の技術者であった本田宗一郎は、それ以上に超一流の経営者だった。