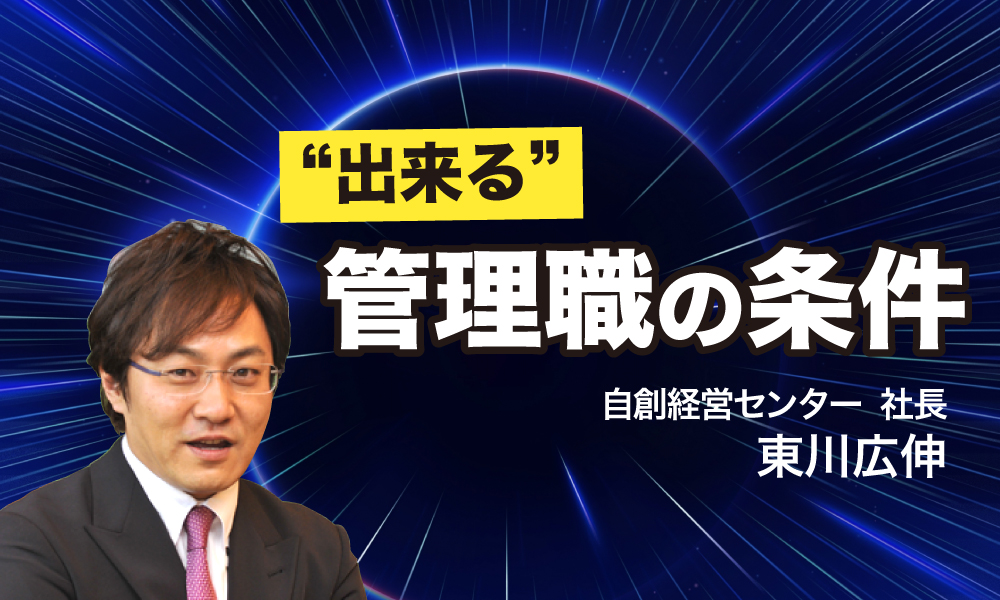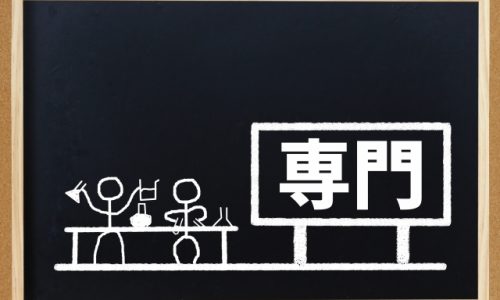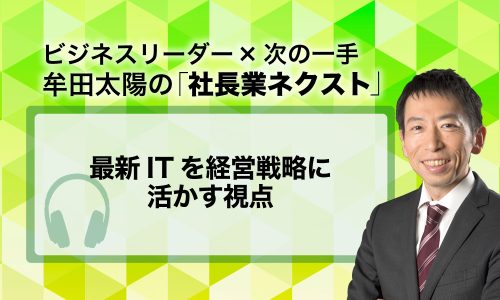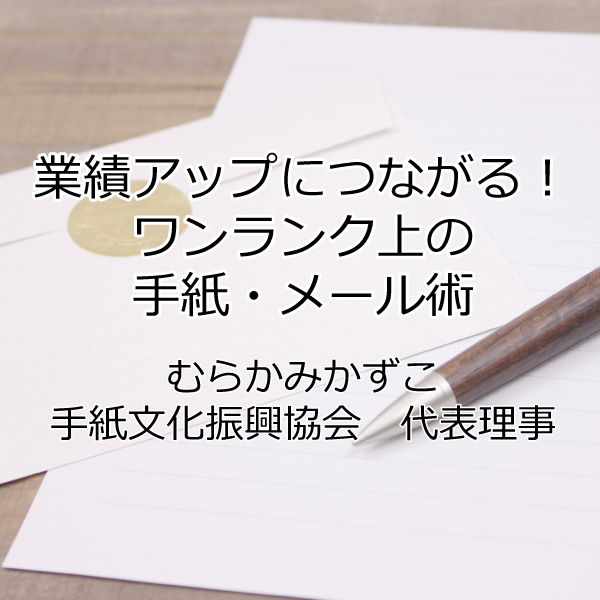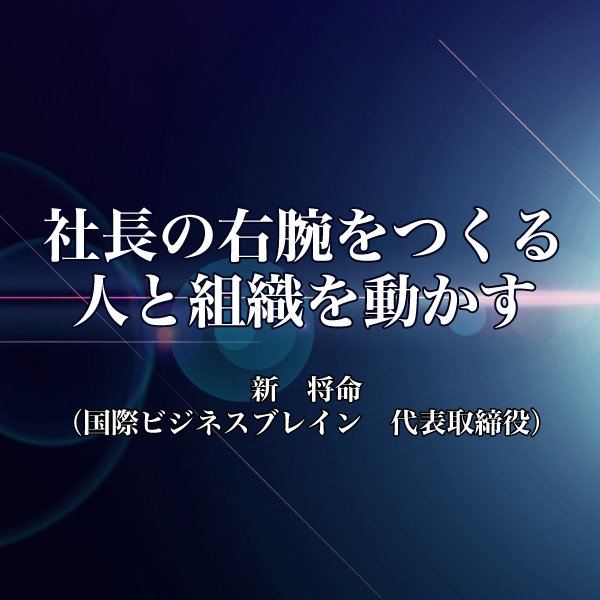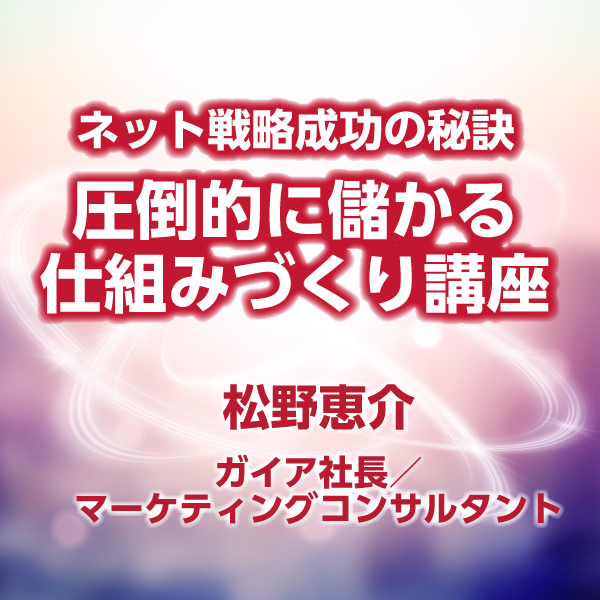やってはならないことのオンパレード
昨年暮れに一部週刊誌が報じたタレント中居正広の女性トラブルは、スポンサー離れと投資ファンドの反発を招いたフジテレビの存続を脅かしかねない混乱に至っている。彼が何をしたのかは、「和解解決による守秘義務」を盾にいまだ藪の中だが、中居本人が、「トラブルがあったのは事実」「相手の女性にも心からお詫びをしたい」として自らの非を認め、芸能活動からの引退を表明したことから、その悪質性について、およその見当はつく。いずれ、第三者委員会の調査で女性が被った被害事実の骨格は明らかになるだろう。
問題の本質は、早い段階で彼と局関係女性との間の深刻なトラブルを知りながら、結果的に隠蔽し、報道で発覚するまで彼を起用し続けた、フジテレビの報道機関としてあり得ない対応にある。
企業のトラブル対応、危機管理についてアドバイス業務を行なっている筆者から見ると、トラブル発覚後の同社の対応は、「やってはならないこと」のオンパレードで、あなたの組織でもし危機が起きた場合の参考になるだろうから書いておく。
記者会見は事態をコントロールする好機と心得よ
企業活動にとってトラブルは不可避である。トラブル発生時の危機管理を指導する際の要諦は、「素早く火を消す」ことにある。消すと言ってももみ消すことではない。社会の企業、組織に対する評価は、トラブルが起きたことにあるのではなく、それにどう対応したかで決まる。危機への対応を世間(顧客、取引先)は見ているのだということを忘れてはならない。
事態発覚後、「これからどう立て直すか」をアピールする重要な機会が記者会見なのだ。吊し上げに耐える場ではない。ここで世間の評価はほぼ決まると言ってよい。不祥事から逃げるのではなく、事態をコントロールする機会なのだ。筆者は、不祥事を招いた後の記者会見に臨む際の基本心得を次の3点で示している。
① 把握している事実関係は隠すことなく示し謝罪する→全て「ノーコメント」「調査中」で通せば、隠蔽体質だと非難され、不毛な会見を繰り返す羽目になり、社の評価は地に落ちる。
② 原因となる組織的欠陥があれば追及される前に自ら示す。
③ 再発防止策について可能な限り処方箋の方向を示す。
ところが、港浩一社長(当時)が行なった1月17日の会見は、参加者を記者会所属の記者に限定し、テレビカメラも排除したクローズドな会見となった。さらに港社長は、事実関係の確認を求める質問に、「被害女性に配慮が必要」「(日弁連の指針に基づかない)第三者の弁護士を中心とする調査委員会に委ねる」としてほぼゼロ回答だった。しかも「この調査委員会では客観性を担保できないのではないか」との批判がでて、その後、「日弁連指針に基づく第三者委員会」に訂正している。「やってはいけない会見」のお手本だ。結局10日後にオープンなやり直し会見を行うことになり、「早めの火消し」どころか、火に油を注ぐ結果となった。フジテレビの評価は地に落ちたのだった。
機能しないコンプライアンス部署
かつてないほどに企業のコンプライアンス(法的遵守原則)が叫ばれている。TBS系テレビで昨年放映されたドラマ『不適切にもほどがある!』で戯画化して描かれたように、報道使命を帯びる放送局なら当然、その体制を充実させているはずだ。フジテレビのホームページでも、コンプライアンスガイドラインを示した上で、「コンプライアンス違反やハラスメントなどの相談ができる社内相談窓口と社外相談窓口を設置」し、「フジテレビで働く全ての関係者を対象にしている」と強調している。
今回の事案は、明らかにタレントによる局関係者へのセクシャルハラスメントに該当する事案だった。にもかかわらず、トラブルの発生後、早い段階で関係者が相談を受けたものの事案は内々に処理され、社長にまで報告が上がったが、「当該女性のプライバシーを考慮し、なるべく少人数のみの扱いとした」と会見で回答している。人権意識が希薄なのだ。コンプライアンス担当の取締役は、「トラブルの発生は、(事案発生後一年半後の)週刊誌の取材で初めて知った」と会見で暴露している。信じられない話である。何のためのコンプライアンス相談室なのか。
トラブルをできるだけ内々に処理しようとしたことは明らかだ。それこそ「隠蔽体質」だろう。
では、なぜコンプライアンス上、無視できない事案を伏せようとしたのか。本当に「被害女性のプライバシーを守る」ためだけだったのか。あるいは、人気番組に起用することで視聴率稼ぎが絡む人気タレントを守るためだったのか。それとも、他に守るべき社内関係者がいるのか。
いずれにしても、この不祥事を公にしないことが得策と考えるような組織運用、経営体質に重大な欠陥があることは間違いない。闇は深い。 (この項、次回へ続く)
(書き手)宇惠一郎 ueichi@nifty.com